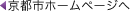学区案内/滋野学区(しげの) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
ページ番号29008
2014年6月16日

官民共存の気風が受け継がれる街
■学区の概要と歴史
滋野学区は,下長者町通(鷹司小路),烏丸通(烏丸小路),丸太町通(春日小路),堀川通(堀川小路)によって囲まれた地域です。かつて平安京の頃は,大内裏に近接し,比較的土地条件等もよかったため,律令政府の役人や技術職員たちが居住し勤務する官衙町および高級貴族の邸地となりました。
官衙町の周辺には,その空間を埋めるようなかたちで,貴族の邸宅が建てられるようになっていきました。また,西部では,本院,滋野貞主邸,高陽院,東部では菅原院,近衛殿,枇杷殿などが著名なものといえます。平安時代中期以降,高陽院や近衛殿なども,しばしば里内裏となり,王朝政治の舞台となりました。衰退期とはいえ,政庁の場として組み込まれたことにより,この地区が急速に発展したことは,充分うかがわれます。
しかし,応仁の乱などによる戦乱によって,古代的景観はまったく失われ,このあたりは武家の陣所へと変貌していきます。代表的なのは斯波氏(武衛派)の館で,その武衛陣が修築されて,将軍足利義輝の武衛陣第(室町御所)に。そこがまた織田信長によって拡築され,将軍足利義昭の御所となっていきます。しかし,政情不安な時代に武家の陣所となることは,そこが戦場ともなることを意味し,事実,義昭と信長の対立から,この地は戦場となって荒廃していきました。
その後,豊臣秀吉による都市改造を経て,江戸時代には,禁裏,公家町に近接する町人の街として発展。ここには両替商や幕府・諸大名の呉服所,用達所などを請け負う特権的御用町人が,数多く軒を並べていました。
こうした御用町人たちは,興亡が激しく,また競合心も強かったから,町組や町の運営も相当難しかったみたいです。もちろん,大町人の没落と拮抗するかのように,堅実な町人たちも勃興したし,伊藤仁斎のように地域にしっかり根をおろした文化人も育ちました。この地がたびたびの火災で繰り返し焼亡しつくされたことや,幕末の広大な京都守護職邸設置によって多くの町が廃町となったこと,また明治以降,京都府庁に隣接する地が,種々の官公府舎となり,市民生活の場が制限されていったことも,町の歴史的性格形成に大きな影響をあたえたことは確かです。

四町目町の記念写真
滋野今昔
■名水「滋野井」について/加藤義昌さん
山紫水明の地と昔から名高い京の街,とりわけ上京地域の水が非常に良く,ここ滋野学区に「滋野井」という京の7つの名水の1つがあり,学区名称の元となっています。詳しく述べますと平安初期の公家滋野貞主の邸宅があり,その後,鎌倉時代に蹴鞠の達人藤原成通が住み蹴鞠発祥の地といわれています。今も蹴鞠についての興味ある話が残っています。それは申の月,申の日,申の時刻に「蹴鞠」も神が3匹の猿の姿となって,この井戸に現れ「蹴鞠」の法を伝授したと伝えられています。そしてその孫の宗長,雅経はそれぞれ難波家,飛鳥井家として「蹴鞠」の宗家となりました。
残りの「7つの名水」を述べますと,この歴史に残るほどの井戸は上京区に大部分集中しており,それは現在の小川通(昔は川でした)を中心に,東西を挟むように点在しています。今出川通から北では千家の井戸があります。次に出水烏丸西に湧水で清らかな名水があって,現在の出水通の地名のもとになっています。次に大宮丸太町あたりに金名水があり,戦前まで酒造業者の仕込みの水として使われていました。次に中京の三条西洞院あたりに「上柳水」「下柳水」の名水があり,織田信長の弟信雄邸跡に在り,千利休が専ら茶の水として愛用していたとの史実があります。次に南に下がりますが六条通醒ヶ井上ルあたりに,足利義政の愛用した「佐女牛井(さめがい)」がありました。次に京都御苑敷地の西側,中立売御門を南に下ったところに「縣井」があります。現在はその場所より10メートル程南で新しく深井戸が掘られて,水が出て色々と御苑で利用されています。このような名水は,どのような地下条件で出るのかと,不思議に思っていましたが,昭和30年頃に,私方の「滋野井」の水を利用したかったために,5メートルほど掘り下げ工事をした時,地質が解明し,それは砂利とコブシ大の小石の地層でした。昔の川原の跡であろうと判断された次第です。地下水の元は貴船の辺りより,延々と地下を流れ市内に至っているようです。ちなみに今の地下水は,約100年位昔の雨水が歳月を経て,現在の市内の地中を流れて,私たちに美味しい水を与えてくれています。

「滋野井」
■腹帯地蔵のはなし/長坂益雄さん
今の日赤病院のすぐ隣に「腹帯地蔵」があるのをご存知でしょうか。昔,お公家さんが無事出産できたことに感謝して,腹帯を洗ったといわれる川の側にあった地蔵さんです。もともとは,新町通下立売下ルにあった腹帯地蔵ですが,天正13年に京極六角南に移され,明治6年に廃されました。椹木町までの両側町を腹帯町といい,以南丸太町までが春日小路にちなんで春日町という両側町でしたが,守護職邸が設置された年の翌年,御添屋敷のために両町共西半分が除却となり,明治2年に合併して,長二町の春帯町になりました。町内西の釜座通までに市立京一工(洛陽工高)の前身の染織学校や日本初の盲唖院があったところです。

日本最初盲唖院創建之地跡碑
滋野小学校
■滋野小学校の思い出/長坂益雄さん
昭和初年はラジオが普及しだし,レコードが販売され,活動写真が盛んに興行されるようになった頃ですが,地味で堅実な両御霊町では,流行歌を歌えば親に叱られるし,活動写真といえば時たま中立売署のグラウンドに支柱と白布で作った映写幕で写される野外映写会を見る程度でした。折から,満州事変・上海事変と戦火が上がり,子供たちの歌にも軍国調が登場してきた時代です。
大正年度最後の15年2月生まれの私は,早生まれとして昭和7年4月に滋野尋常小学校に入学。「ハナ,ハト,マメ,マス」で始まる国語読本を使用する最後の小学生でした。学校には大きな銀杏の木があり,悪いことをした児童は,よくその下で立たされていました。夏休みともなれば,眠たい目をこすりながら毎朝ラジオ体操へ出掛けました。正月3カ日は凧上げに夢中になっていました。凧は滋野校正門前の文林堂や近所の一文菓子屋で買ったものです。幼い子供は1銭の奴凧で新町通を走るだけでしたが,年長の子供は絶好の凧上げ場になった府庁前で西風に乗せながら,豆粒のように見えるまで凧上げに興じていました。もっとも,そこまで上げるのが苦労で,大勢の凧上げ子供の凧糸に引っかからないように上げるのは至難の業でした。昭和12年頃,学内に立派な土俵を造り,土俵開きがおこなわれました。大きなお相撲さんが来ていたのを覚えています。
体操風景(昭和初期)
■滋野尋常小学校の同級生/堤康男さん
明治25年に,全市学区変更により,第20,第21の両区併合して上京第16区となり大路・興文の両校も合併して大路小学校に移る。その後,滋野尋常小学校として開校される。校地が,平安朝初期の碩学,滋野貞主跡であったことから,校名を「滋野」と名づけられた。これが滋野尋常小学校のはじまり。
古稀もいつの間にか過ぎ,枯淡の域に迫りつつある今日この頃,よく鵜飼正造君がやって来る。彼も私も滋野尋常小学校,昭和14年3月の卒業生である。彼は医者いらずの元気者。毎年続いている級会で,少年少女に戻ってワイワイがやがやと賑やかだ。彼の顔には,人生は楽しいものだ,人生を楽しもうよと書いてある。今日も彼がやって来るかなと心待ちしている……。

土俵開き

校門(昭和4年)
■小学校で防空演習/野田進一さん
戦時中,蒲団を持ち込んでの防空演習があったのを思い出します。緊迫した状況にあっただけに,児童を集めて,作法室に蒲団を敷いて夜中にサイレンが鳴り響き,校庭に集まるという退避訓練をしていました。当時は,みんなと一緒に泊り込むことがなかっただけに,それが結構楽しかったんです。そういえば,正親学区に爆弾が落ちた時,その破片がここ滋野学区の私の家の前まで飛んで来たのには驚かされました。その場面を防空壕から見ていました。すぐに警察が処理しに来ましたけど。どの家にも防空壕があった時代です。あの頃の下長者町通は今みたいに広くなく,現在あるマンホールが道の真ん中という狭い道でした。あの辺りは強制疎開で北側の家もなくなり,そこを掘って防空壕にしていました。どこの家庭でも,家の裏まで掘って避難路を確保し,屋根に焼火弾が落ちた時の対処として天井を抜いていました。
今,平和の尊さをしみじみ感じます。

作法室

アクメ紫外線室(太陽燈)
■大きな銀杏の樹/森修一郎さん
♪ゆかりもしるき 学び舎の 滋野
てふ名の 尊しや…
校歌の滋野は,昔のままに存在しています。校樹の銀杏の樹は厳然とそびえ校舎を見下ろしていました。友達みんなをやさしく見守ってくれていました。でも,その銀杏も今はなく,時の流れとはいえ寂しい限りです。大空に大きく張った枝も年を重ねるごとに切り取られ,遂に校舎の建替えの犠牲となった銀杏の樹。あの下で,元気よく過ごした小学生の頃がとても懐かしく思います。
滋野小学校校歌
- ゆかりもしるき 学び舎の
滋野てふ名の 尊しや
その名にはぢず 朝夕に
人たる道や なすわざを
つとめはげみて みがかなん - 比叡のおろし をりをりは
御苑を吹きて わが校の
いてふに清く おとづるる
さやけき庭に つどひきて
遊ぶもたのし 友どちと - をしえの露の しげき野に
おひし我等は 秋草の
千々にさき出て 世の中に
家のほまれや 学び舎の
名をば錦と かざらなん

懐かしの大公孫樹
滋野点描
■府庁前を市電が走っていた/池崎照夫さん
明治28年,京都電気鉄道(京電)は,日本で初めての路面電車として京都に登場。市民からチンチン電車の愛称で親しまれていました。「電車が来まっせえ,危のうおまっせ!」と声をあげながら,告知人と呼ばれる先走り人は,汗まみれになって電車の先5間(約9メートル)以内を走っていたそうです。その場所を電車が通り過ぎると,走っている電車に飛び乗るのですが,失敗してケガをする告知人も多かったと聞きます。告知人にとって,特に夜間は全線にわたって電車の前を走るという重労働だったため,1日勤務すると2,3日休むということもたびたびあったらしいです。先走りは昭和31年9月で廃止になりましたが,「先走り」という言葉はここから出たという説もあります。告知人は年齢12~15歳くらいの少年たちで直接雇用ではなく,請負の親方が会社と契約していたといわれます。
京電の堀川線は,中立売が終点でした。明治33年(1900)に中立売通を北野まで延長することになりましたが,電車は直角に曲がれません。ゆるい弧を描いて方向を変えた所で,堀川に鉄橋を架ければよいのですが,土地の買収で行き詰まっていました。そこで考案されたのが,円形の転車台という設備です。終点の広場へ東北向きに入った電車(乗客を乗せたまま)を台に乗せて,ポールをはずすと,車回しの人が人力で電車の向きを西向きに変えていました。転車台に乗るとき,勢いあまって電車が飛び出し,何度も同じ民家に衝突したというエピソードも残っています。
府庁前の下立売通は,電車が通っていただけあって道幅が広くて電柱などの障害物も少なかったため,車の通行のほとんどない正月3カ日は絶好の凧上げ場になっていました。

京都府庁前を走る京電。
この道は堀川中立売に通じている
(明治28年9月頃)

京都府庁(明治中頃)

京都守護職屋敷跡碑
■府庁について
現在の府庁所在地には,幕末,文久3年(1863)に京都守護職屋敷が建てられる。明治元年(1868)軍務官屋敷になり,明治2年にはこの地に府庁が移転したが,明治5年には二条城に移転しています。その後,明治6年に仮中学校(明治5年の「学制」の発布に伴い,仮中学校と称した京都最初の中学校「京都中学」)が移転。この間,明治7年には当時の槇村大参事が福沢諭吉に要請し英学を教える京都慶應義塾を設置(1年足らずで閉校)。京都中学は明治17年上京区寺町荒神口下ルに移転。明治18年に,京都府庁が移転してきました。
今も残る後期ルネサンス様式の府庁旧本館は明治37年に完成したもので,煉瓦造石造混合構造2階建で京都府指定有形文化財(建造物)指定第1号になっています。創建時の姿をとどめる庁舎としては日本で最古のものです。平成11年(1999),創建以来はじめての全面的な屋根改修工事が完成し,創建当時の姿に保存・復元されました。
■魚市場「上の店(かみのたな)」
椹木町通の堀川と大宮の間は,天正年間の聚楽第の完成と共に,京都最大の市場として栄えたところでしたが,寛永5年(1628)の大火で堀川から西洞院に移され,東魚屋町中心の「上の店」として栄えました。昭和初めまでは,下京の魚の棚,中京の錦の店と共に3店魚問屋として,市民の台所の役割を果たしていました。

外灯の点灯式典

御大典時の奉祝袴

当時の集金袋

上の店のちょうちん

火事羽織
■平安女学院
歴史と伝統をもつキリスト教の平安女学院。常に「女性の自立」をめざした新しい時代の女子教育を追求する学校だけあって,昔からオシャレな制服姿に憧れる女性たちは多かったですね。時代は変わっても,いつも明るく元気な女子生徒たちの姿がこの学区にあるのは実にいいものです。今も,煉瓦造りの教会などの建物がその歴史を語っています。
明治8年(1875),大阪川口の居留地に米国聖公会は,「エディの学校」と呼ばれる女子のためのミッションスクールを設立。これが平安女学院の前身です。その後,校舎の老朽化や教師である宣教師たちの伝道の地が京都に移ったこともあり,明治28年「平安女学院」として現在地に移転して来ました。その後,学校制度の改正を重ね,戦後の新学校教育法に基づき,昭和22年(1947)に平安女学院中学校,翌年には高等学校ができました。昭和25年には短期大学が設置され,昭和63年の短大移転まで多くの女子学生が学びました。

開校時の校舎(明治25年)

聖アグネス教会聖堂
関連コンテンツ
学区案内トップページ
- 学区案内/成逸学区(せいいつ) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月発行)から抜粋
- 学区案内/室町学区(むろまち) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/乾隆学区(けんりゅう) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/西陣学区(にしじん) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/翔鸞学区(しょうらん) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/嘉楽学区(からく) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/桃薗学区(とうえん) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/小川学区(おがわ) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/京極学区(きょうごく) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/仁和学区(にんな) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/正親学区(せいしん) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/聚楽学区(じゅらく) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/中立学区(ちゅうりつ) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/出水学区(でみず) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/待賢学区(たいけん) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/滋野学区(しげの) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- 学区案内/春日学区(かすが) ※上京区120周年記念誌(平成12年3月31日発行)から抜粋
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/成逸学区(せいいつ)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/室町学区(むろまち)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/乾隆学区(けんりゅう)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/西陣学区(にしじん)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/翔鸞学区(しょうらん)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/嘉楽学区(からく)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/桃薗学区(とうえん)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/小川学区(おがわ)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/京極学区(きょうごく)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/仁和学区(にんな)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/正親学区(せいしん)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/聚楽学区(じゅらく)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/中立学区(ちゅうりつ)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/出水学区(でみず)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/待賢学区(たいけん)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/滋野学区(しげの)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/春日学区(かすが)
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/特集1 学区の高齢者サービス
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/特集2 上京の学区今昔
- ふれあいいっぱいかみぎょうのがっく/特集3 まとめ
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/文化人ゆかりの地
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/赤穂浪士ゆかりの地
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/暮らしを支える「商店街」
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/暮らしに広がる文化(まちの老舗)
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/映画
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/今も暮らしに生きる歴史(名所旧跡)
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/まちの風景を支える近代建築
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/地域自治のシンボルとしての小学校
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/伝統文化を育み、伝統文化に育まれるまちの暮らし
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/映画 其の弐
- 我が学区の身近な歴史舞台再発見/まちの歴史と地名