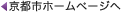第11回「京都市道徳教育振興市民会議」概要
ページ番号6504
2008年2月12日
場 所 京都市大学のまち交流センター キャンパスプラザ京都 第1会議室
出席者
【委 員】
牛尾 誠三 京都市立中学校道徳研究会会長・京都柳池中学校長
小野山正彦 京都新聞社論説委員長
皆藤 章 京都大学大学院教育学研究科助教授 【副座長】
梶 寿美子 市民公募委員
小寺 正一 京都教育大学副学長 【座長】
高田 道弘 市民公募委員
中井 隆栄 (社)京都青年会議所理事長
永田 萠 イラストレーター
中野 悦子 平成12年度京都市中学校PTA連絡協議会副会長
橋本三千代 市民公募委員
藤本奈々子 平成12年度京都市小学校PTA連絡協議会副会長
正木 隆之 人づくり21世紀委員会副幹事長
(財)京都ユースホステル協会事務局長
迫田 敏暉 京都市教育委員会教育次長
【専門員】
村田 喬子 京都市立永松記念教育センター研究課主任研究員
【教育委員会事務局】
生田義久指導部担当部長,向井宣生指導部担当部長,森田正和学校指導課長,宮本昌昭学校指導課担当課長,佐藤卓也永松記念教育センター指導主事
1 協議
(1)「提言作成」について
(2)報告「道徳教育1万人市民アンケート」について
・ 「考える以前の道徳」ですら失われることが問題となっているので,今のわれわれの社会,これからの子どもたちの社会をどうするのかを考えた場合,「考える道徳」,「考える以前の道徳」の2つの分け方ではなく,後者に焦点を当てて提言を作成すべきではないか。
・ 「考える以前の道徳」という表現はもっと考慮したい。お互いが共有できる価値観などに変えたい。
・ 文章表現はまだ固く重たく感じるが,織り込む内容として今日は考えて,表現はまだ修正することとしたい。
・ 大人が態度で示し,それを子どもが自然と学びとるものと私は考えているので,大人に対しての願いは考えられるが,子どもたちへの願いと励ましは考えにくい。
・ 会議で練り上げてきた内容は踏まえられ,伝わっているが,もうひと工夫が必要だ。特に「しなやかな道徳教育」の説明を言葉にした場合,違和感をまだ私は持つので,もっと市民にわかりやすく適切に伝わるように一工夫できるのではないか。
・ しなやかな道徳教育,共に生きるための道徳教育という言葉は,今回のキャッチフレーズになることを踏まえ,もっと考えるべきではないか。
・ 「共に生きるための道徳教育」では繋がりにくいが,「共に生きるための知恵」なら繋がる。今回の「ための」のようなつなぎ言葉の整理は必要なのではないか。
・ 「押し付ける道徳」ではいけないということになっているために,押し付けないということにしている。そのような「押し付けない」という方法論はどうなのだろうか。方法論ではなく,中身から判断すべきではないか。そうすると,「共に生きるための」という表現にいきついた。いろいろな紛争があるけれども,多様な価値観を認めた上で,子どもが共同体の主体者になって,世界に飛び出していくそんな願いを持ってこの表現を出している。
・ 「共に生きるための」は提言のフレーズで使うのはいいが道徳の定義ではない。道徳の持っているイメージが皆で異なる。市民みんなで道徳を共有できるように定義を考えるべきではないか。
・ 「しなやかな」の定義だが,前回の会議で同意を得た内容をもっとわかりやすく盛り込むべきではないか。
・ 道徳教育の目的としては,共に生きることの延長線にもっとあるのではないか。人々が幸せにいきるためとか京都の町をどのようによくしていけばいいかといった内容が目的である。共に生きることはそのための手段にあたるのではないか。会議に出ていない一般の方にいかに伝えるかが大切だ。
・ 私にとっての道徳教育は,生き方や命について考えることとこの会議から単純に受け止めている。
・ 「共に生きる」を定義するとき,一人一人が自立していることが私にとっては前提となっていたが,そうではない場合もあるのが今日の会議を通じ気付いた。改めて言葉の問題の難しさを感じた。
・ 今日は言葉の問題が大きい。ただし,ここで出ている基本的な考えについては,今までの議論の延長線上の話なので同意を得ているのではないか。
・ 一人一人が考える道徳も必要だということは押さえるべきだ。
・ 子どもたちへの願いの文章がまだ固く,重い。
・ 構成についてだが,大人の襟を正して子どもに提言するという観点から,家庭・地域に対する大人への意見を先におき,子どもへの意見を後にすることで整理がつくのではないか。
・ 子育てをしているお母さんは,みんな自分は正しいと思っている。他人が見ると間違いだと思われる場合もある。だから,いろいろな価値観をもった親たちが振りかえることができ,学べる資料にまとまっていくといいのではないか。
・ 多くの人が子どもに思いやりとやさしさを求めているが,大人にも求めるべきではないか。
・ 障害者の立場から言えば,皆さんに犠牲を強いて生きていかなければならない。我慢する気持ちをもってもらわないと生きていけない。
・ 障害者の人にもお互いが配慮して生きていかなければならない。
・ アンケートで大人社会のあり方そのものを問う意見が多かったので,大人社会に向けた提言も行うべきだ。
・ 最後は,委員一同より会議の名で出すほうがいいのではないか。
・ 前段の説明は大変いいが,少し長いのではないか。
・ 目の見えない人のために,この報告書の存在を機関紙で周知していただきたい。
2 その他今後の活動内容等
・ 次回会議については,2月4日(火)午後に実施されることとなった。
・ いろいろな団体からの申入れについて,従来から各委員の手元に文書を渡すことはしてきたが,個別的・直接的には対応しないこととさせていただいた。会議が,自由な論議をすることを第一に考えてきたからである。今後もこのような申入れに対して,同様に対応する。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部学校指導課
電話:075-222-3815
ファックス:075-231-3117