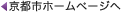第2回「京都市道徳教育振興市民会議」概要
ページ番号6450
2008年2月12日
日 時 平成13年10月9日(火) 14:00~16:00
場 所 京都市大学のまち交流センター キャンパスプラザ京都 第1会議室
出席者
【委 員】
牛尾 誠三 京都市立中学校道徳研究会会長・滋野中学校長
小鴨 梨辺華 能楽金剛流師範
(リベッカ・ティール)
皆藤 章 京都大学大学院教育学研究科助教授
梶 寿美子 市民公募委員
河合 隼雄 京都市教育委員会専門委員・京都大学名誉教授
小寺 正一 京都教育大学副学長
高田 道弘 市民公募委員
中井 隆栄 京都青年会議所副理事長
永田 萠 イラストレーター
橋本三千代 市民公募委員
藤本奈々子 平成12年度京都市小学校PTA連絡協議会副会長
正木 隆之 人づくり21世紀委員会副幹事長
(財)京都ユースホステル協会事務局長
迫田 敏暉 京都市教育委員会教育次長
【専門員】
柴原 弘志 文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官
国立教育政策研究所 道徳・倫理担当調査官
村田 喬子 京都市立永松記念教育センター研究課主任研究員
【教育委員会事務局】
谷口賢司教育企画監,生田義久指導部担当部長,向井宣生学校指導課長
1 報告
柴原専門員から「我が国における道徳教育施策の現状」についての報告が行われた。
2 意見交換
柴原専門員の報告,市民等への「アンケート」や学校視察等について意見交換が行われた。
(1)アンケートについて
○ 今後の活動についてだが,社会的に考えが多様であるが,人々が世の中で共有すべきことを提案していくことも必要である。そうするのに,アンケートを取ることが重要である。
内容については,今の社会を支えている人の意見も,若い世代の人達の意見も聞きたいので,予算の限りはあるが幅広い意見を吸い上げたい。子ども逹に任せるという風潮もあったが,これぐらいがベースだということを提案することも大切である。特に若い人達の意識にウエイトを置いてアンケートを取りたい。
○ 今回のような文字で問う形式もいいが,自分達の言葉で話す形式の方が本当の気持ちが明らかになりやすい。言葉の持つ力をもっと信じていくことも大切である。素直な部分を非常に出しやすいから,子ども逹が自由に話す機会を増やすべきである。
○ これが道徳教育というものを定義するのが難しいので,道徳教育とは一体何なのかということを聞きたい。市民が何を道徳教育と考えているのか把握できることを期待したい。
○ 設問が難しい。○×方式では,答えが淡泊になる。
○ 質問の中に「親の世代」の躾をいれたい。学校の教師をしていると,この子の親はどんな躾をしているのかと思う時がある。子どもが髪を染めていることを注意しようとすると,親が髪を染めている。何も言えないのが現状だ。私が小さい時などは,親が子を怒ることでうまくいっていた。親から,「敷居は親の頭であり,踏むものではない。またぐものだ」と教えられてきて,いつも怖々またいでいたものだ。
内容的には,今の家庭で躾がいったいどういう場面でどういうことを意図してどのようにされてるのかを聞きたい。躾がされていないならば,それはそれで考えねばならないし。そういうことを入れてみてはどうだろうか。
○ 質問の形そのものが大変に難しい。インパクトが弱くなる恐れもある。作業部会の中で具体的に考えることとする。
(2)学校視察について
○ 小学校を訪問してみて,年代によって目が輝いていたり,疲れていたりといろいろな表情があるので,一通り学年を見たい。
○ どんなことを話し合っているのかを知りたいので,子どもたちが話し合っているところを見たい。
○ 保護者とも話をしてみたい。
○ 古い校舎で子供の少ない学校の様子を見てみたい。
○ 地元の小学校はいつも見てるので,違うところを見たい。○ 授業以外のところで子どもたちがどうしてるのかを見たいので,小学校の朝礼やホームルームなども見てみたい。
○ 皆で行くと授業の妨げになるので,幾つかのパターンを用意してグループを分けて行ってみることにしたい。
○ 子どもの本音を上手に聞いていただける学校の授業に行きたい。京都市でも進められている保護者が自由に意見を言える保護者参画型の授業も面白いのではないか。
○ 委員自らが授業をしてみても面白い。
○ 遠足の時に行くのも面白い。
(3)柴原専門員の報告について
○ 先程の報告の中で若い人達が格言が好きだとあったが,何かによりかかりたいという気持ちもあるからだ。
○ 子ども達は変わらないという話もあったが,環境次第で若い人達は変わるという現実もあるので「崩れやすさ」を押さえることも重要である。
○ 今の子ども達は長い時間の努力をするのを嫌ってすぐ答えを求める傾向があるのに,「為せば成る」が「好きな言葉は何か」のアンケートの中で,一番であることに驚いた。
○ 先程の報告の中で,価値観が多様化するのはいいのだけれど,自分達の大事な「もととなるもの」が備わってることが大事だという話があった。その「もととなるもの」を我々がどうやって見極められるかを教えてほしい。
○ 質問は何が正しくて何が正しくないかを見極めることについてお聞きになられていると思うが,正しいか正しくないかは関係なく,そういうことを考える機会を作るべきである。
○ 体験活動をどうやって子ども逹にしみこませていくか聞きたい。体験というと,生きるということになるが,非常に素朴に営んでいる日常の経験,例えば家庭や地域との交流を生かした生き方や体験活動が大事なのは分かる。ただ一方で,メディアの発達に伴って,自分の身の回りには起こっていない現実を超えたものを見ることができる。子ども逹にはこういった経験が簡単に手に入るのに大人逹がどう考えているのかが分からない。そういった体験を我々大人がどうやって子どもにしみこませていくのかということを考えていかなければならない時代ではないか。
○ それを考える場が必要である。実感を持った生活の体験とバーチャルな世界の体験がある。それらを結び付けるには,マスコミ等,子ども逹の体験を崩しかねないものに対してどう子ども逹に教えればいいかを,我々大人や文部科学省として考えていくべきである。
○ 「為せば成る」の件だが,子ども逹の「頑張ってなきゃいけない」という気持ちが現れているのではないか。自分の中学生の子どもが,クラブが終わって塾に行き,大変な日々を過ごしているのを見ているので,自分には子ども逹が頑張っていて,いろいろな体験をしている姿しか見えない。
○ 子どもたちは,日常確かに体験をしているのに,体験として子ども逹が理解していないことが多い。それをどのようにして子ども逹に体験として確認させていくのか。その方策を考えることは大切である。
(4)道徳教育全般
○ 子どもたちへのアンケートの中で他の人達がどう感じているかをもっと知りたいという意見も多かった。子どもは,大人が黙っていれば大人が何を考えているのか分からない。押しつけるのではないのだけれども,意見を述べていくことが必要である。
○ あるテレビ番組を見ていた時に,日本の家庭の夕食風景がでてきた。テレビの中の母親は,子どもが,食事をするのに集中してて静かな時間の間に洗濯をしていた。子どもと会話をするより家事を優先することが増えると感じた。私は子どもと一緒に食事を取り,コミュニケーションを取ることで,子ども逹が今何に困っているかといった話を聞いたり,自分も子どもの気持ちを判断するなど大事な時間としてきた。このような家庭の基盤となるコミュニケーションの中からモラルが作られるのではないか。
○ 先生と生徒といった縦の繋がりはあるのだが,友達同士の横のつながりが弱い。グループ活動の中での体験活動による喜びや成就感などを感じさせる場が重要ではないか。
○ 毎日どこかで価値観の違いで戦争が起こっている。国や民族,宗教の違いを,お互いがどのように尊重し合うかが大事である。
話は違うが,文部科学省が古典の教育に近年力を入れ出しているが,自分の国の文化について自信を持って教えられる先生がいるのかを考えることが必要である。
○ 韓国に旅行をして,電車に乗ると,若者は立っているが,日本では逆である。こうなるのも大人社会の裏返しである。
ただし,韓国では儒教精神がきちっとしているので大人を敬っているが,一方で,目上の教員による生徒への体罰となって現れる問題がある。
○ 事業の関係で中学校しか回っていないから全てのことは分からないが,全員が悪いわけではなく,問題があるのはごく一部の生徒ではないか。この一部の子どもに対して先生がどのように教えていくかが重要である。
5「生き方探究・チャレンジ体験」推進事業等職場体験事業について
○ 職場体験事業において,「教師もともにやってみては」という提案もある。おそらく,教師の採用の時にボランティア経験があるかないかも重要な要素となってくる。
○ 我々は企業側から生き方探究チャレンジ体験推進事業を支援しているが,子どもたちにどこまで教えたらいいのかに悩んでいる。
○ 私の子どもも企業体験をしてきた。わざわざ体験を設定しなければ体験もできないのか,もっと普通の生活の中で体験できないのか。
○ 体験の話がでてきたので,京都市で取り組んでいる生き方探究チャレンジ体験事業も中学校で今年,54校が取り組むにいたっている。
・ アンケートの予備調査については,今日の論議をもとに作業部会の中で作成されることになった。
次回日程については,12月13日木の午前中に実施されることとなった。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部学校指導課
電話:075-222-3815
ファックス:075-231-3117