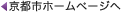第9回「京都市道徳教育振興市民会議」概要
ページ番号6496
2008年2月12日
日 時 平成14年11月8日(金) 10:00 ~ 12:00
場 所 京都市大学のまち交流センター キャンパスプラザ京都 第1会議室
出席者
【委 員】
牛尾 誠三 京都市立中学校道徳研究会会長・京都柳池中学校長
皆藤 章 京都大学大学院教育学研究科助教授 【副座長】
梶 寿美子 市民公募委員
小寺 正一 京都教育大学副学長 【座長】
高田 道弘 市民公募委員
中野 悦子 平成12年度京都市中学校PTA連絡協議会副会長
橋本三千代 市民公募委員
藤本奈々子 平成12年度京都市小学校PTA連絡協議会副会長
正木 隆之 人づくり21世紀委員会副幹事長
(財)京都ユースホステル協会事務局長
迫田 敏暉 京都市教育委員会教育次長
【専門員】
村田 喬子 京都市立永松記念教育センター研究課主任研究員
【教育委員会事務局】
生田義久指導部担当部長,向井宣生指導部担当部長,森田正和学校指導課長,宮本昌昭学校指導課担当課長,佐藤卓也永松記念教育センター指導主事
1 報告「道徳教育1万人市民アンケート」について
・ このタイトル名から論議する必要がある。
・ 30代から40代の人の回答が多かった。児童・生徒は小中学生がほとんどだ。「必ず」,「絶対に」と答えた人の中には,あまり考えずに,「ともに考えていくこと」,「ともに考えていく価値観」の意味も含まれている場合もある。
・ 「まったくそうしなくてもいい」にあまり回答が見られない。
・ 「小中学生が髪の毛を染めること」では,答がばらついている傾向がある。
・ 「わからない」と回答した人のポイントを注意深く見る必要がある。
・ 「日常の親子の会話」や「家族と過ごす時間」について,意識も行動も,親と子の間で違いが見られる。親と子の会話とは何なのかを考えていきたい。
・ 「感謝の言葉を言うこと」,「自然と触れ合う体験の大切さ」,「子育てに関する父親の役割の必要性」,「あいさつの習慣を身に付けさせること」は,結果から共有できる考え方と見ていいのではないか。
・ 大人は,女性の意見が多いことを押えておくべきだ。
・ この結果の背景に何があるかも考えねばならない。例えば,「学校や社会のルールを守ることについて」や「混雑している電車やバスの中で携帯電話をつかうことについて」といった年代層で階段状になっていることの時代背景をつかみたい。このような年代のギャップが何故生まれるのかを考えたい。
・ 年代層の時代背景を考える。人の関わりが希薄になっていることも結果にあらわれているのではないか。
・ 70代以上の人は少ないので,テクニカルに判断すべき。
・ 年代層が変わっていくごとの差に着目すべきではないか。男女別の比較や年齢層でのターゲットの違いについても考慮すべきだ。
・ 子どもと親のギャップもあるが,それを育てた母親の層の違いも考えるべきだ。
・ 父親の子育てに関する意識は注目すべきだ。
・ 子どもの性別の違いからも検討すべきだ。
・ 「歩きながらものを食べる」では,女性が多くなっているのは興味深い。
・ ものが豊かな時代にならないと,「歩きながらものを食べる」ということはしない。そういう時代になったことを表しているのではないか。
・ アンケート結果は,できるだけ幅広い視点が必要だ。もちろん提言作成に向けて,アンケートからも活用するが,当初の議論どおり,会議の論議を中心として考えていくべきだ。
2 提言作成に向けて
・学校に関わっていくことは,PTAの役でもしない限り多くはない。やっと,学校の仕組みを理解する頃には,役を降りているので,保護者の意見を学校に伝えるのはなかなか難しい。
・学校評議員をして感じるが,先生が忙しすぎて,親に関わる時間が取れないのを実感として持っている。これを解消しないと学校と保護者との関係はできないのではないか。
・ 道徳教育の教員研修を充実して欲しい。教員もまだ理解しきれていない。いろいろな考え方もあるので,道徳教育もいろいろな正解を見つけられる方法も必要ではないか。
・ 学校内のいろいろな役割がある組織を保護者に理解してもらっていないため,学校が保護者から見ると要望にすぐ応対できる体制となっていないと見られる側面はある。そのため,親から見ると対応が遅く,不満を持たれることはあるが,時間をかけてでも解決して,納得してもらうことが大切だ。
・ 道徳教育について,教員には学校でする必要があると共通理解されていると認識している。ただ個々の教員で考えていることも異なり,きちっとした道徳教育を経験していない教員世代もいるので,道徳教育の研修は推進していかなければならない。
・ 小中高校で,学校評議員等をして学校を見てきたが,学校でできるだけ初期の段階で子どもに教えていかなければならないのではないか。特に人の話を聞けるように持っていくことが大事だ。それが,生き方のベースとなり,他の教育にも繋がる事となる。
・「共生」という意味での広がりを期待する。
・ 幼稚園に子どもが通っている頃は,保護者と先生はコミュニケーションが取れているのに,小学校に上がると,個人懇談会以外に先生とコミュニケーションが取れず壁を感じた。
・ 道徳の授業はタイミングが大切だ。ある児童が,児童同志のいざこざで,頭を打ったことがあった。そのため,先生は授業予定を変更して道徳の授業を行った。体験とともに授業を行ったことで,子どもはよく理解でき,家庭でも話題になった。
・ 提言のキーワードはいいと思うが,共に生きることが必要だということに合理的な理由があることをもっと説明すべきだ。10年後の将来にとって大切だということを打ち出していくべきだ。
・ 「道徳」という名称も考えるべきという調査結果も出ている。まだ,「道徳」という言葉自体にアレルギーがあると思うし,そのことも踏まえて提言していく必要がある。
・ 本当は別の立場が担うべきだろうが,地域社会が崩壊している現在では,学校は子ども同志が体験から学べる唯一の場であると私は考えているので,期待している。・ 子育ては,学校だけが責任を負えるものではなくなっており,家庭や地域にウエイトを置いた提言であるべきだ。
・ 提言のスタンスとしては,身近な生活の中で皆が疑問に思っているけれども,改めるように行動できていないことを直すために,背中を後押しする冊子であってほしい。例えば,小さな子どもが電車に乗ってきた際に,子どもは吊り革に手が届かないので席を譲るべきか,一方でそれが癖になるのがだめなので譲るべきではないという意見があるように,いろいろな考え方があり,そのあり方を市民皆で考えるきっかけとなる冊子にすべきではないか。
・ 学校だけが学びの場でないのに,週5日制になっても,子どもは家で寝転がっているだけで地域になかなか出て行かない調査結果がある。それが何故かを考えていくべきだ。
・ もちろん家庭や地域の重要性はあるが,なかなか担え切れない実態がある。そのためにも学校が家庭や地域の役割も視野に入れた発信基地であってほしいという期待を持っている。
3 その他今後の活動内容等
次回会議については,12月6日(金)午前に実施されることとなった。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部学校指導課
電話:075-222-3815
ファックス:075-231-3117