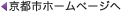「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第4編成)
ページ番号316552
2024年1月30日
車両への設置箇所(2100号車、2800号車)
先頭車両の多目的スペース「おもいやりエリア」に設ける立ち掛けシートの構造を工夫し、伝統産業の素材を飾り付けるガラス張りのスペースを設けました。新型車両全9編成の両先頭車にそれぞれ異なる素材を飾り付けます。(1編成当たり計16個)
京鹿の子絞(2134号車)

素材・技法
「京鹿の子絞」(きょうかのこしぼり)は、京都で生産される絞り製品の総称で千数百年の長い伝統を受け継いでいます。その代表的なものに「疋田絞」(ひったしぼり)があり、一般的に「鹿の子絞」と言われています。絞り染めは友禅と異なり、糸で布地を強く括(くく)り、締めることにより染色されない部分で模様を表現し、また括りによって布地にしわや括り粒で立体感をもたせる独特の技法で、染色は浸染(しんせん)の方法で行います。「おもいやりエリア」には、本疋田絞(ほんびったしぼり)の主な工程を実物の京鹿の子絞を用いて紹介します。ほかにも約50種類以上ある絞り技法のうち「針疋田絞」(はりびったしぼり)・帽子絞(ぼうししぼり)・唄絞(ばいしぼり)・辻が花の技法で製作された実物の京鹿の子絞を紹介します。


京鹿の子絞の製作風景(動画)
- 京鹿の子絞の製作風景(動画)

京鹿の子絞の製作風景を動画で紹介します。
御協力いただいた方々(敬称略)
電話:075-255-0469
京表具(2834号車)

素材・技法
京表具は、京都府内で作られている表具で、京都の長い歴史の中で熟成してきた上品な趣が特徴です。代表的な掛軸(かけじく)のほかにも額装(がくそう)・屏風(びょうぶ)・巻物(まきもの)・襖(ふすま)・衝立(ついたて)などがあり、日本建築とも密接な関係にあります。その技法は、中国から仏教の伝来とともに我が国に伝えられ、なかでも掛軸はそれぞれの時代の文化とともに磨かれ、室町時代にその高度な技法が完成しました。「おもいやりエリア」には、襖・屏風の完成に至るまでの工程及び構造の実物を紹介します。


京表具の製作風景(動画)
- 京表具の製作風景(動画)

京表具の製作風景を動画で紹介します。
御協力いただいた方々(敬称略)
関連コンテンツ
地下鉄烏丸線新型車両20系に活用している伝統産業素材・技法の紹介
- 「京都市交通局章」に「鎚起(ついき)(金属工芸)」を活用
- 「標記銘板(事業者・号車)」に「京象嵌(きょうぞうがん)」を活用
- 車内の壁に「釘隠し(くぎかくし)」を活用
- 「北山丸太」製の吊手の鞘(さや)に「京くみひも」を活用
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第1編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第2編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第3編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第4編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第5編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第6編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第7編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第8編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第9編成)
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269