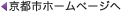「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(京友禅の染型)
ページ番号333290
2025年3月7日
車両への設置(2831号車)
2831号車の「おもいやりエリア」には、京友禅が展示中です。今回、新たな展示の追加として乗務員カーテン(客室側)と客室と運転室の仕切り壁に京友禅で使用される多くの染型の中から厳選した6種類の染型の図柄を御覧いただけます。
技法
「京友禅」には手描友禅と型友禅があり、型友禅に使う型紙は染型と呼ばれ、職人の手作業により丁寧に彫られます。京友禅協同組合連合会では、所蔵する同じ模様が繰り返し並んだ小紋柄(こもんがら)の染型をスキャニングし、そのデジタルデータ化した様々な図柄の新たな活用方法を検討していました。
この度、京友禅協同組合連合会からデジタルデータ化した図柄の新たな活用方法について、交通局に相談があり、新型車両の第1編成の「京友禅」を展示している車両(2831号車)の乗務員カーテン(客室側)に染型の図柄を活用し、新たに染型の図柄のポスターを設置することになりました。

図柄の説明
紗綾形に割菱(さやがたにわりびし)
紗綾形(さやがた)は、不断長久(家の繁栄や長寿が続くこと)を意味する吉祥文様(縁起の良い模様)で、梵字(ぼんじ)の卍(まんじ)を変形して連続させた形からできています。この紗綾形の中に割菱(わりびし)紋が付け加えられています。菱文様とは、古くは縄文土器にもあり、自然発生的に生み出された単純な形ですが、そのルーツは水草のヒシの葉や実の形ともいわれています。ヒシという植物は繁茂(はんも)しやすいことから子孫繁栄や無病息災の意味が込められています。
紗綾形と菱形が重なることで最強の吉祥文様になっています。

茶屋辻(ちゃやつじ)
茶屋辻とは、江戸時代に生まれた風景文様のひとつです。多くは、水辺の風景が描かれていて橋や家屋、樹木、草花などがモチーフとなっています。茶屋辻文様の特徴としての鳥瞰図(ちょうかんず)的な模様構成になっています。
※鳥瞰図とは、空を飛ぶ鳥の目線で地上を見下ろしたように描いた図柄です。

鯛づくし
鯛文様は古くから、めでたいという語呂合わせで、結婚式やお食い初めなどの祝事によく用いられており、日本人になじみ深い縁起魚の吉祥文様です。

地紙(じがみ)に菊づくし
地紙(じがみ)とは、扇や傘などに貼る紙のことです。その中に草花や文様が描かれ、優雅な染織品などに使われていることが良くあります。
菊は秋を代表する植物として多くの種類の文様が作られ、鎌倉時代から菊文様の意匠化が進み、日本的意匠の代表の秋草として扱われるようになりました。

楓(かえで)づくし
楓文様は、平安時代より貴族の間で衣服などに愛用されており、「枕草子」などにもその様子が描かれています。楓は長寿を表した吉祥紋で、季節により色を変え、美しい色で人を喜ばせてくれることから「世渡りがうまく幸せになれる」という意味もあるようです。

蝶づくし
蝶文様は、平安中期以降に用いられるようになり、蝶は卵から脱皮を重ねて蛹(さなぎ)になり、そして美しい蝶になることから「不死不滅」の象徴として武士の紋章にも用いられました。現在では、華やかな女性らしい印象が強い蝶文様は、多くの女性のきもののモチーフとして用いられています。

御協力いただいた方々(敬称略)
車両に展示している「染型文様カーテン」と「染型文様ポスター」は、京都染型協同組合からの寄贈です。
関連コンテンツ
地下鉄烏丸線新型車両20系に活用している伝統産業素材・技法の紹介
- 「京都市交通局章」に「鎚起(ついき)(金属工芸)」を活用
- 「標記銘板(事業者・号車)」に「京象嵌(きょうぞうがん)」を活用
- 車内の壁に「釘隠し(くぎかくし)」を活用
- 「北山丸太」製の吊手の鞘(さや)に「京くみひも」を活用
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第1編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(京友禅の染型)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第2編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第3編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第4編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第5編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第6編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第7編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第8編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第9編成)
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269