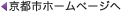「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第5編成)
ページ番号322017
2023年9月27日
車両への設置箇所(2100号車、2800号車)
先頭車両の多目的スペース「おもいやりエリア」に設ける立ち掛けシートの構造を工夫し、伝統産業の素材を飾り付けるガラス張りのスペースを設けました。新型車両全9編成の両先頭車にそれぞれ異なる素材を飾り付けます。(1編成当たり計16個)
京銘竹・京竹工芸(2135号車)
素材・技法
京銘竹とは、京都で生産された良質の竹を京都ならではの技法で加工した白竹(しらたけ)、図面角竹(ずめんかくちく)、亀甲竹(きっこうちく)、胡麻竹(ごまだけ)の4種類を言います。京都産の竹を素材に伝統技法を用いて作られた小物が京竹工芸品です。「おもいやりエリア」には、京銘竹を一部使用した垣根、戸及び京竹工芸の代表的な編み目の実物を紹介します。


御協力いただいた方々(敬称略)
京都府竹産業振興連合会
電話:075-861-1712
電話:075-441-3981
京都竹材商組合
電話:075-925-5826
京都竹工芸品協同組合
電話:075-561-3624
京七宝(2835号車)
素材・技法
七宝(しっぽう)は、銀・銅の金属の上にガラス質の釉薬(ゆうやく)をのせて、高温で焼き付ける金属工芸です。京都で作られている七宝は、安土桃山時代に京の公家文化の中で生活を彩る産業として華開き、宮殿の釘隠し、襖(ふすま)の引き手等のさまざまな作品が作られました。明治時代には釉薬が改良され、現在は工芸品や額、アクセサリー等が作られています。「おもいやりエリア」には、装・食・和・飾・住・楽・誂(あつらえ)の各テーマに沿った実物作品を紹介します。


御協力いただいた方々(敬称略)
電話:075-634-3679
関連コンテンツ
地下鉄烏丸線新型車両20系に活用している伝統産業素材・技法の紹介
- 「京都市交通局章」に「鎚起(ついき)(金属工芸)」を活用
- 「標記銘板(事業者・号車)」に「京象嵌(きょうぞうがん)」を活用
- 車内の壁に「釘隠し(くぎかくし)」を活用
- 「北山丸太」製の吊手の鞘(さや)に「京くみひも」を活用
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第1編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第2編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第3編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第4編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第5編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第6編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第7編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第8編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第9編成)
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269