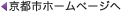車内の壁に「釘隠し(くぎかくし)」を活用
ページ番号299750
2025年8月27日
車内への設置箇所(2200号車、2300号車、2600号車、2700号車)
中間車両の車内の連結部通路の壁(1編成当たり計8個)

車両への設置箇所
素材・技法
寺院などの伝統的な建築の装飾に用いられる「釘隠し」を金属工芸の鏨(たがね)による、打ち出しや彫り技法により製作し、車内装備品のネジ隠しとして活用します。材質は銅とし、編成毎にテーマを定めて、車両毎に異なる4種類のデザインで製作します。
| 第1編成 | 京の花と京の木 |
| 第2編成 | 京の催し |
| 第3編成 | 京の方位(四神) |
| 第4編成 | 京生まれ (京都発祥で日本初のもの) |
| 第5編成 | 地下鉄でお出かけ (地下鉄沿線の京都市関係施設) |
| 第6編成 | 京の生き物 |
| 第7編成 | 古都京都の文化財の行事 |
| 第8編成 | 交通局車両の移り変わりと京の玄関口の発展 |
| 第9編成 | 京の風物詩 |
☆New☆ 第9編成
9編成目のデザインは、「京の風物詩」をテーマとしました。春の京の風物詩である「蹴上インクラインの桜」、夏の京の風物詩である「鴨川の納涼床」、秋の京の風物詩である「東福寺の紅葉狩り」、冬の京の風物詩である「三十三間堂の通し矢」をモチーフとしました。

第1編成
1編成目のデザインについては「京の花」と「京の木」をテーマに季節ごとに「サトザクラ(春)」、「シダレヤナギ(夏)」、「タカオカエデ(秋)」、「ツバキ(冬)」を選定しました。

第2編成
2編成目のデザインについては「京の催し」をテーマとして「舞踊(ぶよう)」(春)、「祇園祭」(夏)、「月見」(秋)、「まねき上げ」(冬)をモチーフとしました。

第3編成
3編成目のデザインは「京の方位(四神)」をテーマにしました。四神(ししん・しじん)とは中国の神話で天の四方の方角を司る聖獣であり、東の青龍(せいりゅう)、西の白虎(びゃっこ)、南の朱雀(すざく)、北の玄武(げんぶ)を指します。平安京は四神が守護する「四神相応の地」として造られたとされています。四神相応とは風水において好適地とされる地勢や地相のことで、古来よりこの条件を満たす土地に住むと長く繁栄すると考えられてきました。

第4編成
4編成目のデザインについては「京生まれ」(京都発祥で日本初のもの)をテーマとしました。明治24年に運転開始した日本初の事業用水力発電所である「蹴上発電所」(けあげはつでんしょ)、昭和2年に日本で最初の中央卸売市場として開業された「中央卸売市場」(ちゅうおうおろしうりしじょう)、明治30年に稲畑勝太郎がフランスから映画装置を持ち帰り日本で初めて映画の試写実験に成功した「映画上映」、大正6年に京都から東京までの514km(23区間)を3昼夜にわたり走り続けた日本で最初の駅伝競走である「駅伝」をモチーフとしました。

第5編成
5編成目のデザインは「地下鉄でお出かけ」(地下鉄沿線の京都市関係施設)をテーマとしました。平安建都1200年を記念して建造された「京都コンサートホール」(烏丸線北山駅)、大政奉還の意思が表明された国宝「二条城二の丸御殿」(東西線二条城前駅)、1903年に日本で2番目に開園した「京都市動物園」(東西線蹴上駅)、日本に現存する最も古い公立美術館である「京都市京セラ美術館」(東西線東山駅)をモチーフとしました。

第6編成
6編成目のデザインは「京の生き物」をテーマとしました。春の生き物として清滝川の渓流で見られる天然記念物のオオサンショウウオ、夏の生き物として鴨川で縄張りを争う2匹の鮎、秋の生き物として鈴虫寺で趣ある音色を奏でる鈴虫、冬の生き物として鴨川デルタで羽を休めるユリカモメをモチーフとしました。

第7編成
7編成目のデザインは世界遺産「古都京都の文化財」の行事をテーマとしました。春の行事は「醍醐寺の五大力さん」、夏の行事は「下鴨神社の御手洗祭」、秋の行事は「上賀茂神社の烏相撲」、冬の行事は「西本願寺の御煤払」をモチーフとしたデザインとしました。

第8編成
8編成目のデザインは、「交通局車両の移り変わりと京の玄関口の発展」をテーマとしました。明治45年頃の市電と初代京都駅舎として「市電(Ⅰ型)と京の玄関口」、昭和24年頃の市電と2代目京都駅舎として「市電(1000型)と京の玄関口」、昭和56年頃に市電に変わり開業した地下鉄と3代目京都駅舎として「地下鉄(10系)と京の玄関口」、令和7年頃の伝統産業を取り入れた京都ならではの地下鉄と4代目京都駅舎として「地下鉄(20系)と京の玄関口」をモチーフとしました。

釘隠しの製作風景(動画)
- 釘隠しの製作風景(動画)

第1編成の釘隠しの製作風景を動画で紹介

製作風景
御協力いただいた方々
関連コンテンツ
地下鉄烏丸線新型車両20系に活用している伝統産業素材・技法の紹介
- 「京都市交通局章」に「鎚起(ついき)(金属工芸)」を活用
- 「標記銘板(事業者・号車)」に「京象嵌(きょうぞうがん)」を活用
- 車内の壁に「釘隠し(くぎかくし)」を活用
- 「北山丸太」製の吊手の鞘(さや)に「京くみひも」を活用
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第1編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第2編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第3編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第4編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第5編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第6編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第7編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第8編成)
- 「おもいやりエリア」の伝統産業素材の展示(第9編成)
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269