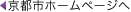伏見区の歴史 : 中世 動乱の時代/北朝ゆかりの伏見
ページ番号13315
2018年7月12日
中世 動乱の時代/北朝ゆかりの伏見
院政の拠点鳥羽殿
白河上皇のあと鳥羽上皇,後白河上皇と院政が続き政治の実権を握っていました。保元元年(1156)鳥羽上皇が崩御のあと,崇徳上皇と後白河法皇との間で皇位継承争いが起こったのが保元の乱。その後,平清盛は後白河院を鳥羽殿に幽閉し,安徳天皇を皇位につけました。中世という武家が台頭する時代の変わり目に鳥羽殿は拠点のひとつとなりました。公家回復をめざして起こした承久の乱に敗れた後鳥羽院は,城南宮の流鏑馬に乗じて兵を集めましたが敗北,隠岐へ配流となり院政は幕を閉じました。

曲水の宴・城南宮
戦乱に巻込まれた法界寺
承久の乱でもっとも被害をうけたのは日野の法界寺でした。日野は平安遷都直後に桓武天皇が遊猟し,多くの貴族たちもこの地を訪れました。また,12世紀の中頃には月の9の日に日野の西辻・今里で市が定期的に開かれており,この地は醍醐とともに奈良から近江への古北陸道に面していたことから,古くから開けたところでした。法界寺は日野に居住し,日野家の祖となった藤原資業が11世紀中頃に阿弥陀堂と薬師堂を創建したことにはじまります。その後,資業の子実綱と実政が観音堂と五大堂を建立しましたが,承久の乱でこれらの堂塔が焼失してしまいました。

法界寺
北朝ゆかりの伏見殿
荒廃した鳥羽離宮に代わってその壮麗さをたたえられたのが伏見殿(伏見山荘)でした。橘俊綱没後,伏見山荘は白河上皇に献上され,皇室の荘園にくわえられました。後白河上皇はここに壮麗な伏見殿を造営,船津御所,伏見離宮とも称されました。南北朝時代には足利尊氏が擁立した北朝の光厳上皇,光明上皇,に受け継がれ,両上皇の母,藤原寧子は伏見殿に居住し,隣接する場所に大光明寺を建立しました。伏見殿は光厳上皇が後に伏見宮家の始祖となる栄仁親王に譲られたものでした。
応仁の乱から戦国時代へ
南朝北朝が統一されると,芸能文化が盛んに行われるようになり,伏見殿に近い御香宮などでも猿楽・連歌・御茶事などが行われました。伏見宮家の貞成親王が著した『看聞御記』には村人が伏見殿に集まり,華美なつくり物や仮装をして,松拍子といわれる拍子物(踊り)を奉納したことが記されています。しかし,足利8代将軍義政の家督相続争いに端を発した応仁の乱(1467)では稲荷社の本殿などが焼失,醍醐寺も五重塔を残して全滅するなど,伏見の町も兵火にかかりました。天正元年(1573)に将軍足利義昭が織田信長に降伏し,室町幕府の崩壊を迎えました。

花傘
関連コンテンツ
伏見区の概要・歴史
- 伏見区の概要 : 伏見区の沿革・特長・文化
- 伏見区の概要 : 京都市域の中の伏見区の位置
- 伏見区の概要 : 伏見区の合併・編入の変遷経過
- 伏見区の概要 : 伏見区の地勢
- 伏見区の概要 : 伏見区シンボルマーク
- 伏見区の歴史 : 古代伏見の成り立ち
- 伏見区の歴史 : 古代神々の時代
- 伏見区の歴史 : 平安時代 貴族文化と伏見
- 伏見区の歴史 : 中世 動乱の時代/北朝ゆかりの伏見
- 伏見区の歴史 : 安土桃山時代 秀吉が開いた城下町
- 伏見区の歴史 : 江戸時代~幕末 港湾商業都市の繁栄
- 伏見区の歴史 : 近代産業への飛躍/明治・大正・昭和へ
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和6年~15年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和16年~25年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和26年~35年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和36年~45年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和46年~55年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和56年~平成2年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(平成3年~13年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(平成14年~)
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-611-1293 地域防災担当、調査担当:075-611-1295
ファックス:075-611-4716