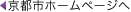伏見区の歴史 : 古代神々の時代
ページ番号13301
2019年7月18日
古代 神々の時代
稲荷創建の伝説
稲荷創建については,『山城国風土記』のなかに記されている, 伊奈利の社の社名由来説話では, 秦 伊呂具が稲梁を積んで富裕になりましたが,あるとき餅を弓矢の的にすると, 餅が白鳥と化して飛び去り,山の峰にいたって稲なり生ひ=伊禰奈利生ひしたため,遂に社の名としたことが記されています。古来,稲荷山のように円錐形をした山は神をなびき寄せる山,神奈備として信仰しました。山上に恐れの対象でもあり,恵みの雨をもたらす雷神を招き降ろし,豊かな実りを祈願しました。伏見稲荷の御祭神は先住氏族の荷田氏の祖神・宇迦之御魂大神,渡来人秦氏の祀った大宮能売大神,佐田彦大神などであり,これらの神はいずれも農耕神でした。

千本鳥居

伏見稲荷大社楼門
神々の鎮座する藤森神社
平安京遷都のはるか以前に,紀氏一族が深草山に雷神を祀っていたことにはじまり,その後,秦氏が社殿を山麓に移し真幡寸神社としました。御祭神は神功皇后で,本殿の東に残る旗塚は皇后が新羅を攻略したときの軍艦旗を納めた場所と伝えられています。また,藤森神社には早良親王,伊予親王,井上内親王など,桓武天皇やその子の平城天皇の即位に絡んで亡くなった悲運の親王を合祀しています。近くに桓武天皇陵があることや平安遷都の折りには,都を悪霊から守るため大将軍社が置かれたことからここに合祀されたと考えられています。このほか天武天皇と壬申の乱で手柄を立てた皇子の舎人親王など12柱もの神々が祀られています。

藤森神社
方除けの神社,城南宮
社伝では神功皇后が新羅を攻略する折りの旗を御神体として奉納したこと,また,平安京遷都の際,王城鎮護のため国常立尊を合祀したことなど,藤森神社と同様のことが伝えられており,真幡寸神社と大きく関わっていることがわかります。城南宮の日・月・星の神紋は神功皇后の旗印だといわれており,これと同じような神紋が日本海側の若狭湾沿岸の神社にも伝わっていることから,秦氏との関連や神紋が航海安全の旗印であったと考えられています。城南宮が京都における方除け信仰の中心となったのは院政時代のこと。最初は城南明神と呼ばれていましたが,白河法皇のはじめての行幸の折り,城南宮と名付けられました。

城南宮
霊水信仰の聖地,御香宮
御香宮は御諸神社と呼ばれ,伏見九郷の産土神でした。社伝では貞観4年(862)に境内からたいそう香りのよい水が湧出て,病人がこれを飲んだところたちまち回復したので,清和天皇から『御香水』の名を賜り,御香宮としたと伝えられています。御祭神を神功皇后としていることから,筑前香椎宮(神功皇后霊廟)から勧請し,御諸の御と香をとり御香宮と呼ぶようになったとする説もあります。御香宮は豊臣秀吉の伏見城築城の際,城の鬼門の守護神として現在の敦賀町に移転,徳川家康により,再び旧社地に戻されました。『伏見九郷之図』では本殿裏に白菊石が描かれており,金札宮に伝わる白菊の翁の伝説と密接なつながりがあったと考えられています。

御香宮

御香水
関連コンテンツ
伏見区の概要・歴史
- 伏見区の概要 : 伏見区の沿革・特長・文化
- 伏見区の概要 : 京都市域の中の伏見区の位置
- 伏見区の概要 : 伏見区の合併・編入の変遷経過
- 伏見区の概要 : 伏見区の地勢
- 伏見区の概要 : 伏見区シンボルマーク
- 伏見区の歴史 : 古代伏見の成り立ち
- 伏見区の歴史 : 古代神々の時代
- 伏見区の歴史 : 平安時代 貴族文化と伏見
- 伏見区の歴史 : 中世 動乱の時代/北朝ゆかりの伏見
- 伏見区の歴史 : 安土桃山時代 秀吉が開いた城下町
- 伏見区の歴史 : 江戸時代~幕末 港湾商業都市の繁栄
- 伏見区の歴史 : 近代産業への飛躍/明治・大正・昭和へ
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和6年~15年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和16年~25年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和26年~35年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和36年~45年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和46年~55年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(昭和56年~平成2年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(平成3年~13年)
- 伏見区の歴史 : 年表/伏見区の歩み(平成14年~)
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-611-1293 地域防災担当、調査担当:075-611-1295
ファックス:075-611-4716