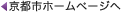汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱
ページ番号81894
2023年4月1日
汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、京都市公共下水道事業条例第17条第4項及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例第21条第4項に規定する使用水量と異なる汚水排出量の認定(以下「減量認定」という。)に関し必要な取扱事項を定めることにより、統一的かつ適正な事務の執行を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、京都市公共下水道事業条例及び京都市特定環境保全公共下水道事業条例において使用する用語の例による。
(減量認定の要件)
第3条 管理者は、事業活動における水道汚水又は井戸汚水等の使用水量のうち、次の各号のいずれかに該当するものの使用水量(以下「対象水量」という。)について、減量認定を行うことができる。
⑴ 製品製造工程の蒸発水又は製品の含有水若しくは混入水
⑵ ボイラーの蒸発水
⑶ 冷却装置の蒸発水
⑷ コンクリート打設の含有水
⑸ その他特に管理者が認めたもの
2 減量認定は、対象水量が、公共下水道に排除されないこととなる目的に使用したものであることが確認でき、かつ、当該水量を計測装置により測定できる場合に行うものとする。ただし、対象水量を測定することが困難であると管理者が認めた場合であって、当該対象水量が合理的であることを証する書類等が提出されたときは、この限りでない。
(減量認定の申請)
第4条 減量認定の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、汚水排出量減量認定申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類のうち管理者が必要と認めたものを添付して管理者に申請しなければならない。
⑴ 申請に係る施設の平面図(給排水系統図を含む)
⑵ 製品製造工程図
⑶ 製品別の蒸発水量又は含有水量等を確認できる書類
⑷ ボイラー、冷却装置等の減量関係機器の仕様書及び設置写真
⑸ ボイラー、冷却装置等の減量関係機器における蒸発水量(蒸発率)を確認できる書類
⑹ 計測装置の仕様書及び設置写真
⑺ その他管理者が必要と認めたもの
(減量認定の決定)
第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、書類審査及び実地調査により申請に係る施設の状況等を確認し、減量認定を行うこと及びその方法又は減量認定を行わないことを決定するものとする。
2 管理者は、前項の規定により減量認定を行うこと及びその方法を決定したときは、汚水排出量減量認定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者(以下「認定適用者」という。)は、対象水量の有無にかかわらず、汚水排出量の認定ごとに、事前に汚水排出量減量申告書(第3号様式)により公共下水道に排除されないこととなる目的に使用した対象水量を管理者に申告しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による申告があったときは、汚水排出量の認定ごとの使用水量を超えない範囲内で、申告された対象水量を考慮したうえで汚水排出量を認定するものとする。ただし、減量関係機器や計測装置の故障等により、対象水量が正確に計量できない場合は、使用水量の全量を公共下水道に排除したものとみなす。
5 管理者は、第1項の規定により減量認定を行わないことを決定したときは、申請者に対して、減量認定を行わない理由を記載した文書を交付するものとする。
(減量認定の適用期間)
第6条 減量認定の適用期間は、5年以内とする。
2 減量認定の適用を引き続き受けようとする者は、汚水排出量減量認定申請書(第1号様式)により管理者に申請しなければならない。
(減量認定事項の変更等)
第7条 認定適用者が、減量認定に係る事項の変更又はその取消しをしようとするときは、速やかに汚水排出量減量認定変更等届出書(第4号様式)に、管理者が必要と認めたものを添付して管理者に届け出なければならない。
(減量認定の取消)
第8条 管理者は、認定適用者が次の各号のいずれかに該当するときは、減量認定を取り消すことができる。
⑴ 偽りその他不正の手段により、減量認定を受けたとき。
⑵ 減量認定の要件に適合しなくなったとき。
⑶ その他この要綱の規定に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定により減量認定を取り消すことを決定したときは、認定適用者に対して、減量認定を取り消す理由を記載した文書を交付するものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、認定適用者に対し、減量認定に関し必要な事項について、報告若しくは資料の提出を求め、又は減量認定に係る施設の実地調査をすることがある。
(認定適用者の遵守事項)
第10条 認定適用者は、この要綱を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 設置した計測装置及び減量関係機器等を自らの責任において適切に維持管理すること。
⑵ 故障、破損その他の事故が発生した場合は、速やかにこれらを修理し、又は交換すること。
⑶ 設置した計測装置を用いて正確に対象水量を測定すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行に関し施行日前に減量認定を適用しているものについては、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱第4条第1項の規定により減量認定の適用を決定した者の汚水排出量については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この要綱による改正前の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙は、改正後の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙は、改正後の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙は、改正後の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
(準備行為)
3 減量認定の適用を引き続き受けるために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙は、改正後の汚水排出量の減量認定に関する取扱要綱に基づく様式による用紙として作成されたものとみなして、当分の間、これを使用することができる。
汚水排出量の減量認定に関する各種様式(PDF)
 汚水排出量減量認定申請書(第1号様式)(PDF形式, 68.16KB)
汚水排出量減量認定申請書(第1号様式)(PDF形式, 68.16KB) 汚水排出量減量認定通知書(第2号様式)(PDF形式, 62.76KB)
汚水排出量減量認定通知書(第2号様式)(PDF形式, 62.76KB) 汚水排出量減量申告書(第3号様式)(PDF形式, 81.63KB)
汚水排出量減量申告書(第3号様式)(PDF形式, 81.63KB) 汚水排出量減量認定変更等届出書(第4号様式)(PDF形式, 71.79KB)
汚水排出量減量認定変更等届出書(第4号様式)(PDF形式, 71.79KB) 汚水排出量減量申告に係る委任状(PDF形式, 54.67KB)
汚水排出量減量申告に係る委任状(PDF形式, 54.67KB)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。