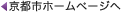京都モノづくりの殿堂・工房学習
ページ番号344079
2026年2月6日
平成21年2月、京都の伝統文化・工芸から発展してきた現在の先端技術産業を中心に「ものづくり都市・京都」の企業創業者・科学者等の歩んできた道やモノづくりにかける情熱・努力等を学び、子どもたちが自らの生き方を考え、生きる力を育む「京都モノづくりの殿堂」並びに「モノづくり第1工房」を生き方探究館の1階に開設しました。また、子どもたちのモノづくり体験の充実を目指し、平成22年8月には地下に「モノづくり第2工房」を開設しました。
京都市立小学校を対象に実施している「京都モノづくりの殿堂」学習プログラムでは、現在の京都を代表する「ものづくり」企業の持つ資産を活用しています。子どもたちに今まであまり知らされていなかった視点(先端産業)から京都の姿を伝えるとともに、伝統産業から発展してきた現在の先端技術やそれを支える科学への興味関心を高めること、また創業者等の歩んだ道や、ものづくりに携わる人々の仕事に対する情熱から、自身の将来や夢に向かう意欲を高めることを目指しています。
京都モノづくりの殿堂
企業の企業創業者等17企業16ブース
先端技術産業を中心に「ものづくり都市・京都」を支える京都の企業創業者・科学者等の創業や研究の動機・あゆみ、日常生活と密接につながる技術・製品等を紹介する17企業16のブースを設置しています。各ブースでは、パネルや映像コンテンツの上映、製品見本の設置、クイズ形式による学習等、工夫を凝らした展示を展開しています。
〈17企業16ブースの内訳〉
- 株式会社イシダ
- 立石 一真氏(オムロン株式会社)
- 初代・二代目 川島 甚兵衞氏(株式会社川島織物セルコン)
- 稲盛 和夫氏(京セラ株式会社)
- 初代・二代目 島津 源蔵氏(株式会社島津製作所・株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション)
- 株式会社SCREENホールディングス
- ニチコン株式会社
- 鈴木 直樹氏(NISSHA株式会社)
- 日本新薬株式会社
- 永守 重信氏(ニデック株式会社)
- 任天堂株式会社
- 堀場 雅夫氏(株式会社堀場製作所)
- 村田 純一氏(村田機械株式会社)
- 村田 昭氏(株式会社村田製作所)
- ローム株式会社
- 塚本 幸一氏(株式会社ワコール)
企業ブース1
企業ブース2
京都を代表する科学者・技術者・匠等の紹介パネル・映像ディスプレイ
○京都ゆかりのノーベル賞受賞者展示コーナー(平成22年4月設置・平成31年3月増設)
京都にゆかりのあるノーベル賞受賞者(科学者編)14名について、その業績や生涯をパネルや映像により紹介しています。
○近代産業や先端技術へ通じる伝統産業の紹介や卓越した技術を持つ匠の作品や技を映像により紹介しています。
京都ゆかりのノーベル賞受賞者展示コーナー1
京都ゆかりのノーベル賞受賞者展示コーナー2
京都モノづくりの系譜
伝統産業から近代産業、さらには先端技術産業へとつながり発展した京都のモノづくりの変遷と歴史を伝える「京都モノづくりの系譜」をパネルで紹介しています。
モノづくりの系譜コーナー1
モノづくりの系譜コーナー2
「工具の世界へようこそ・工具の歴史・工具ができるまで」のパネル
産業革命を経て西洋文明とともに日本へやってきた工具の歴史やモノづくりを支える高品質な工具ができるまでをパネルで紹介しています。
工具コーナー1
工具コーナー2
モノづくり工房
京都のモノづくり企業の代表的な技術や製品の仕組みについて、簡単な工作・実験を通じて体験します。内容は、協賛企業の皆様からの提案や支援を得て開発しています。
|
|
プログラム名 |
提供企業 |
内容 |
|
1 |
音を奏でるふしぎな石ころ |
株式会社村田製作所 |
電気信号を音に変える圧電サウンダーでオルゴールを製作 |
|
2 |
半導体の光“LED” |
ローム株式会社 |
フルカラーLEDで光の三原色を組合せるLED点灯装置を製作 |
|
3 |
タッチからはじまる未来 |
NISSHA株式会社 |
電導性フィルムでタッチパネル式LED点灯装置を製作 |
|
4 |
世界に一つの温度計 |
株式会社堀場製作所 |
温度センサーで様々な熱源を測る簡易電子温度計を製作 |
|
5 |
セラミックスで電気を起こそう! |
京セラ株式会社 |
力を電気に変える圧電素子でLED点灯装置を製作 |
|
6 |
ひかりを調べよう |
株式会社島津製作所 |
様々な光源の成分(スペクトル)を分ける分光器を製作 |
|
7 |
半導体の面白さを知ろう |
株式会社SCREENホールディングス |
半導体を用いてLEDの点滅を制御させる装置を製作 |
|
8 |
夢がふくらむ化学の力 |
積水化成品工業・ 積水化学工業 |
熱で膨張するビーズで弾力性のあるスチロールボールを製作 |
|
9 |
夢を守る化学の力 |
積水化学工業 |
中間膜を使用したものさしを製作 |
|
10 |
自動化にはカラクリがある?! |
村田機械株式会社 |
動く力を伝えるカムとジョイントを組合せて文字を描く |
工房の様子
工房での学習の様子
京都モノづくりの殿堂 学習プログラム
学習活動のねらい
○京都では、優れたものづくりの伝統を受け継いだ工業が盛んであることを理解するとともに、日本のものづくりをリードする京都の先端産業や先端科学に関心をもつようにする。
○ものづくり企業創業者の生き方やものづくりに携わる人のものづくりへの情熱にふれることを通して、自身の将来や夢について考えを深め、その実現にむけて意欲をもつようにする。
学習活動の流れ
「京都モノづくりの殿堂」学習プログラムの流れはおおよそ次の通りです。
- 事前の学習(学校):学習のめあてを確かめたり、自分の学習問題を考えたりする活動
- 殿堂ブース展示学習(探究館):京都を代表する17企業16ブースの展示(創業者等のあゆみ・技術・製品とくらし)等から、調べて学ぶ活動
- 工房体験学習(探究館):先端技術の原理や仕組みを組立や分解、製作や実験で体験する活動
- 事後の学習(学校):探究館での活動を振り返り、整理やまとめをする活動

工房学習の様子(モノを運ぶカラクリの製作)

工房学習の様子(電子オルゴールの完成)
令和6年度の実施状況
令和6年度は、京都市立小学校及び総合支援学校138校が学習を実施しました。
○実施学校数 137校(対象:4~6年生)
○参加児童数 7,921名
○開催回数 143回
京(みやこ)モノレンジャー(モノづくり学習支援員)
「京都モノづくりの殿堂・工房学習」では、企業等OBからなるボランティア組織「京(みやこ)モノレンジャー」の方々に学習を支援いただいています。
「モノづくりの楽しさ・奥深さをたくさんの子どもたちに伝えたい!」「モノづくりの知識やこれまでの経験を活かして子どもたちに将来の夢を考えるきっかけを与えたい!」という熱い思いのもと、令和2年4月現在、219名の方々に御登録いただき、次のような活動をされています。
京(みやこ)モノレンジャーの活動内容
○工房学習支援ボランティア…主に「モノづくり工房」で小学生が行う体験活動の指導や支援を行います。
○殿堂学習支援ボランティア…主に小学生が展示学習を行う「京都モノづくりの殿堂」で、展示内容の説明や案内活動を行います。
「モノづくり工房」での体験活動の支援
「京都モノづくりの殿堂」での展示学習の支援
京(みやこ)モノレンジャー(モノづくり学習支援員) マスター講習会
京(みやこ)モノレンジャーの活動内容や児童との関わり方について理解を深めていただくため講習会を行っています。
「京都モノづくりの殿堂」一般公開
京都モノづくりの殿堂・工房学習を体験しよう!
普段は、京都市立学校の児童が授業の一環として学習する本施設ですが、夏期休業期間中等に体験会を行っています。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局京都まなびの街生き方探究館企画推進室
電話:075-253-0880
ファックス:075-253-0878