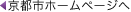区内の施設案内-名所・史跡-
ページ番号72733
2012年10月18日
※すべて住所は京都市下京区内、電話番号の記載のあるものは市外局番(075)です
名所・史跡
赤松小三郎遭難地碑

東洞院通五条下る

佐久間象山から兵学、洋学を学び、勝海舟にも師事した信州上田藩士の赤松小三郎は、京都で塾を開き英国式歩兵練法を教えて名声を得ました。薩摩藩士にも教授しましたが、藩に呼び戻されることになったとき、攘夷運動で活躍した中村半次郎(のちの桐野利秋)らの天誅によって五条東洞院で暗殺されました。
梅ヶ枝手水鉢

西堀川通木津屋橋角

「ひらがな盛哀記」という歌舞伎には、夫のために遊女となった梅ヶ枝が、金の工面のためにこの手水鉢に向かって祈った一幕があり、明治時代にはその様子を諷した俗謡が流行しました。
鉄輪の井(命婦稲荷神社)

堺町通松原下る鍛冶屋町

謡曲「鉄輪」の中で、洛北貴船の神の神託によって鉄輪を被り、生霊と化して自分を捨てた夫に復讐した女性が使っていた井戸とされています。現在水は枯れていますが、その伝説からこの井戸水は縁切りに効果があるといわれていました。
膏薬図子(こうやくのずし)

四条通と綾小路間の新釜座町・矢田町

図子は辻子とも書き、平安京の都市再開発のために設けられた細道を意味しています。平安中期の僧・空也がここに道場を開き、「空也供養の道場」と呼ばれていたのが転じて「膏薬」になったという説が伝えられています。
左女牛井(さめがい)跡碑

堀川通六条上る柿本町

六条堀川邸とも呼ばれる源氏累代の居宅にあった左女牛井の水は、天下の名水と称えられ、千利休も茶の湯に用いたと伝わっています。
島原大門

花屋町通大門西入上之町

江戸期に繁栄した花街・島原の東の入口に残る大門は、切妻造、本瓦葺の風情ある構えで、にぎわっていた往時の面影をとどめています。
渉成園

間之町通正面東入東玉水町

東本願寺の別邸であり、周囲に枳殻(からたち)が植えられていたことから枳殻邸(きこくてい)とも呼ばれています。本願寺十三代宣如上人の時代に、石川丈山らによって造られた池泉回遊式の庭園で、国の名勝に指定されています。
彰如上人(東本願寺第23代。号・句仏)「勿体なや祖師は紙子の九十年」の句碑があります。
親鸞聖人入滅の地碑

西洞院通松原東入薮下町 光円寺門前

松原通(旧五条通)西洞院界隈は、親鸞が生涯を閉じた場所と伝えられ、光円寺の門前にはこれを示す石碑が設けられています。
芹根水跡碑

西堀川通塩小路上る御方紺屋町

平安期より霊水といわれ、室町期には能阿弥によって茶の七名水の1つに数えられました。江戸時代の書家・烏石葛辰が刻んだ石碑がその名残をとどめています。
電気鉄道事業発祥地碑

東洞院通塩小路角

明治28年2月、我が国最初の「市街電車」が、塩小路高倉と伏見区下油掛町間、約6.4キロメートルを走りました。
古高俊太郎寓居跡

西木屋町通四条上る西入真町

元治元年(1864)6月5日、勤皇浪士のためアジトを提供するなどしていた古高俊太郎宅に新選組隊士が押し寄せ、家宅捜索のうえ拷問を加えて厳しく取り調べました。古高の自白によって、新選組は長州志士が集まっていた池田屋を襲撃し、のち古高は六角獄舎で処刑されました。古高俊太郎寓居跡を示す石碑は、四条小橋に近い繁華街に建てられています。
平安京朱雀大路跡銘板

中堂寺南町1 JR丹波口駅構内
JR丹波口駅構内、出改札口前の柱の根本に、「平安京朱雀大路跡」と記す銘板がはめ込まれています。
本居宣長修学地碑

室町通綾小路西入善長寺町

江戸中期の国学者として名高い本居宣長が青年時代、医学や儒学を学ぶために寄寓していた儒医の堀景山宅跡に建てられた碑。宣長は京都遊学時の体験を「在京日記」に書き残しています。
与謝蕪村句碑(宗徳寺 粟嶋堂)

岩上通塩小路上る三軒替地町125

「粟島へはだしまいりや春の雨」
娘の病気平癒祈願に訪れた与謝蕪村が詠んだ句です。
お問い合わせ先
京都市 下京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:【まちづくり企画・事業担当】 075-371-7164 【広聴コミュニティ活性化・振興担当】 075-371-7170
ファックス:075-351-4439