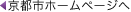区内の施設案内-寺社-
ページ番号12669
2012年10月18日
※すべて住所は京都市下京区内、電話番号の記載のあるものは市外局番(075)です
寺社
文子天満宮(あやこてんまんぐう)

間之町通花屋町下る天神町400

菅原道真を祭神とする神社。道真の乳母だった多治比文子が、道真の没後、自宅に祠を建てて祀ったのが起源と伝え、天神信仰発祥の神社ともいわれています。
市比売神社

市姫通下寺町東入本塩竈町593

市比売神社は延暦14年(795)、平安京の東西市を守護する神社として創祀されました。市場の繁昌に御利益があるほか、女性の神を五神祀っているため、女性の守護神としても篤い信仰を集めてきました。近年は、現代アートのモニュメントのようなカード塚が作られ、期限切れのクレジットカードなどあらゆるカードを供養するという現代的なお祭りも行われています。
延寿寺

河原町通六条上る本塩竃町588

平安末期の後白河天皇は、嘉応元年(1169)仏門に入り法皇となって、院御所「六条殿」に仏堂を建立しました。
六条殿内の仏堂はのちに独立して延寿寺と称し、金仏寺と通称され著名となりましたが、幕末の兵火で本尊は焼失し、現在は金仏を模した木像が祀られています。長講堂はのちに豊臣秀吉によって西隣りの現在地に移され、境内の御影堂には、江戸初期に造られた後白河法皇坐像(写真)が安置されています。
冠者殿社

寺町通四条東入貞安前之町

源頼朝に仕えていた土佐坊昌俊は、文治元年(1185)義経追討を命じられ京に上りました。昌俊はまず堀川邸に義経を訪ねましたが、上洛の目的を怪しまれ、義経を暗殺する意志がない旨を誓紙に書かされたそうです。昌俊はその約束を破って堀川邸を襲撃しましたが失敗し、六条河原で処刑されました。最期に臨んで昌俊は、忠義のために偽りの誓約をする者の罪を救ってほしいと願ったといわれます。これにちなんで、昌俊の慰霊のために創祀された冠者殿社は「誓文」の神として信仰されるようになりました。
こうした言い伝えをもとに、地元の商人たちは日ごろ商売上の駆け引きでやむを得ずついた「嘘」を祓い清めてもらおうと、毎年10月20日に詣でたのが「誓文払」で、いつしかこれに合わせて大売り出しをする風習も生まれました。今も冠者殿社は、商売繁昌の神として地域の商売人の篤い信仰を集め続けています。
菅大臣神社

仏光寺通新町西入菅大臣町189

菅原道真の死後まもなく道真の邸宅(白梅殿)跡に創祀されたと伝えられ、道真生誕の地ともいわれています。仏光寺通を隔てた北側には、道真の父・是善を祀ってきた北菅大臣神社(紅梅殿神社)があります。
光縁寺

大宮通綾小路西入四条大宮町36・37

壬生寺に近い光縁寺墓地には新選組隊士たちの墓碑が並んでおり、その中に、新選組結成時から近藤勇らの同志だった山南敬介の墓も含まれています。新選組が屯所を西本願寺に移すことになった慶応元年(1865)、山南は移転に反対して隊を脱走しましたが、捕らえられ切腹させられたとのことです。
興正寺

堀川通七条上る花園町70

本願寺8代の蓮如上人に帰依した経豪が仏光寺の住持職を辞して、同志とともに本願寺のあった山科に創建したのが起源とされ、仏光寺の旧称である興正寺と命名しました。本願寺の移転に伴って寺地を移し、天正19年(1591)に現在地に移りました。
五条天神社

西洞院通松原西入天神前町351

平安遷都の際大和国(現・奈良県)の宇陀から移されたと伝わる京都有数の古社で、医療の神として信仰を集め、「天使社」とも称していました。社が面する松原通は平安時代には五条大路と呼ばれていて、牛若丸と弁慶が出会ったのは、ここの境内だとも伝えます。
権現寺

朱雀裏畑町22

平安期に、大和国(現・奈良県)の元興寺から勝軍地蔵を移して七条朱雀の歓喜寺に安置したのが起源といわれ、戦乱で荒廃したあと権現堂のみが残ったと伝えられています。門前には、世に「六条判官」と呼ばれ源氏の棟梁だったが、保元の乱(1156)で敗れ朱雀野で処刑された源為義の供養塔があります。
「朱雀の地蔵堂」とも称される権現寺の地蔵堂には、「さんせう太夫」の物語で知られる厨子王丸の危難を救ったと伝えられる身代り地蔵が安置され、また、厨子王丸をかくまったというつづらの断片が寺宝として保存されています。こうした伝説から、当寺には「災難除け」のご利益があると伝わっています。
俊成社

烏丸通松原下る俊成町

平安末期の歌人・藤原俊成の住居跡に俊成の霊を祀ったのが起源とされています。俊成の命日である11月28日には、俊成の画像と稲荷大明神の軸を掲げて「お火焚祭」が行われます。
上徳寺(世継地蔵)

富小路通五条下る本塩竃町556

徳川家康の息女泰誉院と、その生母である上徳院の菩提を弔うために創建された寺院。境内にある世継地蔵に折願するとよい世継が授けられるといわれ、人々の信仰を集めています。
新玉津島神社

烏丸通松原西入玉津島町309

歌人の藤原俊成が歌道の神として創祀。江戸期には歌人の北村季吟が宮司を務めながら弟子を育て、その1人に松尾芭蕉がいたことから、今も多くの人が短歌・俳句・文章上達の祈願に訪れています。
神明神社

東洞院通綾小路東入神明町

平安末期の公家である藤原忠通の邸宅にあった鎮守社が起源。同じく平安末期の武将・源頼政が鵺退治にあたって祈願し、成功のお礼として奉納したと伝わる弓矢が社務所に飾られています。
住吉神社

大宮通中堂寺西入薮之内町617
創建者は藤原顯輔卿。祭神は表筒男命、中筒男命、底筒男命。本殿は文政8年(1825)の再建、稲荷社は、嘉永5年(1852)の再建。猿田彦面神宝は安永9年(1780)の奉納。例祭は9月28日ごろの日曜日。延暦年間の創建。安永~寛政年間の祭は5月19日から10日間にわたって催され、練り物が出てにぎわったと記録に見えます。
諏訪神社

諏訪町通五条下る下諏訪町351

平安初期の武将として名高い坂上田村麻呂が信州(現・長野県)諏訪大明神を勧請し、創建した神社といわれています。現在の社殿は孝明天皇が再建したものと伝わっています。
善徳寺

中堂寺西寺町13

「赤寺さん」と親しまれる善徳寺を訪れると、鮮やかな赤壁が印象に残ります。江戸時代、紅屋を営み成功した檀家の木村平兵衛が、寄進した山門の土壁を京紅で塗ったことから、赤壁の美しさが評判となり、美人になれるというご利益が広まりました。時を経た今も、美を求める女性参拝者の信仰を集めています。
宗徳寺(粟嶋堂)

岩上通塩小路上る三軒替地町125

紀伊国(現・和歌山県)から勧請した粟嶋明神を祀り、古来から婦人病・安産の神として女性の信仰を集めてきましたが、明治の神仏分離によって粟嶋社を廃して粟嶋堂と改められました。境内に与謝蕪村の句碑があります。
綱敷行衛天満宮

西七条北東野町

左遷された菅原道真が博多に上陸し、船の綱を敷いて御座としたとき、道真は一夜のうちに白髪になったといわれますが、その姿を写した神像を祀ったことから綱敷天満宮の名がつけられたそうです。また、合祀されている近衛天満宮は、道真の乳母多治比文子の旧宅にちなんで創祀されたと伝えられます。
天道神社

猪熊通仏光寺西入西田町
延暦13年(794)、桓武天皇の平安遷都とともに、当時の銅駝坊の南、三条坊門東洞院に1丁4面の社地を賜り、勧請鎮座させたのが始まりと伝えられます。その後、たびたびの兵火のため焼失しましたが、天正2年(1574)、正親町帝の代になって、織田信長公から五条坊門猪熊に替地を授けられ再興、現在に至っています。本殿は、神明造り屋根銅版葺の造りで、ご神体は、御祭神・天照皇大神・春日大神・八幡大神を奉り、悪疫消除、子孫長久、開運の神と崇められています。また、往古には家畜の悪疫除けの信仰もあったとされます。
境内には高さ約20メートル、枝張り約12メートル、幹周約3メートルのクスノキがあります
道祖神社

油小路通塩小路下る南不動堂町528

宇多天皇の居所の1つ亭子院の鎮守社として祀られたのを起源とし、豊臣秀吉によって現在地に移されたと伝わっています。境内に道祖神の石像があり、旅人の安全を守る神として民間の信仰を集めました。
西本願寺

堀川通花屋町下る門前町
本願寺は、親鸞聖人の末娘である覚信尼が東山に創建した大谷廟堂を起源としており、戦乱によって各地を転々としたのち、豊臣秀吉から寺地を寄進されて現在地に移りました。徳川家康によって東本願寺が分立してから西本願寺と呼ばれるようになり、現在に至っています。
西本願寺の南側にある唐門は桃山建築の代表的作品であり、国宝に指定されています。入母屋造、桧皮葺の屋根の前後に唐破風がつけられ、細部にわたって見事な装飾・彫刻が施されています。
若一神社

七条御所ノ内本町97

平清盛が造営した西八条殿の鎮守社とも、同じ町内にある勝明寺の鎮守社ともいわれています。平清盛が、埋もれていた御神体を掘り起こして祀ったのちに出世したと伝わっており、現在も立身出世の神として崇敬されています。
梅林寺

梅小路東中町
創建時期は不詳ですが、元禄年間と思われます。江戸時代、土御門家が檀越(だんのつ=堂宇を寄進した施主)となりました。土御門家は安倍清晴の子孫で、陰陽道の大家として天下に名声を博しました。境内墓地にある安倍家代々の墓の中には、正二位安倍朝臣泰邦の墓もあり、天明4年5月9日と忌日が記されています。また、皇女和宮付上臈安倍邦子の墓などもあり、安倍家歴代の位牌も安置しています。
門内右手のお堂に祀られる大日如来は、西寺の旧仏と伝えられ、平安中期の作といわれています。この大日堂では、年頭に、蛇に見たてた丸太棒を青竹で打ちのめす「じじばい講」が行われます。
花咲稲荷社

間之町通松原上る稲荷町

江戸初期の歌人・俳人でもある松永貞徳が、自宅の鎮守社として創祀しました。社名は貞徳の号「花咲亭逍遥軒」にちなんでつけられたそうです。
繁昌神社(班女塚)

室町通高辻西入繁昌町308

班女ノ社とも呼ばれており、「宇治拾遺物語」によると、長門前司の娘の亡骸が邸内で動かなくなったため、その地に葬り祀ったのが起こりと伝えられています。現在は商売繁昌、縁結びの神として信仰されています。

境内にある班女塚(はんじょづか)は、長紋前司の娘を葬った塚といわれ、繁昌神社の旧鎮座地とされています。小祀とともに1個の岩石が祀られています。
東本願寺

烏丸通七条上る常葉町754

烏丸通に面して建つ壮大かつ重厚な御影堂門は、知恩院(東山区)・南禅寺(左京区)と並ぶ京都三大門の1つとされます。
御影堂の南側に並び建つ本堂・阿弥陀堂には、本尊の阿弥陀如来像が安置されています。
御影堂には、宗祖親鸞聖人の御真影が安置されています。明治28年(1895)に再建された入母屋造の御影堂は、面積約4400平方メートル、堂内は1度に4000人もの門徒が参拝できる世界最大級にして最後の木造建築と言われ、その偉観を放っています。
平等寺(因幡薬師)

烏丸通松原東入因幡堂町728

日本三如来の1つにも数えられる因幡薬師を本尊とする寺院。夢のお告げに従って因幡国(現・鳥取県)の海中から引き揚げられた薬師像が、京に飛来してきたという伝説が残されています。
福神社

中堂寺前田町
創建、由緒などについては不明ですが、上京区に紀貫之をまつる福大明神社があることから、何らかのかかわりがあるのではと考えられます。現在は社ひとつだけですが、昔付近は福神の森と呼ばれていました。
佛光寺

高倉通仏光寺下る新開町397

建暦2年(1212)、親鸞聖人のために、高弟の源海が創建した興隆正法寺(略称興正寺)が起源。7代目了源上人のとき本尊が盗まれましたが、時の後醍醐天皇が夢に見た宮中に差し込む光に従って探したところ、二条河原で見つかりました。このとき天皇から「阿弥陀佛光寺」の額を賜り、寺名を改めたと伝えます。
本光寺

油小路通木津屋橋上る油小路町281

江戸末期、京の街には幕末維新の嵐が吹き荒れ、至るところで殺戮が繰り返されました。下京には幕末維新にまつわる史跡がいくつも残されています。
尊王派で近藤勇らと意見が合わなかった新選組参謀の伊東甲子太郎は、新選組を脱退した後、近藤の妾宅に招かれた帰りに襲われ、油小路木津屋橋の本光寺門前で絶命しました。本光寺の門前にはこれにまつわる石碑と駒札が立っています。
明王院不動堂

油小路通塩小路下る南不動堂町7

空海作と伝わる不動明王像を本尊に安置する不動堂が油小路通に面して建っています。このあたりは昔不動堂村と呼ばれ、壬生から移ってきた新選組の本陣があったことでも知られています。
命婦稲荷神社

堺町通松原下る鍜冶屋町

鉄輪の井の傍らにある小祠。伏見稲荷大社の分社であり、家庭円満の神として信仰を集めています。
若宮八幡宮

若宮通花屋町上る若宮町

後冷泉天皇の勅願により源頼義が創建し、慶長10年(1605)に東山五条坂に移転した若宮八幡宮社の旧鎮座地に残る神社。左女牛井八幡とも呼ばれ、長く源氏の崇敬を受けていました。
大行寺

仏光寺通高倉東入る西前町380

本尊の阿弥陀如来立像は、鎌倉時代初期の代表的な仏師、快慶晩年の作です。
また、境内にある仏足跡(石)は、大行寺系と呼ばれ、日本の仏足跡四系統の中の一つを代表するものです。安政3年(1856)に建てられましたが、兵火のため粉砕し、昭和62年(1987)に原図を元に復元されました。
お問い合わせ先
京都市 下京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:【まちづくり企画・事業担当】 075-371-7164 【広聴コミュニティ活性化・振興担当】 075-371-7170
ファックス:075-351-4439