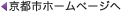烏丸線20系車両
ページ番号296682
2022年6月1日
烏丸線20系車両 ~Subway Karasuma Line "Type-20"~

外観
現行の烏丸線10系車両20編成のうち、開業当初から使用している第1次、2次車両9編成の老朽化にともない、新たに20系車両を製作しました。令和3年度から令和7年度にかけて、6両9編成、計54両を順次、導入していきます。製作にあたっては、安全性の向上、バリアフリー化、快適性の向上、省エネルギー化等を考慮しました。
デザイン
外観および内装デザインについては、デザインの専門家などをメンバーとする「地下鉄烏丸線車両の新造にかかるデザイン懇談会」で議論いただき、3つのデザインコンセプト「みんなにやさしい地下鉄に」、「京都ならではの地下鉄に」、「愛着がわく地下鉄に」を基に、市民および御利用の皆様から御意見を募集し、3つのデザイン案を制作しました。その中から最終的に市民や御利用の皆様に最も多くの投票をいただいたものに決定しました。
さらに、「京都ならではの地下鉄」として、京都の伝統産業の素材・技法を活用しました。
外観デザイン
前面の造形に曲面を多く採り入れ、これまでの烏丸線車両の標識灯・前照灯の配置を変更した近未来的なイメージを表現したデザインとしました。
カラーリングについては、烏丸線のラインカラーである緑色を踏襲しています。

投票により決定した外観デザイン

外観(正面)
視覚に障害がある方の御意見を踏まえ、乗降口ドア外側全体をエメラルドグリーン色にすることで、無塗装の車体側面とのコントラストが生まれ、弱視の方にも乗降口が分かりやすくなるように工夫しました。

乗降口ドア
内装デザイン
両端車両の運転室寄りには、車椅子やベビーカーを御利用のお客様のみならず、介添えの方や大きな荷物をお持ちのお客様にも安心・快適に御利用いただける多目的エリア(おもいやりエリア)を設置しました。

内装

おもいやりエリア(両端車両)
座席の表皮には「若草色」、「茜色」などの鮮やかな和の色彩、床には「鈍(にび)色」などの落ち着いた和の色彩を採用しました。
座席の表皮、袖仕切り・連結部扉部のガラスには、有職文様である「幸菱(さいわいびし)文様」を採用しました。

一般座席
(若草色・幸菱文様)

優先座席
(茜色・幸菱文様)

幸菱文様の袖仕切り
京都の伝統産業の素材・技法の活用
「京都ならではの地下鉄に」のコンセプトに基づき、外観・内装デザインに京都の伝統産業素材・技法を活用しました。少しでも業界全体の振興に繋げたいという各伝統産業の組合・事業者の方の思いと交通局の思いが一致して実現したものです。

車体

アルミニウム合金製の構体

前面非常はしごを
展開した状態
先頭構体はアルミニウム合金の骨組みと外板で構成された骨皮構造を基本に、主要部材に削り出し材を使用して溶接による歪みを低減し、外観の仕上がり向上を図るとともに、厚肉の主要部材を格子状に配置することで、10系車両と同等以上の強固な前面強化構造を実現しています。また、正面行先表示器や前尾灯にはLEDを採用して視認性を高めました。
車体前面の非常扉はリンク式の1枚扉とし、備え付けの非常はしごを使用することで地上へ脱出する際の安全を確保しています。


ドア出入り口の形状
ドア出入口下部のステップの形状をホーム側に傾斜することで、定員乗車時におけるステップとホームの段差を約2㎝まで低減し、車椅子を使用する方々をはじめとするお客様が乗降しやすくしました。
優先席、車椅子スペース、車内通報装置等

(上)車椅子スペース・優先座席
(下)2段手すり

車内通報装置
車椅子・ベビーカースペースを、1編成計12箇所(内2箇所はおもいやりエリア)設置し、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準(車椅子スペースを1編成2箇所以上)を大きく上回る設置数としています。
また、車椅子で移動される方、高齢の方など、だれもが利用しやすいように、出入口から連続する2段手すりを設置しました。
客室の車内通報装置の通報スイッチを押すと、乗務員に表示灯とブザーで知らせ、客室と乗務員の間で通話が可能となります。

31編成~
各車両には、優先席、車椅子スペースおよび車内通報装置を設けています。

車両乗降口の車内乗車位置表示板(烏丸線20系の例)
また、目の不自由なお客様のため、号車や扉番号を点字等により案内している車内乗車位置表示板をすべての車両に設置しています
機器

床下
主要機器は10系第3次~6次車両の制御装置等更新車両と互換性を確保しながら、一部に最新機器を採用しています。編成は各車両の重量平準化などを考慮し、中間に電動車を配置しています。各機器においては、安全かつ性能を十分に発揮させる為、防水・防じん・防振などを考慮し、運転・保守の容易化を図っています。
台車・連結器

台車

連結器
台車は、ボルスタレス構造を採用しています。台車枠は鋼板の溶接構造であり、通常の強度解析・静荷重試験に加え、溶接部の未溶着を仮定した強度解析を実施して強度を確認しています。けん引装置はZリンク構造で、車体を支える空気ばねは、万が一空気が抜けた場合でも、安全に車両を回送できるよう、特殊なストッパ機構を設けています。さらに、騒音を低減するための「防音車輪」を採用し、乗り心地を向上させています。
連結器には、不緩衝帯をなくし、乗り心地を向上させたダブルアクション型ゴム緩衝器を採用しています。
集電装置

パンタグラフ
集電装置は、枠組構造を10系車両の下枠交差型パンタグラフから、部品点数が少ないシングルアーム型パンタグラフに変更し、保守の簡略化・軽量化を図りました。動作方式はバネ上昇・空気下降式とし、互換性を考慮して車体の接続部寸法、操作電圧、空気圧などは下枠交差型パンタグラフと同一としています。
戸閉装置

戸閉装置(各ドア上)
戸閉装置は、扉が閉まる瞬間に締め付け力を一時的に軽減しており、お客様やお手回り品の挟み込みが発生した場合に脱出が容易になっています。
案内表示装置

車内案内表示器(10系車両)

車内案内表示器(20系車両)
現行車両と比べて画面サイズを拡大した17インチワイド液晶2画面一体型の車内案内表示器を、全扉に設置(現行車両は片方の扉に設置)し、耳の不自由な方をはじめとするお客様にとって、運行情報や非常時の案内などをより見やすくしました。また、インバウンド対応として4箇国語表示を採用しました。また、表示される内容については、カラーユニバーサルデザインの認証を取得しています。

緊急案内の表示例

側面行先表示器
(フルカラーLED方式)

正面表示器
(フルカラーLED方式)
側面行先表示器、正面表示器には、フルカラーLED方式のものを採用しました。
主要諸元
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269