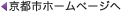烏丸線10系車両
ページ番号296711
2022年6月1日
烏丸線10系車両 ~Subway Karasuma Line "Type-10"~

第1次、2次車両の外観

第3次~6次車両の外観
第1次、2次車両は、昭和56年の京都~北大路間部分開業当時に製造しました。当初、4両編成で営業し、昭和63年の京都~竹田間の延伸開業時に中間車(T車)2両を増結し、6両編成としました。
第3次車両は、京都~竹田間の延伸開業時に製造しました。第1次、2次車両から、前頭形状を一部変更し、全体に丸みを持たせると共に貫通扉に窓を設けました。
第4次車両は、平成2年の北山~北大路間の延伸開業時に製造しました。基本仕様は第3次車両を踏襲しましたが、一部変更しております。その後、平成5年に第5次車両も製造しました。
第6次車両は、平成9年の北大路~国際会館間の延伸開業時に製造しました。全車に車椅子スペースを設置し(1箇所/両) 、客室に車内案内表示器を採用しました(4箇所/両)。
デザイン

内装
第1次、2次車両は、以下の考えのもと、製造いたしました。
●最新の技術を駆使して、安全で速く、しかも快適な乗り心地を目指す。
●省資源・省力化も十分に考慮した構造とする。
第3次~6次車両については、以下の考え方のもと、製造いたしました。
●第1次、2次車両の基本仕様を踏襲しつつ、車両の快適性の向上を図るべく一部改良を加える。
●近鉄京都線との相互直通運転に対応できる設備を備える。
車体

アルミニウム合金製の構体(第3~6次車両)

前面非常はしごを
展開した状態
車体は、全アルミニウム合金製とし、軽量化を図っています。前頭形状はなめらかな曲線をとり入れた前頭傾斜形のデザインとし、運転台正面ガラスを大きくして視野を広くしてあります。
正面の行先表示器は、大型のものを前照灯の間に配置し、遠くからでもはっきり確認できるようにしています。非常扉は上下2枚で構成して、下部の扉に渡り板を設けてあり、備え付けの非常はしごとともに非常時に乗客を安全に地上へ誘導できるよう配慮しています。
非常扉の表面には、エメラルドグリーンの帯を配してアクセントをつけ、京都市の地下鉄にふさわしい車体としています。
また、客室内の一部には車椅子用のスペースおよび優先座席を設けています。
優先席、車椅子スペース、車内通報装置等

優先座席エリア

床貼りシートデザイン

吊手デザイン
優先座席を必要とされるお客様に、これまで以上に優先座席を御利用していただきやすくなるよう、また、そうでないお客様には、優先座席であることを明確に認知していただけるよう、平成29年度に優先座席エリアをリニューアルしました。
床貼りシートの設置、吊手の色と高さの変更を行っています。

車内通報装置(第1次、2次車両)

車内通報装置(第3次~6次車両)
客室の車内通報装置の通報スイッチを押すと、乗務員に知らせることができます。

第1次、2次車両(01~09編成)

第3次~5次車両(10~17編成)

第6次車両(18~20編成)

車両乗降口の車内乗車位置表示板(烏丸線20系の例)
また、目の不自由なお客様のため、号車や扉番号を点字等により案内している車内乗車位置表示板をすべての車両に設置しています。
機器

床下(第3次~6次車両)
通勤用電車として安全に性能を発揮できるよう、機器の構成、配置などを工夫しています。車体の重量バランスを考えて床下に機器を配置しています。M2C(M2'C)車(以下M2)とM1(M1')車(以下M1)を1ユニットとして、M2系に電動空気圧縮機を始めとする空気源機器を搭載、M1系には制御機器をそれぞれ搭載しています。またM1系同士、M2系同士で出来るだけ共通配管にしています。
台車

台車
台車は、シンプルな構造としつつも、十分な剛性があり、かつ重量の軽減を図っています。空気ばねは、上下動および左右動に優れた特性を有した、乗り心地のよいものを採用しています。
集電装置

パンタグラフ
集電装置は、屋根上占有面積の小さい下枠交差形パンタグラフを採用しています。ばね上昇、空気下降式で、かぎ外し操作用としてパンタグラフ本体に電磁かぎ外し装置を搭載しています。良好な集電性能と架線の変動に対する追従性をもたせた設計としています。また、メンテナンスの容易化と信頼性の向上も図っています。
機器の更新
制御装置等の更新(第3次~6次車両)

VVVFインバータ装置
電機子チョッパ方式の制御装置の主要部品が生産中止になったため、第3次~6次車両の11編成をVVVFインバータ装置へ更新しました。また、VVVFインバータ装置への更新に合わせて、他の主要装置についても更新しています。
(おもな更新内容)
制御装置 : 電機子チョッパ方式 ⇒ VVVFインバータ装置
主電動機 : 直流直巻電動機 ⇒ 三相かご形誘導電動機
ブレーキ装置 : 電気指令式電空併用空気演算方式(MBS-R形)
⇒ 電気指令式電空併用電気演算方式(MBSA形)
低圧電源装置 : ブラシレスMG ⇒ SIV装置
モニタ装置 : 機器故障時の乗務員支援機能のみ
⇒ 機器故障時の乗務員支援機能に加え、運転状況記録機能、試運転機能、車上試験機能を付加
ATC装置 : 冗長度3重系 ⇒ 冗長度並列2重系
室内灯のLEDへの更新(第3次~6次車両)

室内灯(第3次~6次車両)
室内灯の蛍光灯具の更新に合わせて、LED化しました。LED化することにより、省エネルギー、省メンテナンス、廃棄物(管球など)の抑制をすることができます。
案内表示装置の更新(第3次~6次車両)

車内案内表示器(フルカラー液晶方式)

側面行先表示器
(カラーLED方式)

正面表示器
(カラーLED方式)
機器の更新に合わせて、車内案内表示器および側面行先表示器(車外)を、4箇国語(日・英・中・韓)表示が可能な機器へと更新しました。車内案内表示器はフルカラー液晶方式、側面行先表示器はカラーLED方式です。あわせて、正面表示器(車外)も、カラーLED方式に更新しました。

緊急案内の表示例
主要諸元
その他
お問い合わせ先
京都市 交通局高速鉄道部高速車両課
電話:075-863-5263
ファックス:075-863-5269