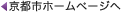【レポート】 令和6年度総合教育会議(令和6年12月17日)
ページ番号337454
2025年2月10日
【テーマ】「ウェルビーイングの向上を目指して~未来社会を見据えて~」
令和6年12月17日、「ウェルビーイングの向上を目指して~未来社会を見据えて~」をテーマに令和6年度京都市総合教育会議を開催しました。
会議での概要は以下のとおりです。また、会議全体の議事録は本ページ最下部の「会議の詳細はこちら」をご覧ください。
開会挨拶
松井 市長
まもなく2月25日の市長就任から、10ヵ月が経とうとしている。この間、「市民対話会議」を開催してきたが、京都市の教育は、市民から高い評価をいただいている。これもひとえに、教育委員の先生方や事務局職員、学校現場の教職員の方、PTAをはじめ保護者や地域の皆様など、学校教育に関わる全ての方々の力添えの結果である。
「新しい公共」は、公教育を公務員や教職員だけで担うのではなく、公教育に関わる全ての方が、公共性を共に担っていただくという概念だが、本市では、全ての学校園に学校運営協議会を設置しており、学力のみならず、児童生徒の学校に対する前向きな気持ちや、地域の方々の学校への関わりも含め、コミュニティスクールが充実した成果を結んでいる。
一方、少子高齢化の中、京都がさらに前向きに発展していくために、新京都戦略(骨子)を策定し、パブリックコメントを募集している。例えば、新京都戦略(骨子)には、「学芸があふれるまち」を掲げているが、この概念は、教育に限らず、文化・芸術政策やまちづくりに関わるもの。京都が「学芸があふれるまち」や「まち中に夢中になって物事に取り組む子どもや人間が溢れるまち」になることで、社会全体がウェルビーイングの度合いを高めていくことに繋がっていくと考えている。
京都のまち柄を深堀りし、京都ならでは魅力を高め世界で唯一の価値を持つまちをつくりたい。そして、子どもたち一人一人が個性とやりがいに溢れ、多様な個性を育み、他者の個性を尊重できる人格を育てる教育を目指したい。
意見交換
松山 教育委員
今後、外国人人口が増加することは明らかだが、最近の京都を見ていると、教育を受ける場所として、京都を選ぶ海外の方が増えている印象。安全であり、文化にあふれるまちである京都は、世界中でも優位性があると感じており、人口増加にも資する取組でもあることから、京都で様々な方々に教育を受けていただける体制を整えてほしい。
ダイバーシティの地域づくりに向けては、子どもたちだけでなく、保護者も含めて、タブーや文化の重要性についてともに学び、全ての方々が安心して暮らせる工夫が大事。
先日、ある市立中学校を視察したが、親と学校の先生しか大人を知らない子どもたちが多いと感じた。様々な研究において、子どもの頃から良い大人のモデルケースに会うことは、将来の子どもの成功の最も重要なキーであると明らかになっているが、そのためには同窓会が大事だと考えている。自分たちが卒業した学校や地域に貢献したいという大人は想像以上に多いため、例えば、小学校や中学校でも同窓会組織を構築し、協力を仰ぐ体制があればよいと考える。
笹岡 教育委員
海外の方々を受け入れる体制整備は必要だと思うし、京都市にはそういう期待があると認識している。
また、外国にルーツを持つ子どもと、京都の子どもが交流することも非常に大切で、そのためには、京都の文化を英語で発信するなど公教育における英語教育の充実も必要。
さらに、各校が、それぞれの特色を改めて考える時間が必要。先日、ある市立小中学校で授業を行ったが、地域と学校の繋がりが強く、一体となっていた。また、小学校1年生から英語教育に取り組んでおり、こうした学校の取組が認められ、地域の都市格があがっており、移住したいという人が後を絶たない。各学校がこうした特色を出すことが大事であると感じている。
野口 教育委員
文化的魅力と宗教的なタブーは矛盾すると感じており、問題が明らかであれば、理解を広めていくことが解決点になるため、オープンに話し合える場所を作っていくことが重要。本市では、韓国・朝鮮にルーツをもつ児童に対しては、コリアみんぞく教室が設けられているが、子どもたちは自国文化に誇りを持っているにも関わらず、クローズな仕組みになっている。国際都市において、教育はある意味で良い突破口になるため、良い施策を展開できればと考えている。
石井 教育委員
パブリックはオープンであることが根本であり、何者も排除しないことが重要。国際性は、多様な人が往来することによって生まれるものであり、市長がおっしゃる「学芸あふれるまちづくり」は、重要なビジョンであると賛同している。
一方、そのビジョンをウェルビーイングとどのように繋げるか。日本社会が何故ウェルビーイングではないのかという視点では、日本社会の特徴である協調性や共同性が、90年代以降、ネガティブな共同性、すなわちビクビクする共同性や同調圧力として機能していることが考えられる。基本、他者は自分とは違う存在で、本来的には分かり合えないかもしれないが、対話して妥協点を探ることが公共の発想。多様性の交わりを大事にする必要がある。
日本型教育では、授業研究や特別活動等、共同性から生まれたものが海外で評価されている。インターナショナルスクールと公立学校の交流など、子どもたち同士が交流を行い、異質な者同士の対話を重ねることが重要。そういったことを学校内で仕組化するためには、人材が必要。京都市の教育行政ほど、人にお金をかけている自治体はないと感じており、京都市教育委員会が教育先進自治体である核心はそこにあると思う。多様性に対して、個別対応するには限界がある。処遇改善や定数改善が進んでいるが、国を待っていられない。優れた方を京都に呼び込むためにも、人に投資する視点は必要であり、余裕のある状態で、公立学校で教育実践を積み重ねることが大事。
濱崎 教育委員
海外から来られた大学生の中には、日本に来て学んだものの、寂しい思いをして国に帰る事例が多いと感じている。要因として、日本人のコミュニティに入っていけないことや、自宅に招かれないことに悩んでいると聞く。義務教育段階においても、海外の方を地域全体で受け入れを積極的に行うことを仕組化しなければ、悪気がなくとも日本人は気が付かない。こうした面についても、教職員だけでなく、地域の方々が積極的に学校をサポートするシステムができれば良いと思う。
松井 市長
できるだけ価値観の違う人たちを混ぜて、交流する場を作ることが重要であると感じた。先日、児童館を視察した際には、家庭と学校で十分と思ってる子どもが多いと聞いたが、異なる価値観や文化を持った大人と関わりがない状態で満足していることは、気になる。児童館等のサードプレイスや図書館の機能を拡張したフォースプレイス等、包摂性が高く、異文化など様々な価値観に触れ、折り合いをつけて生きていく場を作ることが重要。こうした取組がウェルビーイングな社会に繋がると考えている。
松山 教育委員
図書館は可能性があると考えている。以前、ニューヨークにある図書館のドキュメンタリー映像を観たが、食の斡旋や音楽のライブ等、本は置いてあるが本を読む場所ではなく、皆が集まる場所という立ち位置になっていた。広く市民に利用いただく目的としては、本が置いてある静かな場所という図書館の機能は、相当限定的であり、皆が集まれる場所になるよう、工夫するべき。
また、海外の方からは![]() 「せっかく京都で学んでいるのに、お寺に行く機会もなければ、京都の人たちと交流する機会もない。」、「京都という場所で勉強するなら、京都らしい哲学や京都イズムを学ぶ機会があった方がいいのではないか」と言われることもあり、こうした取組は、実施していただきたい。地域の小学校との交流や、京都を改めて知る機会を提供することは重要だと考えている。
「せっかく京都で学んでいるのに、お寺に行く機会もなければ、京都の人たちと交流する機会もない。」、「京都という場所で勉強するなら、京都らしい哲学や京都イズムを学ぶ機会があった方がいいのではないか」と言われることもあり、こうした取組は、実施していただきたい。地域の小学校との交流や、京都を改めて知る機会を提供することは重要だと考えている。
石井 教育委員
早い段階から、海外の方を外国人というカテゴリーで考えるのではなく、隣人として捉えられることが重要で、この感覚があれば日本国内だけでなく、世界で活躍するという価値観が生まれる。国際性の核心は、いかにこの感覚を実装するかである。
「学芸あふれるまち」は、単なるリスキリングではなく、大人自身が学芸しているまちであるかどうか。日本のウェルビーイングが低い所以は、一つはビクビクして尖がれない、自分を出せないこと。一方、自分に適していることは内省のみでは見えないため、様々な経験の中で気づくものでありそれこそが探究の核心。様々な経験をする機会があることが、子どもたちが自分なりの「おもしろさ」や自分を発見する契機になる。もう一つは、世の中への関心がないこと。そもそも、世の中が面白くないから、子どもたちが世の中に関心がないとも言えるため、大人が試されている。勉強ではなくて新しい世界に広がる、つながること。そういう学びのある人生かどうかが重要。学芸する経験、つまり「生涯学芸社会」を目指すことは大変重要。学芸する場として図書館も再定義される。本来、日本の公民館の役割ではあるが、市民活動が空洞化している中、皆が集まる図書館について、改めて公民館機能の担い手としても捉え、教養・学芸ある市民を作るコンセプトでそのあり方を展望することが大事。そのためには、本市職員や教職員も学芸する存在であるとよい。
一方、ウェルビーイングを主観の側からのみ捉えすぎてしまうと、弱点がある。元々、ウェルビーイングは生き方の幅(ケイパビリティ)がベースにあるが、いわゆるしんどい子どもは、しんどい状況を前提に主観的に生き方を見積もってしまっているため、客観的に見たときにも生き方の幅が狭くなってしまいがちである。子どもたちの生き方の実質的な幅やキャリアイメージを広げ、「世界はおもしろい」ということを伝えていくことが学校の役割である。それを実現するためには、先生方に余裕があることが必要。
笹岡 教育委員
子どもに学校で経験してほしいことは、友達づくりと失敗。友達づくりについては、意見の異なる子も含めて、様々な出会いと交流をしてほしい。交流の場としてのサードプレイスやフォースプレイスについては、学校に代わる居場所になるものであり、賛同する。特に、海外にルーツを持つ子どもとの交流は重要。失敗することは、成長に繋がるもので、経験値になる。学校においても、様々な挑戦ができる環境づくりが必要。
また、教師をはじめとする学校全体のウェルビーイングは、重要である。ウェルビーイングを語る上で、教師は欠かせない。教師が幸せでなければ、子どももついていかない。ある市立中学校を視察した際、先生が輝いていた。コロナ禍でなければ学校改革できなかったと言われており、時間ができたからこそ学校改革ができた。先生方は学校を良くしようという強い気持ちを持っている。様々な対応で多忙な教師が一人で抱え込まない環境づくりに向け、人的配置も含め、フォローしなければならないと感じている。
野口 教育委員
全国的に少子化が進んでおり、要因として、経済的な面があげられるが、体験上、キャリア形成と子育ての時期が重なるため、サポートがなければ、子どもを産めないと感じている。地域で子どもを育てる仕組みができれば良いと考えており、高齢者等の「出番」づくりとして、子育てに参加してもらえる場や、医療面では軽微な発熱時に子どもを預ってもらえる仕組みを作ってほしい。
濱崎 教育委員
ウェルビーイングに関する調査で、「人の役に立つ人間になりたい」と思う割合は高いが、「地域や社会を良くするために何かしてみたい」と思う割合が低いことは問題だと感じる。
自分がどのように生かされてきたか考えると、地域や社会を良くするために貢献できないかと思えることが役に立つ人間になること。思いだけが強くなり、社会に出て挫けないか心配。地域や相手のことを考えることを子どもの頃に学べる環境づくりが重要。
いかに多様な価値観を持つ親であったとしても、子どもが親と学校の価値観に限られていれば、「おもしろい」、「価値がある」と思えない恐れがある。学校のカリキュラムに余裕がないことは要因の一つでは。子どもたちが自ら価値を発見する場や、それができる時間的な余裕が必要。
結城 総合企画局長
新京都戦略にも掲げているが、「夢中になれるまちづくり」は重要であると感じている。ウェルビーイングは、人それぞれに感じ方があるものの、一人一人に合う選択の幅を広げ、選択した後、やり直せる教育をつくることが理想。
吉田 副市長
子どものウェルビーイング向上に向けては、地域や大人が多くの子どもに接する気概をどのように作るかという点を意識しなければならないと感じている。60代前半の世代は、現在、地域で中心となる立場になっており、当事者として課題意識を持たなければならない。
部活動の地域移行は、元々、少子化や教師の負担軽減を目的としていたが、子どもの自己実現や可能性を広げるという視点でも仕組みを検討している。その中で、地域の方が子どもたちの活動に関わる仕組みづくりは、大人が子どもに関わる機会づくりに繋がると考えている。ウェルビーイングな環境づくりを具体的に実現するためには、部活動の地域移行等が活用できればと考えている。
寺澤 子ども若者はぐくみ局はぐくみ創造推進室長
子ども若者はぐくみ局では、現在、令和7年度から5年間を取組期間とする子ども若者に係る、新たな総合的な計画である「はぐくみプラン」を策定しているところである。少子化については、経済的な支援はもとより、幼児・病後児保育の安定的な運営や、外国人、ヤングケアラー、貧困等、多様化する支援ニーズの対応や、異年齢の子どもが交流する児童館等、第三の居場所づくりも進めている。いずれも、教育委員会や学校と連携して取り組む必要があると認識している。
平賀 文化市民局文化芸術都市推進室長
現状、多くのカリキュラムの中で時間を捻出いただき、「ようこそアーティスト」という文化芸術授業を実施しており、様々な分野の大人との出会いの場にもなっている。現状、ニーズに応えきれない状況になっており、引き続き、本事業に注力していきたい。
現在、部活動の地域移行・地域展開について議論いただいている。今は運動部7割・文化部3割の比率だが、スポーツと文化の両方に触れられる仕組も検討されており、子どもたちに良い機会を提供できるよう努めたい。
結びに
稲田 教育長
京都市の教育は、かつて学力実態の厳しい時代があり、学力向上に向けた取組が現在実を結んでいる。一方、今は子どもたちが主体性や非認知能力を身につけることが重要。子どもたちが社会や学芸への興味関心が低いことは、社会構造や大人側に問題があると思う。大人がモデルとなることが求められる。
学校運営協議会を全ての学校園に設置しているが、地域の関わり方に差があるため、さらに充実させたい。図書館は、元々一部の知識人が独占していた知識を民衆に開放するために作られたものであり、本だけではなく、文芸など開かれた場所となることが求めれていると認識している。
松井 市長
子どもたちが多様な担い手による様々な体験を経験できる機会を作ることは大切。部活動地域移行は良いチャンスだと捉えている。先生と子どもたちの場である学校を、ある時間からは鍵の管理を任せて様々な大人が集うサードプレイスすることも考えられる。例えば、京都市役所の職員も含め、大人に学芸あふれる機会を提供し、公務員が率先して、自らの学芸を子どもたちに話をする場を提供できないか。その一例として、京都市のまちづくりや文芸の歴史を学ぶ勉強会もしていきたい。こうした活動を市役所ぐるみで支援したい。
ウェルビーイングに関する調査で、「人の役に立つ人間になりたい」と思う割合は高いが、「地域や社会を良くするために何かしてみたい」と思う割合が低いという結果であるが、それは子どもも何かをしたいが、地域や社会で素敵な取組を実践している大人に巡り合っていないのではないかと考えている。地域や社会でいろいろな物事を究めている人間が学校に出向いて、その姿を見せて子どものスイッチが入る機会を提供していきたい。
本市は、コミュニティスクールの先導地域であり、全国コミュニティスクール連絡協議会の会長を務めている稲田教育長の下、学校という場で、大人が学芸を子どもたちに共有する仕組みを作れないか。地域が学校を支えるだけではなく、学校を支えることが喜びになる活動を地域で広げるバージョン2.0のコミュニティスクールを作り、学校が地域や市民に良き影響を与え、子どもたちに共有するような知識・経験を持ち、それを深めていく場にしていきたい。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局総務部総務課
電話:075-222-3767
ファックス:075-256-0483