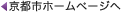【レポート】 令和3年度第2回総合教育会議(令和4年2月1日)
ページ番号295175
2022年2月28日
【テーマ】「様々なニーズに応じた多様な学びの実現について」
令和4年2月1日,「様々なニーズに応じた多様な学びの実現について」をテーマに令和3年度第2回京都市総合教育会議を開催しました。

会議での概要は以下のとおりです。また,会議全体の議事録は本ページ最下部の「会議の詳細はこちら」をご覧ください。
開会挨拶
門川 市長
本日の総合教育会議の全体テーマは「様々なニーズに応じた多様な学びの実現」です。この間,特別支援・不登校・困難な家庭環境など,子どもたちを取り巻く環境が複雑化・多様化していく中で,SDGsの理念である「誰一人取り残さない」教育を実現し,子どもたち一人一人のニーズに応じた学びの場を創ることが求められています。
子どもたちを取り巻く様々な環境の違いが,新たな学力格差や様々な体験の格差を生む結果となってはなりません。「一人一人の子どもを徹底的に大切にする」。本日は,この原点に立ち返り,様々なニーズに応える多様な学びの実現について,様々な視点から忌憚のないご意見をいただき,意見交換を行いたいと考えております。
意見交換「様々なニーズに応じた多様な学びの実現について」
笹岡 教育委員
北総合支援学校において視察を行った際,一般の小・中学校から総合支援学校に異動されてから,障害のある子どもたちへの学びの意欲が高まり,以降,総合支援学校に在籍しつづけたという教員がおられました。そうした事例があることも踏まえ,総合支援学校と他の校種との交流の機会を増やすことも進めていくべきではないかと感じています。
文化・芸術について,コロナ禍の影響で若手のアーティストが活躍する場が減ってきている中,ICTを活用して学校現場で,文化芸術について子どもたちに教えてあげられるような京都らしい授業ができないかと考えています。
野口 教育委員
科学技術が発展し,GIGAスクール構想をはじめとして,学校現場においても活用が進められる中で,技術的な部分が注目されがちですが,こうした取組は実際に使用する教職員等の技術や意欲があって初めて成立するものです。昨年12月に北総合支援学校を視察した際,教職員が意欲的にICTの活用等を進めている姿を見て,まさに,誰ひとり取り残さない教育を実践している学校であると感じました。
一方で,ICTの活用だけでなく,日々の授業準備や校務,保護者対応等によって,疲弊している教職員もいらっしゃいます。今後,こうした学校現場を,教育委員会としてサポートしていけるよう更なる検討が必要だと思います。
稲田 教育長
本市におけるGIGAスクール構想の推進にあたっては,ICT化自体が目的ではなく,文房具と同じような1つの手段として活用を進めています。これまで各教職員が培ってきた授業実践を,ICTの活用によってさらに深めていけるよう,教育委員会としてもサポートしていきたいと考えております。
奥野 教育委員
北総合支援学校は10年前にも視察した時と比べると,児童生徒の数がかなり増えている印象を受けましたが,そうした状況においても,「一人一人の子どもたちを徹底的に大切にする」という本市の教育理念のもと,教育を実践されていました。小・中学校等の普通学級では,1人の教員が担任する児童生徒数が多いため,総合支援学校と同じ水準で,子どもたち1人1人のニーズに対してきめ細かな対応を行うことは難しいとは思いますが,総合支援学校での実践を普通学級にも落とし込むことで,よい効果が得られると思います。
コロナ禍において,子どもたちの体力低下が著しくなっています。体の発育のために,学校での授業や部活動とは別に,外で走ったり遊んだりすることは大切ですが,今の子どもたちはコロナの影響でそれができません。こうした状況においては,ICTを活用しながら,体力向上のための取組を進めるべきだと思います。
高乗教育委員
19世紀のイギリスで公教育の制度が確立されていく中では,教育の質の担保と同時に,効率的な教育について議論されました。今回のテーマに掲げられているような,1人1人のニーズに応じた教育は,いわばオーダーメイドの教育であり財政的な負担も大きいですが,本市も厳しい財政状況の中で,こうしたテーマを選んで意見交換を行うことは,非常に有意義であると思います。
総合支援学校以外の校種においても,どのように多様な学びを実践するかについても,大きな課題かと思います。本市においては,開建高等学校の開校や銅駝美術工芸高校の移転などを契機に,新しい教育のデザインが構想され,実践が始まろうとしています。こうした取組は成果が出るまで時間を要するものなので,粘り強く対応していただきたいと思います。
松山 教育委員
新型コロナが収束した後の生活の在り方をどう戻すのかが,大きな課題であると思います。現在の子どもたちは,常にマスクを着用し,筆記具等を使うたびに消毒するなど,新型コロナ対策をするのが当たり前になっていますが,コロナが収束し,突然にマスクや消毒がいらないといわれたときに,特にコミュニケーションの取り方について,コロナ前の状態に戻すことは難しいと思います。いつかコロナが収束したときを見据えて,現段階から全市的に研究していくべきだと思います。
前回の総合教育会議でも話しましたが,コロナ禍で,心の火が消えている子どもたちが多くいます。現在の学校教育現場では,日頃の授業や校務が多忙なため,児童生徒の心に火をつけるために時間を割くことができていない教員も多くいます。そうした状況において,例えば,有名な学者やプロスポーツ選手等,子どもたちが興味関心を持つような人物に,オンラインで特別な講義を行ってもらうことはできないでしょうか。そうした講義をきっかけに,子どもたちが希望を持ち,心に火をつけることができると思います。門川 市長
様々な分野で活躍する人に学校で授業を行ってもらうことは良い取組だと思います。
以前,ある市立高校に全盲の生徒が入学されました。学校は,声を出して板書を行うなど,その生徒の学力保障に取り組んだ結果,その学年の全体の進学率が上がったといいます。困りを抱える生徒に焦点を当てることで,周りの生徒にも効果が波及します。
吉田 副市長
保育園での受入れには様々な課題があるものの,医療的ケアが必要となる子どもや保護者にとって,保育園への入園が初めての集団参加になることが多く,保育園を卒園した後に,総合支援学校等に入学して学ぶことで,子ども本人の学びの保障になるだけではなく,その周りの子どもたちにいい影響を与えていきます。
ヤングケアラーについては,大きく2つの課題があります。1つは,子どもたち本人のメンタルケアや学習保障といったヤングケアラー個人に対する支援をどのように行うかという課題,もう1つは,ヤングケアラーがいる世帯と福祉サービスをどのようにつなげていくかという課題す。こうした問題を解消するには,学校現場の教職員が窓口になることが多いですが,教職員のみに負担がかからないよう,重層的な相談体制の構築や,地域・NPOとの連携など,社会全体でのフォローアップ体制を整備していく必要があります。
奥井 総合政策室長
総合企画局においては,「デジタル化・情報化」,「大学政策」,「国際交流・共生推進」など,幅広い行政分野で教育機関と連携が求められます。特にデジタル化については,令和3年12月に「京都市DX推進のための基本方針」を策定しており,我々も大切にしていることは「誰一人取り残さない,人に優しいデジタル社会の形成」であり,全世代の市民の皆様にとって,使い勝手の良いデジタル社会を目指しております。
上田 はぐくみ創造推進室長
子ども若者はぐくみ局は,主に福祉や保健等の観点から子どもや家庭と関わっているが,本日の意見交換を聞かせていただき,改めて,学校教育との強い繋がりを感じました。
子どもが何かをやりたい,何かを学びたいと思える気持ちを持つことができるような環境づくりは重要であり,子ども若者はぐくみ局としても,保健や福祉分野からのアプローチや地域で子どもを育てるための活動によって,引き続き,その環境づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
結びに
稲田 教育長
本日,本市の教育に関する大綱に,京都市基本計画を位置付けることを確認いただきました。
ICT活用は,教育の可能性が広がっていくことと合わせて,コミュニケーション力の欠如や健康面等の危険性もあることを踏まえつつ,多様な子どもたちの可能性を広げる1つのツールとして,引き続き,拡充を努めてまいります。
コロナ禍においては,体験的な学習や人と人とのつながりが大事になっており,ウィズコロナ時代は,いわばウィズヒューマンとウィズICTで,よりよい教育環境の整備に努めてまいります。
門川 市長
京都の教育は,長い歴史と伝統を積み重ね,まち全体で子どもを育むという文化の根付きと教育委員会,学校現場の教職員による教育実践で成り立っております。このコロナ禍,1年半続いていく中で,まだ明確な見通しが立てられていない中,この総合教育会議において,今後の子どもたちの学びの在り方,とりわけICTについて議論ができたことは,有意義に感じております。
現在,コロナ禍において,本市は多くの課題を抱えています。1つはワクチン接種や3つの密の回避といった医学的な課題,もう1つは市民の不安解消等の心の課題です。毎日,コロナの陽性者や死亡者の数が報じられ,そうした中で,命の尊さと向き合っている毎日です。このような状況で学び過ごす,現在の子どもたちがつくる未来を輝かしいものとするためにも,コロナ禍を経てどのような大人になるのか,それを本市全体で子どもたちの心を支援していきたいと考えております。社会的な課題として,コロナの影響で更なる格差を生じさせてはならない。1人1人を大事にする,誰一人取り残さない取組みを進めてまいります。
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局総務部総務課
電話:075-222-3767
ファックス:075-256-0483