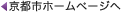参考資料
ページ番号6515
2008年2月12日
【 参 考 資 料 】
1 設置要綱
京都市道徳教育振興市民会議設置要綱
(趣旨及び設置)
第1条 本市における道徳教育の一層の振興を図るため,市民とのパートナーシップの下,幅広い観点から研究・検討を行い,提言することを目的にして,「京都市道徳教育振興市民会議」(以下「道徳会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 道徳会議は,15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は,3名の委員は公募により選出した者を,その他は,次の各号に掲げる者のうちから,京都市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱し,又は任命する。
(1)学職経験者
(2)教育関係者
(3)行政機関関係者
(4)その他教育長が必要と認める者
3 必要に応じ道徳会議に専門員をおくことができる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は,平成13年8月20日から平成16年9月30日までとする。
(座長及び副座長)
第4条 道徳会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は,委員の互選により選出し,副座長は,委員のうちから座長が指名する。
3 座長は道徳会議を主宰する。
4 副座長は,座長を補佐し,座長に事故あるときは,その職務を代理する。
(庶務)
第5条 道徳会議の庶務は,京都市教育委員会事務局において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,道徳会議の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成13年8月20日に施行する。
附 則
この要綱は,平成15年4月1日に施行する。
附 則
この要綱は,平成16年4月1日に施行する。
河合 隼雄 小寺 正一 牛尾 誠三 正木 隆之 小野山正彦 梶 寿美子 高田 道弘 中井 隆栄 永田 萠 中野 悦子 橋本三千代 藤本奈々子 リベッカ・ティール 高桑 三男 | 文化庁長官(名誉座長・平成14年1月まで座長) 京都教育大学理事・副学長(座長,平成14年1月まで副座長) 元中学校長・中学校道徳研究会前会長(平成15年2月から副座長) (財)京都ユースホステル協会事務局長・ 人づくり21世紀委員会前副幹事長(平成15年2月から副座長) 京都新聞社論説委員 市民公募委員 市民公募委員 (社)京都青年会議所2002年度理事長 イラストレーター 元京都市中学校PTA連絡協議会副会長 市民公募委員 元京都市小学校PTA連絡協議会副会長 能楽金剛流師範 京都市教育委員会教育次長(平成15年4月から委員) |
皆藤 章 迫田 敏暉 | 京都大学大学院教育学研究科助教授(平成14年1月から副座長,平成15年3月まで委員) 京都市教育委員会前教育次長(平成15年3月まで委員) |
3 活動経過
平成13年8月20日(月) 第1回会議 ・・・ 於 : こどもみらい館
平成13年10月9日(火) 第2回会議 ・・・ 於 : キャンパスプラザ京都
作業部会
平成13年11月13日(火) ・・・ 市民アンケート予備調査実施
~11月28日(水)
平成13年12月13日(木) 第3回会議 ・・・ 於 : キャンパスプラザ京都
平成14年 1月18日(金) 学校視察 ・・・ 於 : 京都市立陶化中学校
平成14年 1月30日(水) 学校視察 ・・・ 於 : 京都市立岡崎中学校
平成14年 2月 6日(水) 学校視察 ・・・ 於 : 京都市立乾隆小学校
平成14年 2月 7日(木) 学校視察 ・・・ 於 : 京都市立西陣中央小学校
平成14年 2月14日(木) 第4回会議 ・・・ 於 : こどもみらい館
平成14年 3月 8日(金) 第5回会議 ・・・ 於 : こどもみらい館
平成14年 4月26日(金) 作業部会
平成14年 5月24日(金) 第6回会議 ・・・ 於 : 京都市生涯学習総合センター
平成14年 6月 3日(月) 作業部会
平成14年6月25日(火) ・・・ 道徳教育市民アンケートの実施
~7月25日(木) <回答:22,327人>
平成14年 6月28日(金) 学校視察 ・・・ 河合隼雄名誉座長による「心のノート」を使った道徳授業
平成14年 7月 5日(金) 第7回会議 ・・・ 於 : こどもみらい館
平成14年9月12日(木) 作業部会
平成14年 9月17日(火) 第8回会議 ・・・ 於 : キャンパスプラザ京都
平成14年10月11日(金) 作業部会
平成14年10月30日(水) 作業部会
平成14年11月 8日(金) 第9回会議 ・・・ 於 : キャンパスプラザ京都
平成14年12月2日(月) 作業部会
平成14年12月 6日(金) 第10回会議 ・・・ 於 : こどもみらい館
平成15年 1月10日(金) 第11回会議 ・・・ 於 : キャンパスプラザ京都
平成15年 2月 4日(火) 第12回会議 ・・・ 於 : 京都市生涯学習総合センター
平成15年 2月13日(木) 作業部会
平成15年 2月22日(土) ・・・ 京都市道徳教育フォーラム
於 : 京都市総合教育センター
・基調講演(河合名誉座長)
・シンポジウム(パネリスト:小寺座長,正木副座長,永田委員,柴原文科省調査官)
平成15年 5月 2日(金) 作業部会
平成15年 5月28日(水) 作業部会
平成15年 8月26日(火) ・・・ 地域教育フォーラム・イン京都「道徳教育分科会」
於 : 国立京都国際会館
平成15年 8月28日(木) 作業部会
平成15年 9月18日(木) 作業部会
平成15年 9月24日(水) 作業部会
平成15年11月 7日(金) 学校視察
平成15年11月21日(金) 学校視察
平成15年11月28日(金) 学校視察
平成15年11月29日(土) ・・・[京都市PTAフェスティバル]
於 : 国立京都国際会館
取組情報発信
平成15年12月14日(日) ・・・[人づくりフォーラム] 於 : みやこめっせ
取組情報発信
平成16年 1月23日(金) 作業部会
平成16年 2月24日(火) 作業部会
平成16年 3月10日(水) 第13回会議 ・・・ 於 : 京都市生涯学習総合センター
平成16年 3月23日(火) 第14回会議 ・・・ 中間報告案のとりまとめ
平成16年 4月 1日(木) ・・・ 市民意見(パブリックコメント)の募集
~4月30日(金) <回答:209件>
平成16年 5月28日(金) 作業部会
平成16年 6月21日(月) 作業部会
平成16年 6月30日(水) 第15回会議 ・・・ 於 : 京都市教育委員会教育委員室
平成16年 7月14日(水) メッセージ提出
4 市民アンケート調査概要
道徳教育について論議を進める上で,日常生活の中で大人や子どもが何を大切に考え,実際にどう行動しているのかを把握するために,市民アンケート「毎日の生活でのことについて」を実施しました。平成13年11月に実施した予備(* )調査の結果もふまえ,できるだけ建前ではない本音の回答が得られるよう,日常生活でのことについて具体的な例を挙げて聞くこととし,意識と行動の両面にわたって質問項目の作成を行いました(大人88項目,子ども66項目)。
また,特設項目として「尊敬する人」「子どもに育てたいもの」「家庭と学校の役割」 についての3つの質問項目を設定しました。
*予備調査
・406人(小学校6年生59人,中学校1~3年生104人,高校生69人,大人(大学生を含む)174人)に,「あなたが毎日の生活の中で,人間として大切にしていることはどんなことでしょうか?思いつくことを10個まであげてください。」と自由記述の形で尋ねました。
▼ 22,327人の方から回答をいただきました。
アンケートは平成14年6月25日から7月25日までの1か月間にわたって実施しました。大人については,市内各施設に質問・回答用紙を備え,また各種団体を通して配布し,自由に回答いただく形をとり,子どもは,小学校5年生から高校3年生までの児童・生徒を対象に学校を通じて実施しました。当初,1万人調査という形でスタートしましたが,調査票の回収結果は22,327人(大人12,822人,児童生徒9,505人)と2万人を超え,大人用の調査票に設けた自由記述欄には3,971名,31.0%もの方々が記入されるなど,関心の高さを改めて感じさせられました。
大人の回収状況を見ると,現在,直接子育てや教育にかかわっている女性の割合が高くなっています。家庭における教育,子育ての状況の一側面を反映していると言えるのかもしれません。
区 分 | 男 性 | 女 性 | 不 明 | 合 計 |
大 人 | 1,863(14.5%) | 10,943(85.3%) | 16(0.1%) | 12,822(100.0%) |
児童・生徒 | 4,877(51.3%) | 4,620(48.6%) | 8(0.1%) | 9,505(100.0%) |
▼ アンケート結果の特徴的な点をいくつかご紹介します。
(1) 大人の考え方について尋ねる36の質問項目(回答は,5つの選択肢の中から1つを選択)のすべての項目において,「かならずそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」と肯定的に考えている人の割合が50%を超えており,80%以上の高い割合の項目が26項目となっています。
今日,価値観の多様化が言われますが,今回の調査項目についてみると,大人において,そうするべきだと肯定的に考えている人の割合がかなり高い様子がうかがえます。(P.26参照)
(2) 大人と子どもに共通して意識と行動の両面について尋ねる28の質問項目について分析すると,おおむね,次の3つの類型に分類することができました。(P.27,28参照)
① 大人も子どもも,多くがそうするべきだと考えている項目(13項目)
「いつもそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」と答えた人の割合が大人も子どもも80%以上の高い割合になっています。また,「いつもそうしている」「どちらかと言えばそうしている」と答えた人の割合は,全体として,いつもそうするべきだ,そうするべきだと考えている人の割合を下回る傾向が見られますが,次の4つの項目は,意識においても行動においても極めて高い割合になっています。
「人に親切にされた時,感謝の言葉を言う」
「近所の人に会ったとき,あいさつをする」
「他人の自転車に勝手に乗らない」
「暴力で人を従わせ,問題を解決しない」
② 大人の多くがそうするべきと考えているが,子どもの考え方ではそれほどではない項目(7項目)
③ 大人も子どもも比較的多様な考え方が見られる項目(8項目)
(3) 上記(2)の28項目について,意識と行動の関係を見ると,行動の「いつもそうしている」「どちらかとい言えばそうしている」の割合が意識の「必ずそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」の割合を下回る項目が多く,また,その差は子どものほうが大人より大きい傾向がみられます。
大人も子どもも行動の割合が意識の割合を20ポイント以上下回り,意識と行動のギャップが大きい項目は,次の5項目となっています。もとより,子どもは成長過程の存在であること,大人と子どもの調査実施方法に違いがあることなども考慮に入れておく必要があります。
「京都の町を美しくするため積極的に取り組む」
「ボランティア活動に参加する」
「混雑している電車やバスの中で,携帯電話の電源を切る」
「京都の文化財や伝統行事を大切に守るようにする」
「傷ついて飛べない小鳥を見つけた時,たすけようとする」
(4) 大人への「子どもたちに育てたいものは何ですか」という質問への回答には,「思いやりや優しさ」(78.2%)が最も多く「夢や希望,目標を持ち努力する心」(62.4%) 「誠実で素直な心」(54.9%)が続きました。「思いやりや優しさ」は,私たちの考える「共に生きるための知恵としての道徳」の中心的な役割を担うものでもあります。

(5) 「子どもに身につけさせるために,家庭と学校の役割はそれぞれどの程度重要だと思いますか」という質問に対し,「非常に重要である」との回答の割合が最も高い項目は家庭,学校ともに「命を大切にする」で,家庭で87.0%,学校で82.8%となっています。

このアンケートの実施に際し,様々なご意見を市民会議にいただきました。私たち,市民会議委員の一人一人はアンケートの結果はもとより,そうした様々なご意見もふまえて,論議を積み重ねてきました。
そして,何より,アンケートの実施が,道徳教育について多くの方々に関心を持っていただく上で一つの契機となったことは大変有意義だったと考えています。今後,アンケートの結果も活用していただき,家庭で,地域で,学校で一層論議が深まり,子どもたちの育ちに生かされることを願っています。
区 分 質 問 項 目 |
意 識 |
行 動 | ||
大 人 | 子ども |
大 人 |
子ども | |
人に親切にされた時,感謝の言葉を言う | 99.5 | 97.0 | 99.5 | 94.2 |
☆子どもにあいさつの習慣を身につけさせる | 99.2 | 98.1 | ||
道路や公園に空き缶などを捨てない | 99.0 | 83.3 | 96.2 | 68.8 |
☆子どもに自然とふれあう体験の機会を与える | 98.4 | 80.2 | 69.2 | |
他人の自転車に勝手に乗らない | 98.3 | 84.7 | 98.6 | 88.3 |
近所の人に会った時,あいさつをする | 98.2 | 89.3 | 98.7 | 82.6 |
☆日常の親子の会話を積極的にする | 97.3 | 76.7 | 95.0 | 74.9 |
家族と過ごす時間を大切にする | 97.2 | 82.3 | 92.6 | 70.8 |
人生に夢や目標をもつ | 97.2 | 89.3 | 74.1 | 80.7 |
混み合っている電車やバスの中で,お年寄りや障害のある人に席をゆずる | 97.0 | 89.3 | 88.0 | 56.5 |
☆子育てに関して父親も積極的に役割を果たす | 96.3 | 76.6 | ||
学校や社会のルールをまもる | 96.1 | 78.9 | 96.6 | 68.7 |
☆子どもに朝食を食べさせるようにする | 95.0 | 98.0 | ||
朝食を食べる | 95.0 | 90.0 | 72.1 | 71.9 |
暴力で人を従わせ,問題を解決しない | 94.6 | 84.3 | 88.7 | 80.5 |
年上の人に敬語で話す | 94.5 | 68.4 | 96.8 | 61.5 |
自分の夢を実現するために努力や辛抱をする | 93.8 | 83.5 | 74.5 | 64.9 |
☆子どもに家事の役割分担をさせる | 91.4 | 76.2 | 63.3 | |
友達や知り合いの人がいじめや嫌がらせをされている時,助ける | 90.6 | 83.9 | 76.2 | 59.7 |
☆子どもに喫煙させないようにする | 90.1 | 91.4 | ||
先祖のお墓まいりに行くようにする | 89.4 | 89.0 | 82.7 | 77.3 |
混雑している電車やバスの中で,携帯電話の電源を切る | 88.4 | 65.0 | 62.6 | 27.5 |
京都の文化財や伝統行事を守る | 87.6 | 79.6 | 64.7 | 50.9 |
京都の町を美しくするため積極的に取り組む | 87.1 | 70.8 | 43.7 | 36.1 |
子どもたちに伝統行事などを伝えようとする | 83.6 | 63.9 | 67.8 | 57.6 |
傷ついて飛べない小鳥の命を助ける | 80.2 | 81.1 | 56.9 | 56.2 |
☆子どもにテレビやビデオで殺人などの残虐なシーンを見せないようにする | 76.7 | 73.1 | 25.3 | |
観光で京都に訪れた人に対して,積極的に親切に接する | 73.0 | 53.7 | 56.2 | 36.0 |
☆小中学生がテレビやビデオで性的描写の激しい場面を見ない | 72.8 | 57.4 | 80.3 | 71.9 |
☆小中学生が髪の毛を染めない | 71.8 | 37.4 | 83.9 | 84.3 |
自分の国を愛する | 70.0 | 52.4 | 68.6 | 48.9 |
食事を食べ残さない | 68.7 | 58.0 | 65.2 | 39.8 |
地域の行事や会合に参加する | 63.7 | 47.7 | 80.1 | 53.0 |
よくないことをしている近所の中高生を見つけた時,注意する | 61.0 | 28.3 | ||
ボランティア活動に参加する | 60.9 | 61.2 | 35.5 | 28.3 |
歩きながらものを食べない | 57.0 | 28.6 | 68.4 | 24.8 |
☆ 行動の結果は,大人は小中学生の保護者,児童・生徒は小中学生のみ
(注)「意識」は,「かならずそうするべきだと思う」と「そうするべきだと思う」(設問によって「絶対にそうするべきでないと思う」・「そうするべきでないと思う」,「絶対必要だと思う」・「必要だと思う」)を合わせた人の割合
「行動」は,「いつもそうしている」と「どちらかといえばそうしている」(設問によって「よくある」・「ときどきある」,「はっきりとした夢や目標を持っている」・「はっきりとしていないが夢や目標を持っている」)を合わせた人の割合
【大人と児童生徒の意識と行動に共通する28項目のカテゴリー分類】
(1) 大人も子どもも,多くがそうするべきと考えている項目
(「かならずそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」が,大人も児童生徒も80%以上)
「人に親切にされた時,感謝の言葉を言う」(*)
「近所の人に会ったとき,あいさつをする」(*)
「他人の自転車に勝手に乗らない」(*)
「暴力で人を従わせ,問題を解決しない」(*)
「道路や公園に空き缶などを捨てない」
「家族と過ごす時間を大切にする」
「混み合っている電車やバスの中で,お年寄りや障害のある人に席をゆずる」
「友達や知り合いの人がいじめや嫌がらせをされている時,助ける」
「先祖のお墓参りに行くようにする」
「人生に夢や目標を持つ」
「朝食を食べる」
「自分の夢を実現するために努力や辛抱をする」
「傷ついて飛べない小鳥の命を助ける」
(*)印は,いつもそうしている」「どちらかといえばそうしている」が大人も児童生徒も80%以上の項目
(2) 大人の多くがそうするべきと考えているが,子どもの意識はそれほどではない項目
(「かならずそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」が,大人80%以上,児童生徒80%未満)
「日常の親子の会話を積極的にする」
「学校や社会のルールを守る」
「京都の文化財や伝統行事を守る」
「年上の人に敬語で話す」
「混雑している電車やバスの中で,携帯電話の電源を切る」
「京都の町を美しくするため積極的に取り組む」
「子どもたちに伝統行事などを伝えようとする」
(3) 大人も子どもも比較的多様な考え方がある項目
(「かならずそうするべきだと思う」「そうするべきだと思う」が,大人,児童生徒ともに80%未満)
「小中学生が髪の毛を染めない」
「観光で京都に訪れた人に対して,積極的に親切に接する」
「小中学生がテレビやビデオで性的描写の激しい場面を見ない」
「自分の国を愛する」
「食事を食べ残さない」
「地域の行事や会合に参加する」
「ボランティア活動に参加する」
「歩きながらものを食べない」
5 中間報告案に対する市民意見の概要
メッセージをまとめるにあたり,中間報告に対し市民の皆様からご意見・ご感想をお聞きするため,4月1日~30日までの期間,市民意見募集(パブリックコメント)を行ったところ,下記のとおり,209件(うち,文書が全く同じもの45件)もの回答をいただきました。お寄せいただいたご意見・ご感想は,メッセージに反映させていただくとともに,そのすべてを別紙にまとめて掲載しています。
(1) 応募総件数 209件(うち,文書が全く同じもの45件)
(2) 応募男女別 男性 54件(25.8%) 女性 153件(73.2%)
連名 1件( 0.5%) 不明 1件( 0.5%)
(3) 応募年代別 20代 2件( 1.0%) 30代 12件( 5.7%)
40代 21件(10.0%) 50代 30件(14.4%)
60代 54件(25.8%) 70代 27件(12.9%)
80代 4件( 1.9%) 不明 59件(28.2%)
(4) 応募方法別 郵送(直接も含む) 198件 FAX 9件 Eメール 2件
(5) 内容別(意見内容は一部抜粋/2項目以上にまたがる意見については,各項目ごとに積算しており,各項目の合計数と総意見数とは合致しません。)
①「基本的な考え方」に関わるもの(46件)
・物が豊かになる一方で,便利さと引き換えに心の貧しさが目立つようになり,人と人とのつながりが希薄になっているのが現状です。お互いが認め合い,関わり合い,支えあい,高め合う人間同士のつながりを高める取組が21世紀を担う子どもたちに大切である。 (伏見区・男性)
・自分たちが今この時代に生きて存在することの大事さ,父母や祖父母がいて,その昔から連綿と続く祖先のお陰で,今あることを尊く思う気持ちが大事だと思います。今,生活の中にそのような心が希薄になっています。その回復こそが,モラルの回復であり,社会性の向上であり,道徳教育のあるべき基本のように感じます。 (南区・男性)
②「しなやかな道徳教育」推進に向けてに関わるもの(119件)
・家庭の中では親,外に出たら近所のおじちゃん,おばちゃん,学校では先生等によって,事の善悪を分からせることができたら一番だと思います。難しく考えるより,まず身近なところから始めたいと思います。良いことは良い,悪いことは悪いと言えるようになりたい。 (伏見区・女性)
・「これだけは守らなければならないこと」があり,人生の先輩として大人が子どもたちに見られて恥ずかしくない行動や言動を常に心がけていかなければならないと思います。 (右京区・女性)
・今の同世代の人を見ていると,同じ年代ながら「これでいいのか」という場面もあります。大人の方も自信を持って,我々にブチ当たってくる人がほとんどありません。一人一人が評論家になったり,無関心を決め込むのではなく,一歩でもやれることをやっていくことが必要だと思います。 (右京区・男性)
③「家庭で,どうトク?」アクションに関わるもの(87件)
◆家庭こそが,どうトク?の出発点
・子どもにとっても大人にとっても,自分自身を反省したり高めたりする場は家庭内です。明るく楽しく何でも話し合えるところ,その中で社会のルール,人への思いやり,あいさつ,辛抱することなどを学び,また,悩みを解決するのです。 (伏見区・女性)
・親から子,子から孫へ家庭での道徳教育が大きな影響力を持つと思います。 (伏見区・女性)
・社会にもルールがあるように家庭にもルールがあります。毎日の挨拶,おはよう,行ってきます,ただいまから始まります。 (中京区・女性)
◆子どもに家事の分担を
・子どもが何を考え,何をしようとしているのかを見守りながら,親は常に大きな存在であってほしい。家庭こそが子どもたちにとって最高の安らぎの場であり,心を開ける場所であるべきです。 (右京区・女性)
◆親も子も育つ“共育”を
・大人も子どもの背の高さに立って,話をできると良いのではないかと考えます。一人の人間として大人も子どもも対等ですから。 (伏見区・女性)
・大人である我々も子どもに尊敬される大人になるために,子どもに一方的に意見を言うのではなく,自分自身も社会人として誇りを持てる言動を行うようにしなければなりません。 (伏見区・女性)
・生活習慣やルールをしっかりと身に付け,人の命の尊さや大切さを今一度考えられる大人でありたいと思います。そのことを子どもたちに自信を持って教えていきたいと思います。 (右京区・女性)
・大人も共に学べる学習会が必要かと思います。(伏見区・女性)
・子どもは親を見て育つもの。子は親の鏡だと思います。子どもを育てている大人たちもまた子どもに育てられているのです。 (伏見区・女性)
◆やっぱり子どもは親の背中を見ています
・子どもたちの目に映る大人の姿が自然なかたちで優しかったり,夢や希望を持って生きていれば,子どもたちもがんばって力強く育ってくれるのではないでしょうか。 (南区・男性)
・真心の一言を言ってあげるかどうかである。言うべきときの「一言」が人生を変えることさえある。心が揺れ動く子どもたちに進む道をしめしてくれる存在がどれほどありがたいものか,人間の心を動かすのは「真心」「誠実」だけだと思います。教育者たちがどう子どもたちを励ましていくかが大切!
(伏見区・女性)
・“自分ぐらい”“少しくらい”という気持ちでする行動を,小さな瞳が見つめていることを忘れてほしくないと思います。子どもの手本になれるように,行動したいと思っています。 (北区・女性)
◆父親も子育てに参加しよう
・父親も参加を願って,道徳教育の大切さを親自身に教育する場を設けていただき,子育ての大切さを学んでほしいと思います。 (右京区・女性)
④「地域で,どうトク?」アクションに関わるもの(40件)
◆人づくりの風土を生かして
・家の前を通学する子どもに,声をかけるようにしています。知らぬ顔をしていた子どもたちも,その内に挨拶し,語りかけてくれる子どももいます。地域が一体となって声をかけ,見守る必要を感じます。
(伏見区・女性)
・今は開かれた学校などへ地域の者が出向き,子どもと共に学ぶ時代になってきているようですね。大人の中にも道徳心を忘れ,自分さえ良ければの人が多くなり,子どもに悪いですね。 (右京区・女性)
・私の町内の地蔵盆は,若いお母さんたちが色々と企画をたて,ともに楽しみながらつくられています。幼児から高学年の子まで年齢を超えて遊び,また,親も色々なことを相談しあえることは良いことだと見守っています。 (中京区・女性)
◆地域行事にみんなで参画
・地域の清掃やゴミの分別など,習慣付けて子どもも大人も一緒に参加したらどうでしょう。体験を通して,人との出会いや行為を見て学ぶところは大きいと思います。 (伏見区・女性)
・「ゴミを捨ててはいけない」と言葉で伝えても,なかなか実行するのは難しいですが,川掃除に参加する子どもたちは「きれいな川にゴミを捨ててはいけない」ということを身をもって経験するのではないでしょうか。 (伏見区・女性)
◆学校へ出かけよう
・子育てを終え,子どもと関わることもなくなった大人がもっと学校などへ行き,子どもとの関わりをもっていきたいと,昔遊びを教えに学校に行きました。楽しい時を過ごし,子どもも楽しかったと手紙を書いてくれた。とてもうれしかった。 (中京区・女性)
・保護者がもっと道徳教育に関心を持つ必要がある。道徳の授業への積極的な参加を学校は呼びかけ,保護者もそれに応え,教師と共に進んでいければと思う。
(伏見区・女性)
⑤「学校で,どうトク?」アクションに関わるもの(29件)
◆道徳教育のさらなる充実を
・道徳が忘れられた今,急に取り戻すことは至難なことと思いますが,大人一人一人が自覚して地域で,また,学校教育でも力を入れられ,思いやりのある優しい心を大人も子どもも取り戻し,豊かな心で住み良い明るい地域をみんなでつくっていきましょう。
(右京区・女性)
・道徳の時間に計画的に色々な価値に目を向けさせることは大変重要だと思います。道徳の時間に色々な価値について話し合っておくと,日常生活の場において,「これ道徳の時間に話し合ったことや」と言いながら,問題解決をしている姿がたびたび見られます。
(左京区・女性)
◆子どもと向き合って
・今,学校の先生でも挨拶をしない人がいる。学校外で会っても挨拶するどころか顔をそらすような人もいる。子どもの手本となる人が挨拶もできないなんて。指導する立場の人を教育してほしい。道徳の時間を設定しなくても,日常が道徳です。大人が見本を示せばわかる。 (右京区・女性)
・道徳教育を考えるには大人の生き方を問題にすべきです。心から信頼できる親,教師など,子どもを取り巻く大人の姿勢を正すべきです。 (伏見区・女性)
◆道徳教育の情報発信を
・子どもに学校の先生を尊敬する気持ちを持つことが大切であることを教えていくことも必要と思います。そして,教育委員会が学校へ道徳教育の充実を具体的事例とともに発信されることが必要です。 (伏見区・男性)
⑥提言全体に関わるもの(60件/うち,文書が全く同じもの45件)
・もっと人間として心を揺さぶるものがあれば,そんな言葉がでてくるかと期待していました。生命の大切さをもっと厳しく伝えるものがあってほしいです。 (伏見区・女性)
・本当に「命は大事」とか「人を尊重しよう」とか思っているならば,ぜんぜん「命の尊さ」を実感できない社会を,ぜんぜん「人が尊重されていない」学校を,まず変えてほしい。それがないところでの「道徳」なんて言葉は薄っぺらだ。 (左京区・女性)
・もっと具体的な事象に対して,具体的に書いてある方が,響くものがあるのではないかと思います。冊子を読んで一番わかりやすくていろいろ共感できたところがアンケートでの声のコラムでした。
(上京区・男性)
・中間報告案の「どうトク?」アクションが家庭,地域,学校で具体的に行動として起こるようにするための取組について,今後の会議の中で具体化することを期待します。また,すばらしい提言が市民に広く知っていただくような方策も考えていただいたらと思います。 (左京区・男性)
・教育行政は,決して人々の内心,思想,信条に立ち入ってはいけないし,いかなる組織も機関も,人の感情を支配,コントロール,命令はできないという自覚を持っていただきたい。その点において,今回の<中間報告>は,教育基本法を逸脱する不届き至極な行為であり,即刻,撤回していただきたい。
(伏見区・女性)
・心の持ち方を教え込もうというのは教育とは言えないのです。 (宇治市・男性)
⑦その他(8件)
・昔のような競争社会がどこかで必要なのではないでしょうか?今は競争社会から生まれてくるひたむきな真剣な時が失われてきていて,若者があり余る力をぶつける場がなくなり,それがいろんな問題をひき起こしている様に思います。 (不明・女性)
・心よりしなやかな道徳教育が実行され,人々の争いがない様に,みんなが幸せでいられるような,地域や社会づくりをして下さいと願っています。 (伏見区・女性)
お問い合わせ先
京都市 教育委員会事務局指導部学校指導課
電話:075-222-3815
ファックス:075-231-3117