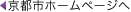第5回「幻の伏見区横断鉄道(戦前の鉄道計画)」(最終回)
ページ番号304212
2022年9月22日
第5回「幻の伏見区横断鉄道(戦前の鉄道計画)」(最終回)
昭和初期、阪急京都線の前身である新京阪線を建設した、戦前の京阪電鉄は次なる一手として、滋賀県から鈴鹿山脈を越えて名古屋へ至る名阪連絡の電鉄構想を具体化させました。この壮大な計画の一部を担うための計画線が京阪六地蔵線と新京阪山科線でした。
六地蔵線は京阪宇治線六地蔵付近から分岐し、奈良街道西側を石田、醍醐、山科と進み、逢坂山をトンネルで抜けて大津市の膳所付近に達し、ここから名古屋への計画線に乗り入れる予定でした。実現していれば、中書島経由の名古屋ルートが拓かれていたのです。
一方、山科線は新京阪線からのアクセスとして、現在の阪急西向日駅から分岐して伏見区北部を横断します。久我の田園地帯を一直線に進み、最初の駅が「上久我」(旧・神川出張所あたり)。続いて久我橋・京川橋の南で桂川・鴨川を渡り、赤池を通って、パルスプラザあたりに「城南宮前」。そして、七瀬川沿いを進み、今の深草支所の西手に「深草」。ここからは大岩街道に並行して峠を越えて「勧修寺」、山科盆地を横断して、山科大宅で六地蔵線に接続します。二つの計画が実現していれば、神川地域と深草地域が10分程度で移動できたり、列車ダイヤによりますが、中書島から乗り換えなしで醍醐まで行けたりする可能性もありました。しかし、昭和恐慌が直撃し、伏見区を横断する名阪連絡の鉄道計画は幻となります。
伏見区の歴史を振り返ると夢のまた夢に終わったことも数多くあります。歴史と向き合う時、過去を変えることはできません。しかし、歴史を教訓とすることで、未来への糧にすることはできます。この連載を通じて、伏見区の歴史へのみなさんの向き合い方が深まったのならば幸いです。

昭和初期(1930年代)の鉄道計画
(京都府行政文書より筆者作成)
関連コンテンツ
伏見区誕生90周年記念歴史コラム!(全5回)
- 第1回「多様性の歴史」
- 第2回「看聞日記(かんもんにっき)の時代」
- 第3回「徳川の伏見城」
- 第4回「水運の伏見(熊野詣から疏水まで)」
- 第5回「幻の伏見区横断鉄道(戦前の鉄道計画)」(最終回)
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-611-1295、事業担当・広聴担当・振興担当:075-611-1144
ファックス:075-611-0634