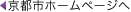第1回「多様性の歴史」
ページ番号303887
2022年9月22日
第1回「多様性の歴史」
伏見区が誕生した90年前、区の南には芦ノ湖ほどの面積の巨椋池があり、深草を中心に陸軍第16師団の軍用地が点在し、醍醐には街道と田園風景が広がっていました。三栖閘門が完成し、ここを大阪との蒸気船が通るようになったのもこの頃です。
しかし、景観は移ろい、巨椋池は干拓され農地に、軍用地は住宅地や大学に姿を変えました。水運の衰退により三栖閘門も役割を終えました。田園地帯だった醍醐の市街化も進みました。
この90年間、他にも鉄道や道路のたゆまざる変化、伏見桃山城キャッスルランドの開園と閉園、向島ニュータウンの建設、醍醐寺の世界遺産登録、最近では伏見港の「みなとオアシス」への登録など数えきれないことがありました。
そして、歴史をさかのぼれば、醍醐は山科や宇治市東部とともに宇治郡、神川は向日市などとともに乙訓郡を構成していた時代があります。江戸時代、淀には淀藩の城下町が形成され、納所や美豆などとつながっていました。。旧伏見市、桃山、向島、深草、竹田、下鳥羽、横大路などは、同じ紀伊郡に属していましたが、地域の氏神である御香宮、藤森神社、城南宮、三栖神社、田中神社などを中心にそれぞれのコミュニティがありました。
これら多様な歴史を持つ各地域が90年前、あるいはそれ以降に、縁あって伏見区という名のもとに、共に歩むことになったのです。伏見の歴史は秀吉、龍馬で語られることが多いのですが、そこで話を終わらせず、区内各地の様々な時代に目を向け、互いに理解を深めれば、より多様性にあふれた未来が広がることでしょう。

たゆまざる鉄道の変化
「1970年廃止の市電伏見線と中書島」
(西山修朗氏撮影 伏見駿河屋所蔵)

たゆまざる道路の変化
「高速道路開通前の油小路通と津知橋通」
(1987年筆者撮影)
※この内容は市民しんぶん伏見区版きらり伏見の令和3年7月15日号に掲載しました。
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-611-1295、事業担当・広聴担当・振興担当:075-611-1144
ファックス:075-611-0634