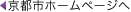第3回「徳川の伏見城」
ページ番号304188
2022年9月22日
第3回「徳川の伏見城」
江戸幕府を支えた尾張、紀伊、水戸の徳川御三家の初代は、三人ともが、家康の子で伏見生まれでした。尾張の義直は幼名の五郎太を深草大亀谷の町名に、紀伊の頼宣(よりのぶ)と水戸の頼房(よりふさ)は御香宮神社の建物の寄進で伏見に名を残しています。
家康は東海や江戸という印象が強いのですが、三人が生まれた1600年代前半、一年の多くを伏見で過ごし、秀吉没後の天下取りに動いていました。そして、1603年に伏見城で将軍となり、その後も伏見に長くとどまりました。伏見には日本初の銀座が置かれていたり、全国の大名が屋敷を構えたりしたため、江戸幕府ではなく伏見幕府の感もありました。
1606年を最後に伏見の首都的機能は駿府(静岡)へ移りますが、将軍家の城としての伏見城は残りました。そのため、大坂の豊臣氏が滅び、家康が亡くなった後も、二代将軍秀忠は数年おきに全国の大名を従えて伏見城に入り、ここを拠点に西国大名の国替えや朝廷との交渉を行いました。
三代将軍家光も江戸から伏見城に入り、将軍宣下を受けました。しかし、伏見城はこれを最後に将軍家の城としての役割を終え、廃城となりました。伏見城は豊臣よりも徳川の城としての期間が長く、しかも初期の徳川幕府には欠くことのできない拠点だったのです。
桃山学区などに残る大名ゆかりの町名もよく眺めると、徳川に近い大名の名前が多く見られます。2023年の大河ドラマは徳川家康です。家康天下取りの舞台として伏見がどう脚本化されるのか楽しみです。(※義直の伏見生誕は『清涼庵縁起』による)
徳川頼宣寄進御香宮神社拝殿
(2021年4月著者撮影)
※この内容は市民しんぶん伏見区版きらり伏見の令和3年11月15日号に掲載しました。
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-611-1295、事業担当・広聴担当・振興担当:075-611-1144
ファックス:075-611-0634