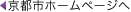第4回「水運の伏見(熊野詣から疏水まで)」
ページ番号304190
2022年9月22日
第4回「水運の伏見(熊野詣から疏水まで)」
昨年は川の港である伏見港が、国土交通省の「みなとオアシス」に登録されました。川の港というと奇抜な感じもしますが、伏見区内には古代から港が幾つもあり賑わってきた歴史があります。
平安時代、皇族、貴族の間で紀伊半島の熊野へ参ることがはやります。都を出た一行は、城南宮あたりにあった鳥羽の港から、淀川を下りました。鎌倉・室町時代は淀の港が京都への物流拠点として機能します。納所の地名の由来もここにあります。
16世紀後半、天下の政庁として伏見城が建設され、城下に港が整備されました。同時期、六地蔵は醍醐から大坂へ向う港となっていました。
大坂に全国の物資が集まるようになった17世紀後半、淀川で伏見へ、そして高瀬川で京都までという交通の大動脈が形成されます。伏見城廃城で衰退していた城下町伏見が宿場町、物流の拠点として再生したのです。そして、淀や横大路、下鳥羽が港湾機能を補完しました。
明治になると、伏見と大坂の水運は蒸気船により近代化されます。また、琵琶湖疏水が深草を縦断して伏見までつながり、鴨川運河の名で呼ばれ、船が行き交いました。
戦後も三栖閘門をとおり、中書島駅南西にあった大きな船溜まりへ石炭の運搬船が就航していましたが、1960年代に水運は幕を閉じました。船溜まりは埋め立てられ、現在は伏見港公園として整備されています。
伏見区内には「みなとオアシス」に登録された伏見港だけでなく、各地に水運の歴史があり、畿内・近畿の交通の要(かなめ)として機能していたのです。

城南宮(筆者提供)

戦前の鴨川運河(疏水)
(「未来へ紡ぐ深草の記憶から」)
関連コンテンツ
伏見区誕生90周年記念歴史コラム!(全5回)
- 第1回「多様性の歴史」
- 第2回「看聞日記(かんもんにっき)の時代」
- 第3回「徳川の伏見城」
- 第4回「水運の伏見(熊野詣から疏水まで)」
- 第5回「幻の伏見区横断鉄道(戦前の鉄道計画)」(最終回)
お問い合わせ先
京都市 伏見区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-611-1295、事業担当・広聴担当・振興担当:075-611-1144
ファックス:075-611-0634