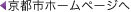防災豆知識をお届け!~家にあるもので、今からでもできる~
ページ番号331198
2024年11月26日
防災豆知識をお届け!~家にあるもので、今からでもできる~
地震や台風などの自然災害が多い日本では、災害への備えは欠かせません。しかし大きな災害直後は防災意識が高まりますが、実際には時間が経過するにつれて薄れてしまいがちに…。
そこで、中京しんぶんでは、シリーズ企画として「防災豆知識~家にあるもので、今からでもできる~」を連載しています。日々のくらしの中で使っているものが「災害時に活用できるかな?」と少し考えてみませんか?
監修:防災寺子屋・京都
※情報源は記事をご覧ください。
第1弾 ペットボトルとスマホのライトでつくる即席ランタン
ライトをつけたスマホの上に水を入れたペットボトルを置くと、光が乱反射して周りを照らすことができます。

さらに、牛乳等を数滴入れて半透明にしてみると、照明のような明かりになりました!

第2弾 災害時、SNSをどう使う?(災害時ではもう遅い!)
災害発生時は、電話やメールがつながらなくなることが多く、とても心配です。しかし、Wi-Fi(無線LAN)等でインターネットに接続できれば、「LINE」や「Facebook」等のSNS(ソーシャルネットワーキングサービスの略)を使用でき、大切な人に連絡することができます!
今回は国内でよく使用されている「LINE」の災害時の活用方法をご紹介します。
LINEの「ノート」機能に基本ルールを書いておく
「ノート」の記載例:
災害時の連絡方法
・このグループトークに、それぞれの居場所を位置情報をつけて連絡
・スマホの電源が切れた場合は災害伝言ダイヤル「171」を使用する。
災害伝言ダイヤルの登録番号は090-XXXX-XXXX(太郎の携帯電話番号)を使用すること。
・太郎の避難場所は○○小学校
・非常用持出袋は1階の〇〇横にあるので、太郎が居ない場合は、家に居る人が避難場所に持ってくる。
「アナウンス」機能を活用する
重要なメッセージを長押しし「アナウンス」を選択すると、トーク画面の上部に固定表示することができます。
集合時間や場所など、一定期間目立たせておきたい情報を目立たせることができます。
「安否確認」機能
震度6弱以上の大規模な災害等の発生時に出現します。
タップするだけでLINEに登録している「友だち」に状況を共有することができます。
LINEのほかのSNSでもメッセージ機能がありますので事前にどのSNSを使用して、何(どのような連絡事項)を共有するか、大切な人と確認しておきましょう! Wi-Fiの接続方法も事前に確認しておきましょう。
→記事はこちらから(令和6年4月15日号)
記事では、「ノート」機能の使用手順についてイラストで掲載しています。
第3弾 キャッシュレスの時代ですが、現金は必要!
昨今は、交通系ICカード等の電子マネーや、QRコード決済サービスなどにより、現金を持っていなくても簡単に支払うことができます。
しかし、災害が発生し、ライフラインの電気が途絶えると、電源を必要とする機器は使用できなくなり、スマホも充電がなくなれば使用できなくなります。
そのため、10円玉、100円玉といった硬貨や、少しのお札等を切らさずに持っておきましょう!
また大規模災害が起きたとき、日本銀行は被災地の金融機関に対し「災害時における金融上の特別措置」を要請します。これを受けて金融機関は、被災者が印鑑や通帳がなくても預金の引き出し(限度額有)ができるよう、柔軟に対応をすることになっています。
基本的に本人であることが確認できれば預金の引き出しは可能です。運転免許証等の本人確認書類は日頃から携帯したり、避難袋にコピーを入れておくなど、対策しておきましょう!
→記事はこちらから(令和6年5月15日号)
第4弾 こんなに使えるポリ袋~小サイズ編~
家に身近にある「ポリ袋」。通常、食材の保存に使用したり、ゴミ袋として用いられることが多いですが、災害時にはとても役立つすぐれものであることをご存知でしょうか。
今回は「小サイズのポリ袋」の災害時の活用方法をご紹介します!

その1
お皿または新聞紙を折ったものにポリ袋をかぶせ、直接食べ物をのせて食べることができます。洗わずそのまま捨てられるため、水を使わずに済みます。


その2
ケガをした方の手当や、ものや食べ物を触るとき、ポリ袋を手にかぶせてから触ることで、菌やウイルスの感染を防ぐことができます。

第5弾 こんなに使えるポリ袋~大サイズ編~
今回は「大サイズのポリ袋」の災害時の活用方法をご紹介します!
その1 水運びが簡単に!
バケツやペットボトルだけでなく、ダンボールやリュックなど深さのある容器にポリ袋をかぶせることで、大量の水を運ぶことができます。
また運んだ後も袋の口を開けるだけで、必要な時に必要な分だけ使用することができ、水瓶(みずがめ)になります。

その2 土のうにもなる!
小さなポリ袋に水を入れて口を縛り、それを大きなポリ袋にいれることで土のうならぬ「水のう」に変身します!この水のうが小さな隙間をうめてくれるので室内への水の侵入を防ぐことができます。

→記事はこちらから(令和6年7月15日号)
第6弾 こんなに使えるポリ袋~大サイズ編2~
その1 簡易空気袋に変身!
火災発生時は酸素が不足し、呼吸をしながらの避難が難しくなります。きれいな空気を大きなポリ袋にたっぷりいれて口元にあてることで、有毒な煙を吸うことなく、避難できます。

その2 雨除けカバーになる!
座る時の敷物として、また大切なものの上から大きなポリ袋をかぶせることで、雨除けカバーとして活用できます。
さらに、切り方ひとつで、カッパ(ポンチョ)にもなります!

その3 簡易布団に変身!
紙おむつを大きなポリ袋に敷き詰めて、その上からバスタオルなどで覆うと、赤ちゃん用の布団や座布団代わりとして使うことができます。

→記事はこちらから(令和6年8月15日号)
第7弾 こんなに使えるポリ袋 ~大サイズ編3~
下水道が壊れている間は、「自作トイレ」 を作成し、衛生的に処理することで生活 空間を清潔に保ちましょう!
1 便座を上げて大サイズのポリ袋を敷き、 便座を下げてからもう1枚ポリ袋を被せます。
2 くしゃくしゃにした新聞紙2枚程度を便器の中に敷き、 その上から丸めた新聞紙を敷き詰めます。
(新聞紙の代わりに紙おむつやペットシーツでも可。 使用後は消臭剤を使うと尚良。柔軟剤でも代用可。)
3 何度か使用してから上のポリ袋のみ廃棄します。
(回収日まではふた付のごみ箱に入れて保管しましょう。手を洗う水も不足するので、手指消毒液を準備しましょう。)
→記事はこちらから(令和6年9月15日号)

第8弾 水分だけとっても脱水予防にならない!?
災害時は通常の生活を送ることができず、様々なストレスがかかり、
知らない間に身体から水分が失われます。(夏場は特に!)水分を常に補
わないと、体内ミネラルのバランスがとれなくなり、脱水症状になります。
一度脱水症状を起こすと、口から水を飲んでも水分を吸収することができず、病院で点滴をせざるを得なくなります。しかし、災害時は病院
が機能せず、安全に点滴を行うことができない可能性も。そこで、今回はいざという時の「簡易経口補水液」の作り方をご紹介します!
水2リットルに塩小さじ1、砂糖大さじ9を溶かすことで
「簡易経口補水液」が完成します。
※レモン汁を少々入れると飲みやすくなります。

非常時に備えて水だけでなく、
小袋にいれた塩や砂糖も一緒に準備しておきましょう! (吸収率は水の25倍!)
※作られたら無菌ではないため1~2日で飲み切るようにしましょう。
→記事はこちらから(令和6年10月15日号)
第9弾 見落としがちな「粉じん対策」
震災に備え、枕元に靴やスリッパを置いて、安全にすぐ
逃げられるように対策をされている方も多いと思います。しかし、見落としがちなのが「粉じん対策」です。 大きな災害時は建物の倒壊などで、目に見えない粉じんが大量に舞います。粉じんは一旦吸い込むと、肺から出ることはなく、窒息や将来の肺機能を低下させる大きな原因
になります。
そこで今回は、災害時の「粉じん対策」をご紹介します!
→記事はこちらから(令和6年11月15日号)
【対策1】大きなバンダナをいつも持ち歩くカバン等の中に入れておきましょう。
口の周りに巻くことで、粉じんの吸い込みを防ぎます。また帯状にすることで止血できたり、石を包むことでハンマーにもなります。

「粉じん防止用マスク」もありますが、市販のマスクでもよく、隙間がないように装着することが大切です。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
引き続き更新していきますので、ぜひお役立てください!
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182