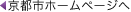北区民まちづくり会議「共同部会」開催結果(1日目)12月17日開催
ページ番号264613
2020年2月7日

開催結果のPDF版はこちら

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 日時
令和元年12月17日(火曜日)午後6時30分~8時45分頃
2 場所
大谷大学 尋源館(じんげんかん)1階J103教室
3 出席者等
(1)部会長等
大谷大学社会学部長 志藤 修史 氏
佛教大学保健医療技術学部教授 松岡 千代 氏
(2)出席者
地域代表者 7人
北区民まちづくり会議委員 11人
地域代表者推薦の地域の担い手(比較的若手の方) 7人
各種地域団体 5人
北区民まちづくり提案支援事業活用経験者 1人
大学生 9人
その他 伝統芸能,伝統産業,寺社仏閣,災害時要配慮者との関わりが深い団体等 12人
(例:観世流能楽師,株式会社 福田喜,今宮神社,地域包括支援センター等)
合計 79人(行政職員を含む)
4 概要
既開催の4部会(高齢化部会,人口減少部会,防災部会,文化・観光部会)を横断して議論する場で,12月17日と22日に同内容で開催した。
テーブルごとに対象となる世代を設定し,これまでの部会意見をもとに,個人が孤立することによって生じる様々な課題に対して,まちやまちづくりによって解消していくためにできることは何かという観点から,取組アイデアをさらに深掘りすることを目的とした。
主な意見と取組アイデア
(1) Aグループ 対象者:子ども(概ね6~18歳)
1 遊ぶ場所,集まる場所。公園に限らず,まちにそんな場所が増えると子どもたちは喜ぶはず!
増やす?見つける?見守る?伝える?どうすれば居場所をつくれるでしょう?
【主な意見】
<世代>
・小中高校生等,世代をまたいだグループ単位で集まれるとよい。
・子どもと高齢者が交流できるような居場所があればよい。
<場所>
・空き家や空き地を再整備し,居場所として活用する。
・是非,神社を活用してほしい。
<情報>
・ラジオミックス京都を活用する。子どもが集まる場所について,子どもの発想で情報発信する。
・メール配信で子どもの様子を伝え,親を安心させる。
<その他>
・環境問題のイベント,ボーイスカウトの野外活動など,楽しいだけではないひとひねりが必要。
・いつでも集える居場所が必要。居場所は安心できる場所でなければならない。
2 習い事も多いけれど,地域の文化や活動にも触れて,継承していってほしい!
食文化,伝統行事,地蔵盆,夏祭り。また,地域企業の活動も知ってほしい!
楽しく伝えていくための仕掛けとは?
【主な意見】
<職業体験>
・企業とコラボし,「北区子どものまち」(※)の取組を発展させる。
・ゲーム形式で北区の企業を回る。
・学校での職業体験は1箇所だが,関心のあることはいろいろ体験できる方がよい。
・神社の職業体験で,雅楽や舞を体験し,夏祭りで発表するなど,職場体験の後,形に残るように工夫できるとよい。
・神社の職場体験は,アルバイト等では体験できないし,文化に触れる機会にもなるので大変よい。
・地域に根付いた企業での職場体験もよい。
・関心ある職業体験をしてみることで,将来の後継者を生むことに繋がるかもしれない(神社・寺,すぐき作り,京野菜等)。
<その他>
・子どもに知ってほしい場所のスタンプラリー。ポケモンGOのようなスマホゲーム。一人ではなく,複数人でクリアしていく。
・地域体験を継続して実施し,経験を重ねた高校生が中心に企画するイベントになれば,大人が企画するよりも子どもウケするだろう。
【取組アイデア】
1 「北区子どものまち」(※)に地域企業や神社の声を取り入れ,バージョンアップする。
※子どもたち自身が,まちの仕組みを考える中で,まちづくりの楽しさや社会の仕組みを体感できる事業。北区が大谷大学と連携して,平成28年度から取り組んでいる。
2 中学校等の職場体験の対象を拡大する。
(2)Bグループ 対象者:大学生(概ね18~25歳)
1 多様な生き方に触れ,地域企業も含めた将来への可能性を広げてほしい!
大学生が学び経験したくなる地域での出会いや交流のしかけとは?
【主な意見】
・学生が参加できるイベントがあればよい。大学によっては積極的に情報発信してくれる。
・(そもそも大学生は地域とつながりたいのかという問いに対して)つながりたい学生は1/3ぐらいだと思う。
・大学生に地域行事に参加し,地域に住み,手伝ってほしい。学生のスポーツ大会を地元にPRしてほしい。大学の知を地域に還元してほしい。地域側も学校行事に参加すべき。地域にどんな楽しみがあるかPRすべき。
・学生の立場で参加してみたいイベントとしては,地域のお祭り1日体験,音楽を通じた交流,学生の発表の場があるイベント等。
・夏祭りなど地域行事にアイデアを持ち込んでもらう。そのための仕掛けづくりが必要。地域のニーズと学生のやりたいことをマッチングさせる仕組みが必要。地域と大学や学生がつながるプラットフォームがあればよい(SNSを活用)。大学が配信するメールを見て参加する学生もいる(例:紙屋川の清掃活動)。
・学生は個人で参加することに抵抗を感じる人も多いので,サークルやゼミ単位で声掛けをしたほうがよい。
【取組アイデア】
1 地域・大学・学生がつながるプラットフォームをつくろう
・SNS,大学メールを活用し,情報発信。地域のホームページと大学のホームページを連携させる。
・大学生を広報班に位置付け,見守り活動など地域活動に参加してもらう。
2 北区が住みよいまちであることをアピール
・家賃が安い物件や割のいいバイト先を紹介する。
・大学近くのバス停に地域の掲示板を設置する,学食のトレーに地域の宣伝を載せるなど,折に触れて大学生が地域情報に接する状況をつくる。
3 地域のお祭り1日体験
地域として具体的に依頼し,例えば盆踊りで,音楽を通じた交流をしたり,学生の発表の場として機能させるなど,学生のニーズに応じた取組を盛り込む。
2 大学での学びを,地域で実践・発表してほしい!
ゼミやサークルが地域で活躍するために,互いに知り合える仕組みとは?
12月22日の共同部会で議論
3 学生自身の災害時の対応や支援者としての活躍に期待!
そんな安心を生む関係・連携を育む仕組みとは?
【主な意見】
・学生は避難場所を知らないことが多い。避難訓練で単位認定したり,大学入学時のオリエンテーションで伝えるなどの工夫が必要。
・学生が地域と一緒に避難ルートなどを示したマップを作る。
・地域と大学が防災協定を結ぶ。
・佛教大学の消防防災サークルFASTのようなボランティアサークルを増やす。
・災害発生時に動くことができる学生とのネットワーク構築が大切。
・学区主催の防災訓練への参加者の少なさが課題。防災訓練とイベントを組み合わせるなど,学生のアイデアを貸してほしい。
【取組アイデア】
・災害時に機能する,学生とのネットワーク構築や防災訓練の参加者を増やすための協力体制の確立等。
(3)Cグループ 対象者:若者世代(概ね20~30歳代の独身の人)
1 北区での暮らしに夢や希望を持ってほしい!いろんな働き方や暮らし方があることを知ってもらうしかけとは?
3 災害時での,自身の対応や支援者としての活躍につなげてほしい!そんな安心できる関係を育む取組とは?
【主な意見】
・北区には山間部とまちなかがある。山間部にはコンビニもないところもある。まちなかは住宅地として住みやすいと思うが,若い人から見てどうなのか知りたい。
・シェアハウスに住む学生は意外に多い。個人のプライバシーがしっかり守られる個室もある。行政が紹介して,安心して住めるような制度があれば,所有者としても安心だ。
・シェアハウスは住むだけではなく,一緒に料理をしたり,協力して農業をするなど,多様な価値を見出しうる。学生に限らず,若者も活用できるのではないか。
・自身が独身の20~30代の頃は北区には仕事がないと感じ,外に出ていたが,北区は独立して店を持つには非常に魅力的なエリア。内容も多彩で,パソコンひとつで仕事する人もいれば,農業もある。
・人口減少という観点から,京都市内で人の取り合いをするのか,滋賀など近隣県から来てもらうのか,という価値判断もある。学区のイベントでも,若者は面白いものには参加する傾向がある。
・学生の意見として,既にあるものに参加するよりも,企画段階から主体的に参加できるようなものであれば関わりたいと思う。
・新大宮広場のように,若い人が自由に出店できる場所と機会がたくさんあればよい。押し付けではなく,企画から関わり,イチからつくることができる機会が大切。また,北区が外国人にとっても住みやすい環境にしていきたい。
・北区のまちなかでは本当に空き家が目立つ。移住者に空き家を貸せないか。住民税を下げるなどの思い切った対応ができないか。山間部では京大生等で構成される山仕事サークル「杉良太郎(すぎよしたろう)」の活動で大変助かっている。土地を持つ人には農業をやってほしいという声もある。
【取組アイデア】
1 北区の暮らし妄想ラボ
内容:「今ある暮らしを伝える」よりも,「北区でこんなことができるかも!」を提案するプロジェクト。
※イチから主体的にかかわれる内容であることが大切。
※志ある職人さんや芸術家で,何かチャレンジしたいけれど資金面の課題などから二の足を踏む人が実際に出店できる
場所を設ける。
広報:ラジオミックス京都の活用,CM,動画の作成。声を集める仕組みと発信する仕組みが重要。
活用資源:空き家,空き地,山,小学校などの資源を有効活用する。
2 災害時に役立つ地域の炊き出しBBQ大会
内容:地域の広場や小学校などで,火おこしの練習や炊き出しの予行演習を兼ねてバーベキュー大会を開催。
2 北区で暮らしていることをもっと楽しんでほしい!
文化のこと地域のこと,若者が学び経験したくなる出会いや交流の仕組みとは?
12月22日の共同部会で議論
(4)Dグループ 対象者:子育て世帯(概ね0~6歳の子ども,20~40歳代の親)
1 子育てしている期間も,北区を楽しく過ごしてほしい!
いろんなサービスとあわせて,地域で子育てを支える仕組みとは?
12月22日の共同部会で議論
2 親子で北区の魅力を体験してほしい!
自然や文化,地域の魅力を伝え,地域で育った思い出をつくってもらうには?
【主な意見】
・イベントに向けた地域団体の役員会議や打ち合わせは回数も多く,若い人が全て出席するのは大変。会議の回数を減らしたり,全て出席しなくてもよいなどの工夫をして参加を呼び掛けてはどうか。
・地域の役員をお願いする際,楽しい和気あいあいとした入りやすい雰囲気作りが必要。知らない人の中に入っていくのは誰でも気が引けるもの。
・上賀茂学区では,農村文化が残っており,消防団に若い人は入るものという雰囲気が残っているため参加に繋がっている。そのような雰囲気作りも有効。
・金閣学区の役員は女性が多い。若い女性パワーを活用するためにも,会議が子どもの世話付きであれば参加しやすくなる。また,夜の時間帯よりも昼間の時間帯の方がいいという人もいる。昔は近所の人に子どもを預かってもらったりしていたが,最近では難しい。
・小学生の場合,「放課後まなび教室」(※)や「みやこ子ども土曜塾」(※)とコラボして,それらの実施時間帯に会議を開催するという方法はどうか。
・大学生が地域行事に参加し,子どもをみるなどのお手伝いをしてもらえれば助かる。
・大学生を単に地域行事の人手として便利使いするのでは誰も来ない。学生リーダーを決めてもらい,企画段階から参加してもらうことで,自主的に動いてくれるのでは。
・若い人に参加してもらうためには,楽しい場になるよう工夫が必要。楽しそうと感じると,少々しんどくても行こうかなという気持ちになる。
・文化・芸術,スポーツに子どもが参加するような取組なら,親や祖父母も集まるのではないか。
・北区には,文化・芸術などで大変秀でた実績のある人が実は多く住んでいる。そのような人を発掘して協力してもらい,文化・芸術やスポーツを子どもに教えてもらう。
※放課後まなび教室…放課後の子どもたちに,学習の習慣づけを図る「自主的な学びの場」と「安心安全な居場所」を提供する事業。市内全小学校で実施している。
※みやこ子ども土曜塾…「まち全体を学びと育ちの場に」を目標に,土曜日をはじめ学校休業日に様々な学びの場を提供し,子どもを育む市民ぐるみの取組。
【取組アイデア】
1 集まれ!となりの人間国宝さん教室
北区には,文化・芸術などの分野で大変秀でた実績のある人が住んでいる。そのような人を発掘して講師になってもらい,地域で文化・芸術やスポーツを子どもに教えてもらう。小学生の場合,「放課後まなび教室」や「みやこ子ども土曜塾」とコラボして,それらの時間帯に会議を開催してはどうか。また,教室で学んだ成果を,地域のまつりなどで発表すれば,発表を見に親や祖父母も来る(今まで地域のまつりに参加しなかった層の発掘にもつながる)。
3 災害時にも,安心できる地域にしたい!
親子にとっての安心のために,地域にできることは!
【主な意見】
・子育て世代は,年齢的には災害時に最も頼りになる存在だが,自分の子どもや親などの面倒をみることで精一杯で,地域の世話役までこなせないのではないか。
・できる人がやればよい。避難所では中学生も立派に戦力になっていると聞く。できる人が動いて困った人を助ける仕組みを作る。
(5)Eグループ 対象者:そろそろ老後が気になる世代(概ね40~60歳)
1 趣味や特技など,北区で学びを深めてほしい!
サークル活動や講座など,学びや遊びを,地域への入口にするには?
【主な意見】
・働き世代であり,日中のイベント参加は困難。
・休日に40~60歳対象のイベントを開催する。
・家族で参加できるイベントなどを企画することで,家族サービスとセットで参加できるのでは。
・自分から仕掛けていく。とにかくやってみる,言ってみる。一人でも始めてみることで,コミュニティができていくはず。
・忙しい40~60代が参加しやすいタイミングを見極めて,地道に継続開催する。
・イベント等に来ない人をどう引っ張り込むか。来てほしい人へのアプローチをどうしていくか。(こまめに声掛けするしかないのか…)
・最初に登録してもらい,その人のニーズに応じた情報を提供する。人を誘ってきたら特典を用意するなど工夫を。
【取組アイデア】
1 「とにかく集まれ!大人の土曜塾」
紙媒体,FAX,SNS,ラジオなど,様々な媒体で情報発信。最初に登録し,興味ある分野にチェックを入れる。必ず一人は連れてくる。いろいろな仕掛けを用意する。既にやっていることを発信する。
【補足】出てくること自体が難しい世代なので,イベントを分かりやすく発信するとともに,半ば強制的に参加してもらう仕組みを作ることで,地域活動に引き込んでいく必要がある。
2 体の健康だけでなく,心も健康でいてほしい!
美化活動や子育て支援など,空いた時間に気軽に参加できるような社会貢献の仕組みとは?
12月22日の共同部会で議論
3 災害に対して,安心できる地域にしたい!
情報が行き渡る,高齢者にとって安心できる防災とは?
【主な意見】
・トレパトウォーク(トレーニングとパトロールを兼ねたウォーキングのこと),インターバル速歩のような,楽しみながら体を動かせる方法があればよい。
・コンビニを含む地域の店に協力してもらい,健康情報を発信。(買い物は引っ込みがちな人も行くので,その機会を捉えて発信する。)
・YouTube等で北区のいいところを発信(湧き水を汲んでお酒を楽しむとか。)
【取組アイデア】
「お店や商店街を活用しよう!」
買い物スタンプラリーをして,最後はウォーキングなど健康活動に参加してもらう。
(6)Fグループ 対象者:元気な高齢者
1 趣味や特技など,北区で学びを深めてほしい!
サークル活動や講座など,学びや遊びを,地域への入口にするには?
【主な意見】
・女性は引っ張り出しやすく,グループで参加することが多い印象。
・男性はプライドが高く,得意な分野は参加するが,自分に合わなかったり,明確な目的がないものは敬遠しがちなようだ。会社勤めをしていると,上下関係に慣れて,地域のフラットな関係性に馴染めないということもある。
・男性の共通の話題としては,野球や競馬,農業,旅行,健康に関する話など,女性と比べると限定されている印象。
・友達になる「仕組み」のようなものが必要。何度も誘ったり,イベント後などタイミングを見計らって声を掛けることも大切。
【取組アイデア】
特に男性に対しては,「人の役に立つ」など目的を明確にした集まりであることがアピールになる。そのうえで一緒においしいものを食べ,酒を飲み,集まりに帰属意識を持ってもらうことで,継続した参加につなげていく。
2 高齢者の豊富な知識や経験をまちに活かしてほしい!
若い世代に刺激を与えるような,まちづくりへの関わり方とは?
12月22日の共同部会で議論
3 災害に対して,安心できる地域にしたい!
情報が行き渡る,高齢者にとって安心できる防災とは?
【主な意見】
・防災訓練をしても,高齢者ばかりで比較的若い世代は出てこない。
・高齢者等を避難させるためには事前の情報が必要だが,個人情報の壁もある。町内会長が要支援対象者を把握しているが,他の人にも共有することは難しいところが課題。
・山間部では,「自宅外に避難する際は町内会長に言う」ということが当たり前にできているが,まちなかではそうではないと思う。仕組みとして確立する必要があるかもしれない。
【取組アイデア】
・地域の人が知っている,「川のどこの水位がどこまで上がったらこの地域は注意した方がいい」とか,「この地域は坂になっているから他の地域よりも浸水する可能性が高い」といった,市が出す避難情報では分からないようなローカル情報をしっかり共有しておき,「ここがこうなったら避難する」という「危険スイッチ」のようなものを地域が共通認識として持つようにしておく。
・自宅から避難する際には,避難していることがひと目で分かるよう,共通の目印を自宅に掲げる。
(7)Gグループ 対象者:健康に不安を感じる高齢者
1 高齢になっても,安心して暮らしてほしい!
多くの人と,顔の見える関係を育むには?
【主な意見】
<交流>
・節目節目で食事会を企画する。
・町内会単位でイベントを開催する(結局同じ人ばかり参加する,という意見もあり)。
・参加したり,関わりを持ち続けようという気持ちになるには,感謝したりされたり,「気持ちのおみやげ」のようなものが大切だ。
・子ども食堂が増えたが,これからは子どもだけを対象にするのではなく,高齢者も集まるようにする。子ども食堂は貧困のイメージがあり,人によっては行きづらく感じてしまう。開かれた,誰でも参加できる「みんな食堂」が必要だ。
<交通・足>
・敬老乗車証があっても使えていない人が多い。低価格で利用できる送迎車があれば気軽に出かけられる。
・気軽に声を掛けられる人間関係づくりが大切。車で通りがかりに声を掛けて目的地まで連れて行ってあげるような関係があれば,その時の世間話からいろいろなことが分かる。
<日常の小さな困りごと>
・大学生が困りごとのアンケートを集める。
・風呂掃除の実情を知り,手助けする。(風呂掃除が大変で週1回しか風呂に入らない人もいるという声を受けて。)
・役割があることで人は輝くことができる。すぐき作りやしめ縄作りなど,多少形は悪くても昔取った杵柄でできる。そういったものを安く売れる場所があるといい。
・高齢者のお宅で格安の大学生下宿を運営する。
【取組アイデア】
1 格安下宿へどうぞ!(京都市版「ソリデール」)
子育てが終わり,部屋が余っている高齢者が,空き部屋を学生の下宿として活用,運営する。学生にとっては家賃が安く済む,昔の知恵を得られる。高齢者にとっては話し相手ができ,防犯にもなってスマホの使い方など最新の知恵を得られるというメリットがある。まちとしても,世代交流が促され,学区運動会などの地域行事に大学生が参加するきっかけとなる。
2 「みんな食堂」をはじめよう!
子どもから高齢者まで多世代が集まる,「子ども食堂」の全世代対象版。ボランティアが運営し,食材や調理器具やスーパーやコンビニ,JAなどから寄付してもらい調達する。大学生が子どもに宿題を教えるなど,連動した取組も考えられる。子どもやボランティア,学生3人以上で無料など,料金設定を工夫する。個人にとっては安く食事しながら交流でき,居場所にもなる。またそういった場所が増えることで,誰もが居場所があると感じるまちづくりにつながる。
2 災害に対して,安心できる地域にしたい!
情報が行き渡る,高齢者にとって安心できる防災とは?
【主な意見】
・情報共有が何よりも大切だ。住民間だけでなく,各種団体や地域外の団体など,幅広い共有が必要。特に山間部は左京区・右京区とも隣接しており,山に境界はないため,行政区をまたいだ連携が特に重要と感じる。
・学区で決められた避難所が必ずしも最寄りとは限らない。近いところに避難できるようにできないか。その場合,あらかじめ情報共有していないと,避難所では来るべき人が来ない,と混乱状態になる。あらかじめ決めておく必要があるだろう。
【取組アイデア】
・情報共有の徹底を!
地域ケア会議での情報共有の徹底。特に山間部では行政区をまたいで連携することが重要だ。それにより,個人にとっては避難の心理的ハードルが下がり,まちにとっては避難が難しい人の把握,対応方法の事前確認ができる。
(8)Hグループ 対象者:北山三学区
1 多くの人に北山の魅力を感じてほしい!
イベント参加や活動への協力など,北山の魅力を活かした交流のしかけとは?
3 山間地でも安心して暮らしてほしい!
災害時の対応や復旧活動など,市街地の住民とできることは?
【主な意見】
・人口が減り,兼務する役職が増えるなど,一人にかかる負担は重くなっている。ゴミ分別などで学生が協力してくれており非常に助かっているが,受け入れ側の年齢だけが上がり続けているという現実がある。
・ホストとゲストの関係にある限り,受け入れ側の労力が必要という課題は残る。学生や地域外の人の活動を受け入れるより,「任せる,自由にさせる」と受け入れ側の負担が減るかもしれない。ただし,任せた後の考えは継続性をもって考えないと,ただやっているだけになるのではないか。
・単純に受け入れというよりも,WIN-WINの関係で,何か困っていることや助けてほしいことを大学生に頼む方法もある。
・子ども世代に集まってもらい,親世代が住む地域の状況を知ってもらえれば。自助も必要であり,家族で何とかしてほしいところはある
【取組アイデア】
・ニュー青年会
地域に親が住む子ども達のネットワーク化。不安や困りごとを相談できる関係を作り,まちの未来を担う。
2 自然に寄り添った暮らしの魅力を知ってほしい!
北山三学区を続けるための, 移住を促す仕組みとは?
【主な意見】
・そもそも3学区に移住者が来てほしいのかという疑問の声もあるようだが,やはり地域に灯かりがあるのは嬉しい。できれば,誰かわかっている自分たちの子ども世代に帰ってきて住んでほしいと思う。
・移住が進まないのは,市街化調整区域のため,売買や建て替えなどが難しい地域であることも関係しているのかもしれない。
・以前,区域外から就学を希望する児童を受け入れている他市の小学校を視察し地域で報告した際は,積極的に受け入れることに賛否があった。
・地域を出た人が戻ってくるシステムがあれば。夏まつりなどは子どもがたくさん来るので,この機運を一時的なものにしないようにしたい。
・北山3学区について話す会議は,実際に地域で話す方が現実味があると思う。現地のこと知らずに話をしているので実際の現場を見ながら話すほうが良い。
・土日のみ学校の校舎を開放し体験活動をする人を受け入れることはできないか。行事で地域が疲弊しているのでできるだけ減らすことも必要だが。
・区役所が率先して地元の様子をみることが必要。
【取組アイデア】
1 川で金魚すくい!
子どもが楽しめる山や川を活かしたイベント。孫世代に向けたイベントを移住希望者にも拡げる。まずは雲ケ畑からやってみる?
2 小規模特認校制度を活用する。
PTAと相談しながら学校を通じた北山三学区の体験学習を。まずは週末からスタート。中川は「村おこしの会」も一緒に。
3 会議を北山で!
北区のことを考えている人が北山三学区に集まる機会を作り意識を変える。まずはまちづくり会議を北山三学区で開催する。
(9)Iグループ 対象者:障害者
1 障害者への理解が深まり,誰もが安心して生活できる環境をつくりたい!
地域で障害者への理解が広がるしかけとは??
【主な意見】
<障害への理解>
・障害者をあまり知らない。身体障害者手帳の内容や,手帳を持つ人が学区でどれだけいるのか,どこまで話を突っ込んでいいか分からない。
・「見える障害」と「見えない障害」があるので,どう接してよいかわからない。手助けして何かあって責任を問われても困る。
・「何かお手伝いしましょうか」と尋ねてほしい。また障害を持つ人と友達になってほしい。そうすれば自然と分かり,手引き歩行も身に付くのではないか。
・障害のある人は自分と違うと区分けせず,同じ住民だという思いが大切。誰でも急病や事故で障害を持つ可能性があることに関心を寄せてほしい。
・まちの段差はその人の課題でなく,まちの課題という認識が大切。
・地域包括支援センターの高齢者の見守り名簿は,75歳以上の単身生活者を対象にしているが,障害者と同居の場合でも対象にしてほしい。
・接し方は,施設の支援スタッフを見るだけでも勉強になる。まずは出会えるところに出かけるといい。ライトハウスの喫茶コーナーを利用してはどうか。
<障害者と一緒に開催する催し>
・当事者が何を望んでおられるのかをまずは知ることが大切。イベントを企画したが,そこを把握していなかったため参加者が少なかった。企画の段階から地域と障害者とのコミュニケーションが必要。
・「フナオカスタンダード」では多くの障害者に会える。ぜひ参加してほしい。
・各学区で「プチ・フナオカスタンダード」を開催してはどうか。
・障害者施設も地域に出ていく努力をしている。町内会に入り,掃除ボランティアをしているところもある。お互いを理解し合う良いきっかけである。
・学区行事に障害者自身が参加し,自分のことを語ることで地域に障害への理解が広まる。障害者も役割を果たせることに生きがいを感じるのではないか。
・町内の餅つき,運動会,敬老会に地域の障害者施設からの参加者を受け入れてはどうか。
【取組アイデア】
・各学区でプチ・フナオカスタンダード
地域の催しや行事(運動会,お祭り,敬老会など)に障害のある人が出張。施設の人が障害者の得意分野を見極めて,一緒に地域へ出て参加。(例 地域のカフェにコーヒーを入れに来てもらうなど)
2 災害に対して,障害があっても安心できる地域にしたい!
障害者にとって安心できる防災とは?
【主な意見】
・「北コミまつり」などでは障害に関するブースもあり,「フナオカスタンダード」で障害者の防災に関するブースを来年度は設置してはどうか。
・学区の様々なイベントで啓発していく。
・福祉避難所の訓練を多くの学区に広げていく。
・障害のある当事者も避難訓練に積極的に参加し,障害者がここにいるという発信をする意識改革が必要。
【取組アイデア】
・フナオカスタンダードのような催しを開催
障害のある方の防災を考えるブースを出す。佛教大学で災害訓練に取り組んでいる先生がおり,行政も連携する。まずは障害者のニーズを聞くことが大切。心のバリアフリーを広げていくためにも必要な取組。
(10)Jグループ 対象者:外国人
1 北区に移り住んだ外国人が地域の魅力を感じながら楽しく暮らしてほしい!
北区の良さを感じてもらい地域に馴染んでもらうしかけとは?
【主な意見】
・誤解を恐れずに言うが,居住外国人は,大きく2種類に分けられると思う。生活に余裕のある外国人と必ずしもそうではない方。後者は,例えば出稼ぎとして単身で来日し,働きづめの毎日のような印象。地域に溶け込む余裕がなく,仲間内で独自のコミュニティを形成している。こうした人たちにターゲットを絞り,対策を立てることが必要ではないか。
・まずは実態把握が重要。どこに,どういう状況の外国人がどれだけ住んでいるのかを,地域が把握する仕組みができないものか。
・悩みを打ち明けられる場としての相談窓口が必要だが,現代ではネットを上手に活用することが有効。外国人同士の独自のコミュニティをネット上でも形成しているはず。そこにうまく働きかけることが必要。
2 外国人観光客に北区の魅力をもっと伝えたい!
特定の観光地にとどまらない,北区の魅力を届けるための取組とは?
【主な意見】
・ハードとソフト両面でのアプローチが必要。ハード面では,楽只市住の再整備もふまえて,インフォメーションセンターを設置してはどうか。大学生を活用し,案内所であると同時に交流センターのような機能を持たせたい。北区の伝統産業製品,農林産品等の紹介,北区アンテナショップのような機能もあると良い。ソフト面では,コーディネーター。人気のゲストハウス経営者は優秀なコーディネーターでもある。ほんまもんをうまく組み合わせて紹介している。
外国人観光客は,それぞれの国の口コミサイトを活用しているので,相手に応じ情報を適切に流す必要がある。
・外国人に発信する前提として,地域の魅力を地域が知る必要がある。地域住民の口コミサイトの立ち上げ,生き字引や長老へのインタビュー,まち歩きなどにより,まずは地域の魅力の掘り起こしが必要。
3 北区に移り住んだ外国人に災害時での,自身の対応や支援者としての活躍に
つなげてほしい!そんな安心できる関係を育む取組とは?
12月22日の共同部会で議論
5 部会長のまとめ
(志藤教授)
・大学と地域の接点づくりや,男性の地域活動への参画など,「孤立」の解消にまちづくりが果たす役割のヒントが多く出されたと感じる。まちづくりは一朝一夕に進むものではないが,皆が自分ごととしてとらえていく空気が最も大切だ。そのきっかけづくりとなるような基本計画となるよう,事務局には本日出された意見をしっかりと受け止めてもらいたい。
(松岡教授)
・意見が多く出された部分と,比較的少なかった部分があると思う。それも含めた現状を踏まえ,どう行動していくかが北区の未来をつくっていく。皆さんが率先して行動することが大切と感じた。
関連コンテンツ
北区民まちづくり会議 部会の開催結果
- 北区民まちづくり会議「人口減少部会」開催結果
- 北区民まちづくり会議「防災部会」開催結果
- 北区民まちづくり会議「共同部会」開催結果(1日目)12月17日開催
- 北区民まちづくり会議「共同部会」開催結果(2日目)12月22日開催
お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画連携担当、事業担当、広聴・地域コミュニティ活性化担当、振興担当:075-432-1208
ファックス:075-441-3282