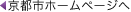北区民まちづくり会議「文化・観光部会」開催結果
ページ番号258127
2020年2月7日

北区民まちづくり会議「文化・観光部会」開催結果

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 日時
令和元年9月2日(月曜日)午後6時30分~午後8時30分
2 場所
北区役所3階 大会議室
3 参加者等
(1)部会長
立命館大学准教授 河角 直美 氏
(2)出席者
地域代表者 7人
北区民まちづくり会議委員 3人
地域代表者推薦の地域の担い手(比較的若手の方) 2人
各種地域団体 3人
北区民まちづくり提案支援事業活用経験者 1人
大学生 5人
その他,伝統芸能関係,織物関係,観光関係,寺社仏閣関係
の団体・個人 10人
(例:観世流能楽師,株式会社 福田喜,株式会社龍村光峯,茶道速水流,
株式会社らくたび,今宮神社,大徳寺)
合計 55人(行政職員を含む)
4 概要
京都産業大学文化学部村上教授から「生活文化と地域」をテーマにお話しいただいた後,ワークショップ1として「北区の生活文化ってどんなもの?(過去~現在)」をテーマに,グループごとに自分の住んでいる地域を基点に“生活文化”を出し合った。
その後,時代が変化しても,生活の中に文化が息づく“しかけ”を模索するため,ワークショップ2として「未来の暮らしにも生活文化を!(現在~未来)」をテーマに話し合った。具体的には,ワークショップ1で抽出した「生活文化」や「伝統芸能」を通じて,「地域をつなぐためにできること(地域コミュニティ)」及び「地域を元気にするためにできること(観光)」についての取組アイデアについて検討した。
主な意見
(1)Aグループ
テーマ:生活文化と伝統芸能で,地域をつなぐためにできること
【身近な生活文化とは】
・個人商店・・・昔はどこでも魚屋,八百屋,駄菓子屋とそれぞれの商店があったが,今はスーパーで足りるようになった。便利になった反面,店の人や隣近所との付き合いは薄れてしまった。
・幸在祭(さんやれさい)・・・上賀茂神社・大田神社に15歳の元服を報告する。
・千度参り・・・年に1~2度,町内の人が集まって疫病が流行しないよう祈念する。
・銭湯・・・地域の人とのコミュニケーションの場にもなっている。
・その他,やすらい祭(今宮神社),地蔵盆,メンコ遊び,納豆餅,松上げ,茶文化,野菜の振り売り,盆送り(千本えんま堂)等々
・学生に優しい・・・学割のある店が多い,地域の人が学生に温かいなど。
・障害者に優しい・・・元町学区では障害者施設や支援活動をしているNPO法人が多い。
・西陣工房など,伝統工芸で障害者雇用を行っているところもある。
・各学区の居場所づくり活動は,100年続けば文化になる。
・北区民ふれあいまつり・ふれあい発表会,FUNAOKA STANDARD(フナオカスタンダード)などのイベント
【地域をつなぐためにできること】
・「裏を往く」(平成30年度に北区役所改革実践チームが作成した北区の魅力を伝える冊子)で取り上げたような「住民でも知らない,知る人ぞ知る」という情報を掘り起こし,多くの人に伝えることが必要だ。
・情報をもとにして,人や物が動く仕組みを作りたいと思っている。例えば,障害者が作った物を観光客が手に取ってくれるなど。人とつながることによって,誰かが楽になるような仕組みとなれば。
・昔は神社の境内が交流の場だった。神社が変わったわけではなく,地域の方から離れていったのだと思う。
・しっかりした祭りが地域に残っているところは,子どもを地域で見守る環境を保っていることが多いのではないか。
・子ども自身が参加したくなるようなイベントでないと,習い事や塾で忙しい現代の子どもは参加しない。宿題を一緒にするなどの工夫をしていくことも必要ではないか。
(2)Bグループ
テーマ:生活文化と伝統芸能で,地域を元気にするためにできること
【身近な生活文化とは】
食
・すぐき,焼きもちが生活の中に普通にある。
・正月にお雑煮ではなく,納豆餅を食べる。かつては納豆も自家製で作っていた。
・白みそ雑煮,京野菜の振り売り,パンとコーヒー(コーヒー屋さんが多い)。
お祭り
・葵祭,上賀茂神社の賀茂競馬
・今宮神社のやすらい祭り,あぶり餅
・建勲神社の船岡大祭
・地蔵盆,春祭り,秋祭り,区民運動会
・寺社仏閣等の手作り市が多い
スポーツ
・山が近く,ロードバイク乗りには素晴らしい環境がある。
・大文字駅伝。市民にはお馴染みで応援も迫力があり,冬の風物詩となっている。
伝統工芸
・工房見学を積極的に開催し,単なる体験教室ではなく,機織り機に触れ,ありのままを楽しんでもらえるような体験会を開催している。
環境
・市の中心部と比較すると公園が多く,緑豊かな環境がある。大宮交通公園のような大きな公園や,賀茂川河川敷といった自然が身近にある。
【地域を元気にするためにできること】
・京見峠の湧き水や雲ケ畑の鴨川源流など,水資源の豊富さを活用できないか。
・例えば「◯◯さん家のお雑煮」など,京都ならではの食文化を学べる体験会。
・地蔵盆をはじめ,地域に息づく行事に参加を促す工夫。フリーペーパーで広報するなど。
(3)Cグループ
テーマ:生活文化と伝統芸能で,地域をつなぐためにできること
【身近な生活文化とは】
・山間部における,畑や山での作業協力
・食事や野菜のおすそ分けをはじめとした近所の人との交流
・松上げ,お火焚き,地蔵盆
・昔ながらの商店街から,若者向けの新しい店もある。
・四季折々の家屋等のしつらえ。
・お祭りの際に各家庭で用意した鯖寿司,おはぎ,ぼた餅。
・白みそ雑煮,羽二重餅,亥(い)の子(こ)餅。
・大学が多いため,学術関係者や知識人が多く住む風土。
・北山杉,北山丸太,北山台杉。
・学区ごとの夏祭り。
・「水」と縁が深い生活(京見峠や上賀茂神社の湧き水)
【地域をつなぐためにできること】
・お寺で花見やバーベキュー,お月見を開催し,地域の交流の場にする。
・外国人,留学生,大学生が参加できる,新しい送り火や地蔵盆を開催する。
・北区産の野菜を売りに行くことができる,道の駅・里の駅のような「まちの駅」があれば,交流も生まれる場所になるのではないか。
・空き家を文化資源として活用する。
・例えば,西陣織と自動車メーカーがコラボレーションして,カーボンファイバーで西陣織を織るなど,伝統技術を新素材に活用して新たな商品を生み出す。
・北山杉の端材を活かしたお土産づくり。
・北区の野菜を使った「持ち寄りご飯会」。
・自転車の観光コースを設定し,国内外に発信する。
(4)Dグループ
テーマ: 生活文化と伝統芸能で,地域をつなぐためにできること
【身近な生活文化とは】
・8月16日に左大文字に護摩木を納めに行く。伝統行事が身近に感じられる。
・托鉢の修行僧の声が聞こえる。
・区民運動会で本気で頑張る。
・尺八や琴のけいこ場が身近にある。
・ご飯を食べるときに必ず漬物を食べる。賀茂のすぐきは京都が誇る最高品だ。
・おいしいパン屋さんが多い。京都の人は3軒ぐらい行きつけのパン屋さんを持っており,その時の気分や用途で使い分けている。
・新しい食べ物や様々なジャンルの店ができて,良いものであればそれを受け入れる文化がある。
・犬矢来,垣根など,昔からの京都らしいものが残っている。
【地域をつなぐためにできること】
・アピール不足。例えば東京都港区のように,ブランド化できるいいものがたくさんある。それらをもっとPRして北区ブランドを確立すべき。
・建勲神社の刀はアニメ「刀剣乱舞」」でモデルとして取り上げられている。船岡山を聖地巡礼先としてもっと盛り上げられないか。
・よい素材はたくさんあるが,それらを一覧できるマップがない。パン屋さんや食文化の情報を落とし込んだり,区民目線の辛口コメントをつけたりしても面白いものができるのではないか。
・楽只市営住宅は立地的に金閣寺と上賀茂神社の間に位置している。外国人向けのインフォメーションセンターにして,北区の文化が一目でわかるようにしてはどうか。
(5)Eグループ
テーマ:生活文化と伝統芸能で,地域を元気にするためにできること
【身近な生活文化とは】
・銭湯
・表具屋
・おすそ分けなど近所とのコミュニケーション
・川での金魚すくい
・納豆餅
・結婚のときのお嫁さん披露
・ラジオミックス京都
【地域を元気にするためにできること】
・楽只市営住宅の再整備において,1階を商業施設,2階を北区役所,3階を24時間の託児施設としてはどうか。
・北区の特産品を巡るツアーや,道の駅や商業施設などに集約された場をつくる。
・北区サイクリングコース「キタイチ」を考案する。
(6)Fグループ
テーマ:生活文化と伝統芸能で,地域をつなぐためにできること
【身近な生活文化とは】
・銭湯が今も比較的多く残っている。
・商店街,特に個人商店が比較的元気なところが多い。
・お祭りや四季折々の行事が多くある。
・子どもたちに地域の畑を使って農業を教えている。
・しめ縄飾りを焼く「どんと焼き」を行っている。
・精霊流し,おしょらいさん,大根炊き,明神川の灯篭,北山杉の磨き砂等々
【地域をつなぐためにできること】
・まずは知り,興味を持ってもらうことが大切。経験していいと思えるものが後世に残り,文化となる。本来文化は固定的なものではなく,移ろいゆくものである。
・様々なことが移ろい,変わっていくが,根っこにあるものがどれだけ共有できるか。
・「知る」「いいなと思う」「好きになる」。そういった経験が個人のアイデンティティとなり,やがて個人でなく地域のつながりに広がっていく。
・特に子供が様々なことを経験する機会を大人がどれだけ作ることができるか。そのためには,学校の教員もその地域にある文化を知っておく必要がある。
・お米はスーパーで売っているが,稲穂から脱穀した後のわらを使ったわら細工のように,自然の恵みを最後まで使い切るということを,地域の人が小学校で教えている例がある。
・商店街活性化に大学生が関わっている事例のように,学生が地域をつなぐキーマンになると思う。
5 部会長のまとめ
本日の部会では,非常に活発な意見交換ができた。そのこと自体がすばらしく,大切なことだと思う。
あるテーブルでは,次の世代への伝え方についての意見も出ていた。北区で長く住んでいて知っていることや新たに見つけたものなどをお互いに伝えられる拠点,情報誌などの活用である。また,私自身の意見だが,京野菜(賀茂なす等)は北区がもっと誇ってもよいものではないか。平安時代頃から作られてきている歴史があり,京都の中心部にはないものである。
何よりも,お互いに理解し合いながら,次の世代に文化を伝えられればと思う。関連コンテンツ
北区民まちづくり会議 部会の開催結果
お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画連携担当、事業担当、広聴・地域コミュニティ活性化担当、振興担当:075-432-1208
ファックス:075-441-3282