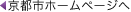北区民まちづくり会議「防災部会」開催結果
ページ番号255284
2020年2月7日

北区民まちづくり会議「防災部会」開催結果
開催結果のPDF版はこちら

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
1 日時
令和元年6月26日(水曜日)午後6時30分~午後8時30分
2 場所
北区役所3階 会議室
3 参加者等
(1)部会長
佛教大学保健医療技術学部教授 松岡千代 氏
(2)出席者
地域代表者 4人
北区民まちづくり会議委員 4人
地域代表者推薦の地域の担い手(比較的若手の方) 5人
各種地域団体 3人
北区民まちづくり提案支援事業活用経験者 3人
大学生 5人
災害時の避難弱者と関わりの深い団体等 7人
(例:紫野地域包括支援センター,京都ライトハウス,京都手をつなぐ育成会北支部)
社会課題解決等に取り組まれている団体(パトラン京都) 1人
合計 49人(行政職員を含む)
4 概要
キーワード「地域防災」に対して,対象者(高齢者,障害者・難病患者,妊婦・子育て世帯など)における課題や取組アイデアを検討した。
主な意見
※太字は中心的に扱ったテーマ
(1)Aグループ
対象者:高齢者,障害者・難病患者,妊婦・子育て世帯
【課題】
・高齢者の情報は地域がある程度つかんでいるが,障害者は把握できていない。医療機関や行政等は個人情報を地域に流せないため,把握が難しい。
・高齢者の中には避難情報や避難場所などを正確に理解していない人もいる。
・単身の高齢者は日常的にコミュニケーションをとれる相手がいないことも多い。災害時にはそのような人の避難も課題になるのではないか。
【取組アイデア】
・いざ避難となった時には,向こう三軒両隣でいかに助け合えるかが最大のポイント。町内会長が情報を持っていても,距離的に離れていてあまり意味がない。日頃からの隣近所の付き合いが重要だ。
・単身の高齢者世帯を対象とした,大学生による話し相手のボランティアがあれば,高齢者に喜ばれるし,世帯状況等の把握にもつながるのではないか。
・避難途中の怪我や避難所での発病に備えて,多種多様の薬剤をあらかじめ用意しておけば,少しでも安心安全な避難所生活になるのではないか。
・楽只市営住宅の団地再生で防災拠点を設置し,物資を備蓄したり,観光客や外国人も避難できる場所にしてはどうか。
(2)Bグループ
対象者:障害者・難病患者,妊婦・子育て世帯,大学生
【課題】
・障害が原因でコミュニケーションを取りづらい方もおられる。そのために避難所に行くことが難しい場合や,防災訓練に参加できていない場合もある。
・要介護状態の高齢者は障害者と状況が比較的似ているかもしれないが,高齢者は介護保険など,制度が充実しており,災害時はケアマネジャーなどが安否確認等をしてくれるだろう。
・親が関わっている若年の障害者は,いずれ親の高齢化という現実に直面する。親が関われなくなったときにどうするのかが課題。近所が見守るしかないのではないか。一方で障害者世帯は近所との交流が少ないことも課題。
・若年齢層の障害者はネットワークがあるが,高年齢層の障害者は家族以外のつながりが
ないことが多く,家から出ないか,家と職場の往復になりがちである。
・地域で障害者について話し合いを持つ場がない。
・障害者を対象とした福祉避難所は,一般避難所へ避難した後,トリアージ(患者の重症度に基づいて,治療の優先度を決定して選別を行うこと)を経て移送することとなっているため,直接避難することができない。
・一般避難所では,障害の内容によっては,通常よりも広いスペースを必要とする場合等が考えられ,同じスペースで障害者同士が生活することが困難な場合がある。
・避難所での障害者受け入れを考えると,障害者と接するときの基礎的な知識が運営側に不足している。
【取組アイデア】
・障害者が,(一般避難所にいったん避難してからではなく)直接避難できる施設が必要ではないか。
・地域包括支援センターの地域ケア会議は高齢者のケアを想定して設けられているが,障害者を対象とした同様の会議があればいい。
・子どものときから障害者に対する理解を深めていく必要がある。
(3)Cグループ
対象者:妊婦・子育て世帯,大学生,外国人
【課題】
・避難所に乳児用のミルクや紙オムツや,幼児・児童の遊び場があるのか心配。
・避難の際,重たい防災グッズを持ち,子どもを連れて避難できるのか不安。
・助け合える普段の顔の見える関係性が築けていない。助ける人の登録はなかなか難しい。
・避難情報が伝わっていない。
【取組アイデア】
・ある学区では,要配慮者を登録している。妊婦も登録の対象にしてはどうか。
・母子手帳取得の段階で,本人の了承を得た上で,情報を地域に知らせてはどうか。
・大学生に避難所での戦力として活動してもらえるよう,大学での勉強(救急救命講習など)と意識付けをしてもらい,思いのある学生に登録してもらうようにしてはどうか。
・助ける側の人員が足りていない。中学生が戦力になるのではないか。
(4)Dグループ
対象者:大学生,外国人,山間地に住む人
【課題】
・住民票を移していない学生が多いため,行政の避難者名簿に挙がらず本人の安否確認ができない。
・地域の避難場所に避難してきた大学生のマナーが非常に悪かったということがあった。
・同年代だけで固まって活動しがちで,地域との接点がない学生が多い。
【取組アイデア】
・大学は既に,学生の安否確認システムを持っている。緊急時は必要な情報を同システムで共有できるとよい。
・避難所の場所,避難行動の仕方,避難場所での気を付けるマナーなどをわかりやすく発信する必要がある。
・地蔵盆,地域のお祭りなどの地域行事に参加したり,老人会や地域の会合・懇親会に来てもらい,芸や演奏を披露してもらう。
(5)Eグループ
対象者:外国人,障害者・難病患者,その他(ペット同行者,マンション住民など)
【課題】
・外国人は,言葉の問題があり,コミュニケーションが取りづらい。避難所生活でも,言葉の壁が大きな課題になる。
・外国人であっても,いかに地域とのつながりをもってもらうかが基本。特に単身者は孤立しがち。
【取組アイデア】
・災害はいつ起こるか分からない。どこに,いつ避難すればよいか分かるように,避難先については,誰もが分かるサインをまちのあちらこちらに設けるべき。
・障害の内容も様々である。例えば,聴覚障害者向けに,避難所での情報のサイン表示や,駅等における電光掲示版での表示も大切である。
・楽只市営住宅の再整備について,外国人観光客が訪れたいと思える仕掛けが重要である。例えば北区ならではの「食」や「伝統産業」をテーマにできないか。
(6)Fグループ
対象者:山間地に住む人,高齢者,その他(ペット同行者,マンション住民など)
【課題】
・避難情報が,実際の肌感覚と合わない。避難所への一歩が踏み出しにくい。
・川が近いと増水して氾濫することがある。高齢者の多くが避難所に行くのが難しいこともある。
・普段からの地域との交流が大事ということは頭では分かっていても,実際の地域への入り方が分からないという声がある。
・サイクリストに人気があるなど,魅力はあるのだがそれを発信していく力がない。
【取組アイデア】
・近所にどんな人が住んでいるのかを知っておく(持病や家族構成など)。知っていれば,助けに行ったり,避難所に行くときに声掛けできるかもしれない。
・住んでいる人の多くは,自分が居住している学区を意識していない。実態に即して,学区にとらわれずどこの避難場所にいってもよいことにしてもいいのではないか。
・発信力がないという課題に対しては,北区のコミュニティラジオ局「ラジオミックス京都」を活用してはどうか。
お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画連携担当、事業担当、広聴・地域コミュニティ活性化担当、振興担当:075-432-1208
ファックス:075-441-3282