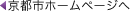サキョウ見聞録 その22 聖護院と近代化の歩み
ページ番号346487
2025年10月9日
今年5月、琵琶湖疏水施設24か所が重要文化財に、うち5か所が国宝に指定されるという、うれしいニュースが飛び込んできました。
明治時代、東京奠都により衰退の危機に瀕した京都のまちの再生と発展を支えてきた琵琶湖疏水施設は、現在も京都市民の生活に不可欠な現役の施設です。
この重要文化財の指定を受けた施設のうち、1914年に運転を開始した夷川発電所本館(左京区聖護院蓮華蔵町)はレンガ造りの重厚な建物で、すぐ傍の夷川船溜(えびずがわふなだまり。夷川ダムともいいます。)から鴨川方向へ向かって勢いよく流れる水流が、水力発電の原動力となっています。船溜を見守るように、疏水建設を推進した第3代京都府知事・北垣国道(きたがきくにみち 1836~1916)の銅像があり、ダム全体を見渡すことができる小さな広場から眺めることができます。

関西電力夷川発電所本館

広場の北側にある北垣国道像と京都踏水会建物
船溜の北側には、多くのオリンピック選手を輩出した京都踏水会の建物が見えます。かつて、夷川船溜は、京都踏水会の前身組織、大日本武徳会遊泳部の練習場となっていて、1960年代頃まで使われていました。先日、踏水会設立130周年を記念し、船溜で40年ぶりに記念遊泳が行われました。
さて、疏水が完成する前のこの地域は一体どんな風景だったのでしょうか。

1868年の聖護院村
幕末に多くの藩邸が立ち並んでいた聖護院村は、明治維新を迎え藩邸が取り壊され畑地に変貌したのち、琵琶湖疏水の掘削ルートがインクラインから仁王門通・冷泉通に沿って直角に折れ曲がる計画が採用されると、その風景が一変します。
明治時代の日本画家、河田小龍が1889年頃に描いた夷川船溜の工事の様子には、現代のような重機は見当たらず、過酷な人力作業をする人々の姿がうかがえます。

河田小龍(筆)「聖護院村工事」(1889年末頃)

河田小龍(筆)「河東工場全図」(1889年末頃)
この一大事業には、多くの地主や企業なども尽力しました。疏水工事のための土地買収に奔走した石田音吉氏もそのひとり、周辺地価の高騰で売りたがらない地主から土地の取りまとめを行った石田は、後に世界的に有名な計量検査精密機械メーカー、イシダグループの創始者となります。今もイシダ株式会社の本社が聖護院山王町に置かれています。
また、平安神宮大鳥居の疏水沿いにある株式会社岡野組は、日本を代表する建築会社と共に疏水建設工事を請け負いました。当時、日本は大型土木事業に対応できる技術力が乏しい中でしたが、幾多の困難を乗り越えながら、日本の技術を結集して大型土木事業を完成させました。
そして、疏水が完成すると、作り出されるエネルギー(水力、電力)を求めて、精米・製粉業、紡績業など多くの工場が疏水周辺に集まってきました。今も製粉工場や、かつて疏水から水を引いて稼働していた大型水車跡などが残っています。
そのうち、三谷卯三郎氏は、水車を用いて精米製粉を行っていましたが、今でも白川沿いには、三谷稲荷社、別名水車稲荷社が建っています。その後、1916年に夷川船溜の北側で三谷伸銅株式会社(現在は南区上鳥羽に所在)を創業し、日本最初の商業用水力発電所の電力を利用した近代工場を建設したといわれています。
ようやく過ごしやすい季節になった初秋の琵琶湖疏水を訪ねて、京都の近代化を支えた産業遺構に思いを馳せてみませんか。
参考文献:
「京都岡崎の文化的景観」京都市文化財保護課
「琵琶湖疏水記念館」常設展示図録」京都市上下水道局
「本家尾張屋日々のこと~河村製粉株式会社インタビュー」HP
「株式会社岡野組ものがたり 歴史」HP
「京都踏水会スイミングクラブ 沿革」HP
「三谷伸銅株式会社企業情報」HP
「琵琶湖疏水 京都の近代化産業遺産完成130年」京都市上下水道局