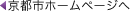サキョウ見聞録 その23 吉田木瓜大明神の剣鉾差し~新たな担い手からみた左京の伝統行事~
ページ番号339599
2025年11月10日
吉田木瓜大明神の剣鉾差し

10月第2日曜日、左京区吉田で行われる今宮社の神幸祭では「剣鉾」と呼ばれる祭具が神輿を先導しながら地域を練り歩く。吉田木瓜大明神の剣鉾差しは、京都市登録無形民俗文化財に登録されている。
吉田山と鴨川の間に位置する吉田地域は、京都大学に通う学生たちや昔からこの土地で商売を営んできた住民たちが混ざり合うエリア。吉田神社今宮社の神幸祭では、剣鉾の差し手たちが神輿を先導しながら巡行し「サイアレ」という掛け声とともに剣鉾の鈴(りん)の音を響かせる。
今回は、新たな担い手として吉田木瓜大明神の剣鉾差し(以下、吉田剣鉾)に携わる野坂智章(のさかともあき)さん、守時英治(もりときえいじ)さん、高島和之(たかしまかずゆき)さん、村中稔(むらなかみのる)さんの4名に話を伺った。
(肩書等は、取材を行った2023年8月当時のものです。)
(動画はこちらからご覧いただけます)
左京区内外の人が関わる吉田剣鉾

野坂智章(剣鉾2年目、システム開発営業職)
吉田剣鉾には、昔からこの土地に暮らす住民だけではなく、進学や仕事で吉田に縁ができた人など様々な人たちが携わっている。神事への参加は保存会メンバーに限られるが、夏祭りなどの地域イベントには左京区外のメンバーも参加可能だ。
大学への進学を機に京都に引っ越してきた野坂さんは、もともとは神奈川県出身。現在は吉田にオフィスがある会社でシステム開発営業をしている。
「大学が京都大学だったので、そのご縁もあるんです。たまたま近所のパン屋さんで『剣鉾の差し手募集』というチラシをみつけて。それまで、実際に剣鉾を差している姿をみたことはなかったので一度見学に行きました。そこで先輩方にいろいろと教えていただいて剣鉾の面白さに触れ、参加することに決めました。」
大きなものだと高さ7m、重さ30kgを超える剣鉾。それを腰に巻いた袋状の差し革に差してバランスをとる。胸から腰を連動させるようにして、鉾先についた招きと呼ばれる剣をしならせて( = 招いて)鈴を鳴らす。綺麗に鳴らすためには強靭な体力と独特な足の動きを必要とする。
保存会のメンバーは、「招きや鈴を綺麗に動かすには最低でも3年はかかる」と口を揃える。最初は重量を支えるだけでも精一杯だが、次第に剣鉾の芯を捉えてなんとか操れるようになっていくようだ。

「まだ綺麗に鈴を鳴らせるわけではないんですが、最初より重たい鉾を差して歩けるようになったり、タイミングを合わせて招けるようになったり、小さいところですけど成果を体で実感できるのが楽しいですね。」
父から子へ受け継がれていく思い

守時英治(剣鉾2年目、保険営業職)
もともと吉田出身の守時さんは、数年前まで全国転勤のある会社で働いていたが、転職して地元に戻ることが決まり、せっかくなので何か地元に貢献できる活動に取り組めたらと考えていたという。
きっかけとなったのは昔から吉田剣鉾に携わっていた父からの提案。江戸時代から続く吉田剣鉾だが、1960年ごろには差し鉾ではなく台車に鉾を乗せて巡行する曳鉾(ひきほこ)の形をとっていた。1993年、差し鉾復活の機運が高まったのと同時に、守時さんの父を含む吉田剣鉾保存会が発足し、同年に剣鉾差しが復活したのだ。
「もともと差し鉾を復活させた時のメンバーに父がいたことは知らなかったんです。地元に帰って、父といろいろと話している中でそのことを知って、剣鉾に興味をもちました。自分も地域に貢献していく活動がしたいなと思って参加することを決めました。」

今年剣鉾の差し手2年目となる守時さんは、ベテランの差し手たちに教わりながら剣鉾差しの基礎を身につけている段階。10月に行われる今宮社の神幸祭に向けて、差し手たちは約2週間、午後7時から9時まで毎日練習しながら技術を身につけていく。
夜間の練習は剣鉾の先端を目で見て確認することが難しく、より一層全身の感覚を研ぎ澄ませなければならない。若手が本鉾と呼ばれる一番大きな鉾を差す際には、空気が張り詰め、その場にいる全員が神経を集中させる。

練習後は軽くお酒を酌み交わしながら、ざっくばらんに話す交流の場。ベテランも若手も分け隔てなく、剣鉾の背景や歴史、地域との関わりについて熱心に語り合うシーンも見られた。こうして、技術だけでなく地域に対する思いが継承されている。
深くて長い剣鉾の道

高島和之(剣鉾4年目、建築士)
左京区で設計事務所を構えている建築士の高島さん。断続的ではあるが、剣鉾を初めて4年になる。

「うまくいかないとき、練習に来るのもあまり気が乗らないときもありました。バランスを崩して自分ごと持っていかれそうになる恐怖心があったり。ただその段階を乗り越えるとだんだん軽くなってくるんですよ。あまり重さを感じなくなって心にゆとりができてくる。少しずつできるようになると、楽しくなってきますね。」
はじめはすぐに鳴らせると思っていた剣鉾だがその道は想像よりも険しかったという。差し手としては初参加となる2023年の神幸祭。高島さんは、地域の人たちの前で初めて剣鉾を披露する瞬間を前に「とにかくしっかり鈴を鳴らしたい」と意気込む。

「巡行の時には、地域の方が家やお店の前に立って剣鉾差し迎えてくださるんです。その人たちの前で、形はどうあれしっかりと鈴を鳴らすことができたらいいなと思います。」

子どもたちの印象に残る鉾差し

村中稔(剣鉾8年目、銭湯経営)
銭湯業を営む村中さんは、剣鉾に携わるようになって8年目。小さい頃からこの地で育った村中さんには、中学生の頃に聞いた剣鉾の鈴の音が記憶にあったそうだ。
「12歳の時に、家の前にきていた剣鉾の鈴の音を綺麗やなと思って、眺めながら聞いていたのが思い出にあったんです。当時、すぐに剣鉾に関わることはなかったんですけど、8年前に地域の行事で現保存会の会長の中川さんに声をかけてもらって。それがきっかけで剣鉾に関わるようになりました。」
力には自信があった村中さんだが、最初の頃はうまく鉾がさせずに悔しい思いをしたこともあるそうだ。

「吉田剣鉾は、女性も鉾を差すんです。中には大人の男性が差す鉾を綺麗に鳴らしている女性の方もいて。ぼくは力に自信があったので、絶対に鳴らしたろうという意気込みでいったら、うんともすんとも鈴がならなくて。すごい悔しかったですね。」

それから8年間、村中さんは吉田地域だけではなく京都市内で剣鉾差しを行っている他の地域にも出向いて剣鉾の技術を習得していった。今では中学生や高校生に剣鉾を教える中堅としての役割も担っている。

そんな村中さんは、吉田剣鉾を次世代に受け継いでいくために、自身の経験を思い浮かべながら「小さい子どもたちの印象に残る鉾差しをしていきたい」と語る。

「剣鉾の差し手の年齢層は、下は中学生から上は70代の方まですごく幅広いんです。ぼくたちはちょうど真ん中の年代なので、あと数十年したら世代が変わって自分たちが中心になってやっていかないといけない時代がくる。だから今は必死に練習しています。偉そうなことは言えないですけど、小さい子たちに印象付ける鉾差しをしていきたいですね。」

昔、吉田剣鉾差しは地元の男性のみが担い手として参加する伝統行事だった。今では老若男女が参加して、アットホームな雰囲気の中で剣鉾の技術を磨き、その歴史や思いを継承している。
吉田剣鉾は、様々な背景をもつ人々が、同じ地域の一員として行事に関わることで、地域とともに変化し、長く愛され続ける文化になっていく。