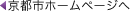サキョウ見聞録 その19 洛北 お盆の流し団子
ページ番号344403
2025年8月22日
お盆にはご先祖をお迎えし、おもてなしし、送ります。
家族や一族が集まり、この世にはもうおられないご先祖や故人が、そこに帰ってきてくれたような何日かを過ごして、再び見送る、そんなお盆を過ごされるみなさまも多いのではないでしょうか。
それにも地域で、そしてご家庭で独特な、多様なやり方があります。
左京区の岩倉にお住まいで、洛北地域の伝統行事にとても詳しい中村治・大阪府立大学名誉教授にご案内いただき、「流し団子」という独特のお供えものを作っておられるお宅を訪問させていただきました。

訪問させていただいたのは、岩倉の佐藤隆夫さんのお宅。
佐藤隆夫・順子さん夫妻が温かく迎えてくださいました。
それにしても立派なお宅。豪壮な農村の旧家のつくりで、パッと目に入るのはおくどさんですが、台所に井戸があったり、お宅の探訪だけでも、ひとつのお話が書けそうなくらいです。

佐藤隆夫さんと立派なおくどさん
手提げ燈籠というものも見せていただきました。「火の用心」、ではなく「町内安全」と書かれています。町内に愛宕燈籠があり、毎日火を灯す際に使ったものだったそう。


当番に当たった家が手提げ燈籠の中の菜種油に火をつけて、その火で愛宕燈籠に火を点ける。今は手提げ燈籠には火を灯してはいないのですが、近所の6軒で手提げ燈籠を回し、愛宕燈籠に火を灯しておられるのだそうです。
佐藤さんのお宅のお盆の行事について、お聞きしました。
岩倉ではお墓参りを8月1~7日の間(町によって日が決まっていました。)に行い、流し団子を供えました。かつては、岩倉でご先祖さんをお迎えしていたと思いますが、先代の頃には、ご先祖をお迎えするために、10日に六原の六道珍皇寺にお参りして、高野槇(こうやまき。精霊を枝につけて家に導いたと言われている。)を持ち帰りました。8月13日に野菜や果物を仏前にお供えをし、14日にお寺さんが棚経に来られます。
14日のお供え物としては、朝はおはぎとアラメを、昼はそうめんを、夜はこまごま(かんぴょう、なすび、こんにゃく、ゴボウ、ニンジン、おあげを炊いたもの)を供えます。
この日は8月13日で、お仏壇を見せてくださいました。お供えは佐藤さんのお家でとれたもの。花は久多の北山友禅菊だそうです。

お仏壇にお供えされている、この三角形のものが「流し団子」です。普通の年には、これを13日~15日にお供えせず、お墓参りの日に墓や仏前にお供えし、墓参りから帰ってから、みんなで食べ、談笑するそうですが、この日は、取材用にお供えしてくださいました。
実際に作っておられるところを見せていただきました。

佐藤順子さん

おくどさんでお湯を沸かして、蒸します。
材料は、小麦粉、片栗粉、砂糖、ゆで小豆。それらを水で練ったものを布巾に流し、20分間蒸します。
流し団子はほのかに甘く、片栗粉のおかげでプルンとした触感でした。

中村先生によると、松ケ崎丘陵より南側は野菜を栽培しており、高く売れていたが、岩倉ではそういった現金収入がなかった。しかし小豆を作るゆとりはあった。それで、小豆を食べることに喜びを見出していたのではないか。小麦や小豆は自家用が前提で、ご先祖をお迎えするための流し団子を作るゆとりとこだわりがあったのではないか、といいます。
また、流し団子は岩倉だけでなく上高野や松ケ崎、一乗寺でも作っているお宅があったそうです(修学院では竹の皮に流す丁稚羊羹を作ったそうです)。
岩倉にある、お盆の独特のお供え物について紹介させていただきました。
みなさまのお住いの地域には、そして各家にはそれぞれのお盆のやり方があると思います。そういうものを見ていくと、また味わい深いものかもしれません。
この記事を書いた人
矢野裕史(左京区役所 左京の魅力づくり推進・山間地域振興課長)
左京区北部の花背在住の、左京区民歴20ウン年の自称左京ファン。冬は花背の山でシカを獲ったりしてます。