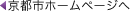サキョウ見聞録 その20 久多の花笠踊~移住者からみた左京の伝統行事 ~
ページ番号339598
2025年9月5日
8月24日の夜、京都市左京区の最北端・久多で行われる久多の花笠踊は、造花でかざった燈籠に火をともし、室町小歌のしらべに合わせて踊る。令和4年11月にユネスコ無形文化遺産に登録された。
京都市街から車で1時間半の山間に位置する久多。人口100人に満たないこの集落に、8月24日の夜は花笠踊を一目見ようと各地から多くの人々が集まる。
花笠踊で使われる造花は、各町ごとに「花宿」と呼ばれる民家に寄りあって、およそ1週間にわたって製作される。その工程の多くが地域の方々によって口伝えで受け継がれてきた。その中に飛び込んで、住民たちと一緒に花笠踊に携わる人物がいる。久多に移住して3年目の料理人、田邉賢司(たなべ・けんじ)さんに話を聞いた。
(肩書等は、取材を行った2023年8月当時のものです。)
(動画はこちらからご覧いただけます)

田邉賢司(料理人、北部山間かがやき隊)
地域おこしがきっかけで久多に移住
田邉さんが久多に引っ越してきたのは2021年のこと。京都市山間部の地域おこしを目的とした「京都市北部山間かがやき隊員」の久多担当として移住してきた。現在は、地域住民と一緒に自治や伝統行事の運営に取り組むかたわら、料理人として出張料理やレストラン開業のための場所探しを行っている。

もともとは久多の南に位置する左京区岩倉の出身の田邉さん。小さい頃から実家の蕎麦屋を手伝い、次第に料理の道を志すように。これまでに、京都や沖縄で懐石料理やフランス料理など、料理人として幅広い経験を積んできた。

久多には鮎やアマゴなどが生息する美しい渓流や、ゼンマイ、わらび、きのこなどの豊かな山菜が採れる山々が広がる。田邉さんは「いつか地元に近い山間部で自分のレストランを開きたいんです」と話す。
「人の雰囲気や土地の空気感を含めて体験するために、その土地に暮らしてみた方がいいと思って。地域の方が郷土料理をつくっているのをみて勉強させてもらったり、自分でつくった米や野菜を使って料理をふるまうこともあります。」

伝統行事を通じて地域に溶け込む
縁もゆかりもない中でスタートした久多での生活だったが、移住してから地域に溶け込むまでは早かったそう。そのきっかけになったのが花笠踊などの伝統行事だった。
花笠踊の準備は、毎年8月上旬ごろから行われる花笠製作から始まる。5つの集落でそれぞれ花宿と呼ばれる家を決め町内の人々が寄り合い、1週間に渡って製作される。8月24日の夜、5つの集落が上の組と下の組に分かれ、完成した花笠に火を灯し、久多にある3つの神社を巡行しながら踊りと花笠を奉納して回る。
「ちょうど夏頃にきたので、花笠踊や”松上げ”という行事の準備を通して、地域の人に顔を知ってもらうことができたと思います。」

花笠の造花製作は、細かな模様に和紙を切り出したり、1枚1枚の花びらの形を手作業で整えたりと長時間に渡って集中力が必要とされる作業だ。苦戦しながらも「今年はわりとうまくできてると思います」と笑顔で話しながら町内の住民たちと作業に取り組む。

「造花をつくる作業は、和食に似てるところがあるんです。細かい剥きものをやっていたときの感覚を思い出しながら。といっても、失敗もよくしますけどね。作り方のマニュアルがあるわけじゃないので、町内の先輩たちにも確認してもらっています。失敗する度に『あ、ここは去年も間違えていたな』みたいな。」

田邉さんからみた花笠踊の魅力
花笠踊本番の24日午後5時すぎ、保存会の浴衣に着替えた田邉さんたちは花宿に集まっていた。花笠の最終調整を終えた後は、各町ごとに寄りあって、お酒を飲みながら本番に向けての英気を養う「出立ち」と呼ばれる慣例のためだ。

「1年に1回の行事なんで、みんなお酒を飲んで楽しむんです。僕は去年飲みすぎてしまって大変だったので、今年は控えめにしようかな。」
花笠踊には「より棒」と呼ばれる重要な役割があり、2人で棒を打ち合うことで花笠踊の始まりの口火を切る。踊りが始まる前ともあって、参加者や見学者が固唾を飲んで見守る、祭の中でもとくに緊張感が漂うシーンだ。

出立ちの和やかな雰囲気のなか、先輩たちから「今年は、田邉くんがより棒役だね」と声をかけられ「いえいえ」と恐縮するもいつの間にかその大役は田邊さんに決定。急きょ、庭先で練習が始まった。突然の抜擢に緊張した面持ちだった田邉さんだが、先輩たちから口々にアドバイスをもらい、なんとかより棒の動きを習得。本番の場所となる志古淵神社への移動道中も、参加者たちの集まりから少し離れた片隅で何度も繰り返しその動きを身体に叩き込んでいた。

花笠踊は上の宮神社をスタートしてから、巡行や各所での歌・踊りの奉納を合わせると5時間以上続く長丁場の行事だ。「ろうそくのついた花笠を持ってかなり長い時間、歌に合わせて同じような動きをし続けるので、時間が経ってくるとバグってくるというか、一種のトランスのような状態に入るんですよ」と田邉さん。その時の独特の空気感も花笠踊の魅力のひとつだと話す。

午後10時前、最後の目的地である志古淵神社に到着した田邉さんはより棒を披露。「こういうのは、失敗した方が盛り上がるんやで」と先輩方に冗談を言われながらも、見事なより棒をみせ、境内は歓声に包まれた。

花笠踊を引き継ぐためにできること
人口の減少が進む久多では、町によっては花笠踊の作り手や、当日、花笠を持つ人が少ないといった話も出ることも。次世代に花笠踊を引き継ぐためには「記録を残し、発信をしていくこと」が大切だと田邉さんは語る。

「花笠踊のように地域で古くから続いているコミュニケーションの場を次世代に残していくことって大切だと思うんです。だから、花笠踊のことやこの地域のことを発信することで、移住者や行事に興味をもってくれる方が少しずつでも増えて、ながく継続していけたらいいなと思います。」
田邊さんのかがやき隊としての任期は3年。2024年春で満了し、その後、現在は久多を離れている。伝統行事開催という地域活動を通して地域との関係性を築きながら自身のキャリアも確立させていくことは決して容易ではない。しかし、一時的な関わりではなく住民たちと同じ目線で取り組み、築いた関係性の中でしか見えないものがある。