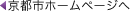サキョウ見聞録 その17 熊野神社界隈~鴨東の賑わい
ページ番号342894
2025年10月6日
毎年4月29日、東山丸太町北西に鎮座する熊野神社では、華やかに神幸祭が催されます。行列を先導するのは、氏子区域の子供たちが時代装束を身に着けて、笛、太鼓を演奏しながら練り歩く熊野神社少年勤王隊。神輿とともに、熊野神社が守護する聖護院門跡へ向かい、門主のご祈祷を受け、奉納演奏された後、氏子区域である川東学区の各町内へと巡行します。
巡行前に本殿前に整列する熊野神社少年勤王隊の皆さん

現在の熊野神社前
熊野神社は、811年に紀伊国熊野から熊野大神を勧請したのに始まる由緒ある神社。1090年には、聖護院が創建され、熊野神社はその鎮守社とされました。
この熊野神社界隈は、昔、どのような地域だったのでしょうか。1864年発行の花洛名勝図会には、前回サキョウ見聞録で取り上げた「大文字送り火」が載っています。その一部を拡大してみると、鴨川に架かる丸太町通橋の奥に鳥居があり、見物客でたいそう賑わっているのがわかります。その鳥居の先には、聖護院の森に囲まれた熊野権現社(熊野神社)があります。

平安京都名所図会データベース(国際日本文化研究センター)抜粋
江戸時代、鴨川東側は、京都市中に近い南部地域から賑わいを見せ、享保年間に祇園新地・七条新地・上七軒と並ぶ二条新地が生まれ、聖護院の森は梅や桜の名所として、夏は納涼の場として賑わいました。当時、熊野神社も八重桜の名所だったそうです。熊野神社西門前には旅籠や茶屋などが多く並び、また、幕末の志士たちに大きな影響を与えた詩人の梁川星巌や幕末の女流歌人の太田垣連月、明治・大正期の文人画の大家富岡鉄斎など文化人が居を構えました。

富岡鉄斎が残した熊野神社西門前の絵図

川端丸太町上る北東に石碑が建つ 江戸時代後期の漢詩人 梁川星巌邸跡
また、この一帯は、幕末に京都が政治の中心であったことから諸藩の動きが活発になり、彦根、越前などの藩邸が林立することで、これまでにない賑わいを見せました。

1868年の聖護院村 明治に入ると藩邸が取り壊され、鴨東運河(琵琶湖疏水)が開通することになる。
東山二条西から北へ続く熊野道 広い幅員は東山通が拡幅される前の大通りの名残か
さらに北上すると熊野橋、熊野神社西側の道につながる。
大正から昭和にかけて市電の開通や東山通が拡幅されると、この界隈は、交通の要所となり、熊野神社の社域も現在のようになったのだそう。
都会的な街並みが続く現在の熊野神社前交差点
参考文献:
「京都岡崎の文化的景観」京都市文化財保護課
「京都左京あゆみとくらし」宇野日出夫著
「左京区誕生七十周年記念誌 左京区七十年のあゆみ」左京区誕生70周年記念事業実行委員会
「琵琶湖疏水記念館」常設展示図録」京都市上下水道局
平安京都名所図会データベース(国際日本文化研究センター)