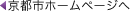サキョウ見聞録 その16 大文字送り火~奉仕を経験した学生からみた左京の伝統行事~
ページ番号339595
2025年6月17日
8月16日に京都市左京区に位置する東山如意ヶ嶽の中腹(仮称大文字山)で行われる伝統行事「大文字送り火」は、旧浄土寺村の村民によって保存継承されていたが、近年に至って、法人化された特定非営利活動法人大文字保存会(以下、大文字保存会)により保存継承されている。
左京区内には7つの大学があり、大文字送り火には長年にわたって多くの学生がボランティア奉仕者として関わってきた。8月16日の点火当日までの事前の準備作業や送り火実施後の林内清掃作業など、年間を通して様々な作業に参加する学生ボランティアは行事に欠かせないものとなっている。
1度きりの参加という学生も珍しくない中、複数年にわたり熱心に関わり続ける学生たちもいる。
今回は、学生ボランティアとして大文字に関わる同志社大学大学院博士課程の得能司さんと、京都芸術大学3回生の山田恵美さん、そして大文字保存会の理事長である長谷川英文さんに、送り火に対する思いを伺った。
(肩書や学年等は、取材を行った2023年8月当時のものです。)
(動画はこちらからご覧いただけます。)

得能 司(同志社大学大学院博士課程)

山田 恵美(京都芸術大学3回生)

長谷川 英文(大文字保存会理事長)
ボランティアを通して伝統の重みに触れる
得能さんは、大学院で地域コミュニティの継承について多角的に研究する地域社会学を専攻。ゼミ活動として大文字送り火に関わるようになり、2023年が3年目だ。

送り火が行われる当日の学生ボランティアの役割は、朝8時から行われる護摩木の志納受付のサポートや火床を組むために必要な物資の運搬など。銀閣寺裏手の登山口から山頂近くの火床まで約2Kmの往復に加え、「大」の中央となる最も大きな火床である「金尾(かなわ)」から全部で75基ある各火床への資材バケツリレーなど、炎天下の中で朝早くから夜遅くまでかなりの体力を使う。

得能さんは保存会と連携をとりながら同志社大学の学生ボランティア10名以上をまとめつつ、必要であれば他大学の学生にも指示をつなぐ。各所に学生たちを配置したり、運搬する資材を率先して準備するなど、学生ボランティアたちの中枢となる役割を担っていた。3年目となり、保存会にも顔見知りが増え、学生だけではなく保存会理事長からの信頼も厚い。

得能さんと話す中で何度も出てきたのが「とにかく、保存会の方々に迷惑をかけないようにしたい」という言葉だ。
「僕たちはあくまでも参加させていただいている側。いくら僕たちがお手伝いしたいと言っても、必要ないと言われたら参加できない立場なんです。僕たちが参加することで、かえって保存会のみなさんに迷惑をかけてしまったら、後輩たちは来年から呼ばれなくなってしまうかもしれない。そのことは、学生全員に伝えた上で参加するようにしています。」

例年、慣れない登山や炎天下での作業で、熱中症や体調不良を訴える参加者が数人は現れるという。送り火当日は35度を超える猛暑日。火床へ向かう登山の途中、体調不良を訴える学生に得能さんが下山を促すシーンがあった。
参加する学生たちの安全に配慮することは、保存会が送り火を滞りなく完遂するために得能さんが担う、最も重要で基本的な役割だ。「学生たちに間近で送り火を経験させてあげたい」という思いはありつつも、決して無理はさせず、終始、積極的に水分補給や休憩を促す声かけを行っている姿が印象的だった。

「1年目から2年目にかけては、送り火の前後だけではなくて、保存会のみなさんが年間を通してずっとこの日のために準備をしてこられていることを知りました。3年目の今は、伝統の重みや、それをお手伝いさせていただいていることのありがたさを改めて意識して、より一層ご迷惑をかけてはいけないなと思うようになりましたね。」

8月16日、大文字山に火が灯されるのはたった数十分。しかしその裏には、毎年安全に送り火を実施するための膨大な労力がかけられている。送り火当日だけではなく、これまで継続的に関わってきた得能さんだからこそ、保存会への配慮やリスペクトが人一倍大きいのだろう。
将来的には「できればずっと関わっていきたい」と話す得能さん。学生たちに対しても、このボランティアの経験が地域と関わるきっかけになることを願っているそうだ。

「今回参加した学生たちが、社会人になっても京都に残ったら、引き続き送り火のボランティアに来たいって言ってくれるようになると嬉しいです。京都に残らなくても、新しい場所に移り住んだり、地元に帰ったりした先で、大文字での経験を思い出してその地域の行事をお手伝いしようってなってくれるといいなと思います。」
熱気、気迫。山の上から「大」を見て感じたこと
大文字送り火は、これまで長年にわたって保存会員やその親族の男性のみによって受け継がれてきた。学生や社会人ボランティア、女性が参加するようになったのは2000年以降のこと。
京都芸術大学3回生の山田さんは、サークル活動の一環で大文字送り火のボランティアに関わっている。得能さんと同じく、大文字送り火のボランティアは2023年で3回目だ。

せっかく京都の大学に来たのだから京都らしい伝統や文化に関わりたいと思って入ったボランティアサークル。明るくハキハキとした姿勢を買われて2回生から副部長を務め、多数の学部生や留学生から構成される約40名の部員をまとめている。

過去2回のボランティアは山の麓から撮影係としての参加だったため、実際に点火が行われる火床に上がるのは今回が初めてだった。
「実はこれまで大文字送り火って『京都らしいなあ』くらいの印象しかもってなかったんです。
今回初めて、実際に火床まで登って点火の様子を見させていただくと、下から見る『大』と、近くで見る『大』は迫力が全然違って驚きました。とにかく人の思いも、火も、すごく熱かったです。現場は『よっしゃー!おらーっ!』っていう気迫があってすごくかっこよかったですね。」
保存会のメンバーと一緒に山へ上がって準備を進める中で、京都の伝統に対する印象も変わっていったという。

「京都の伝統行事っていうと、堅苦しい人たちが難しい顔をして黙々とされてるイメージだったんですが、今回、一緒に山に上がってみて、全然そうじゃないと知りました。みなさんとてもアットホームで温かいなと。地域一体で運営されていて、こうやって京都の伝統が守られているんだと気づきました。」

自身の印象の変化を踏まえて、後輩に伝えたいことがある。
「ネットではわからない、本当にリアルな体験をさせてもらってることがありがたいなと思います。後輩たちも、せっかく参加しているので貪欲にたくさんチャレンジしていってほしいなと思いますね。」

地域に入って人を知り関わり方を見だす
大文字保存会理事長の長谷川さんは、学生に対して「できるだけ多くのことを見て、自分のものにしてもらうこと」が重要だと話す。

「京都人って裏表があって...っていうイメージもあるけど、本気になって関わってくれる人に対してはすごくオープンだと思います。僕は、伝統行事はこれまでの継承の方法だけではなく、時代の変化に合わせて、地域の中で生かされていくべきというのを常に意識しています。だから学生ボランティアでも現場に来てもらって、できるだけ多くのことを見て吸収してもらう。それをまたどこかに生かしてもらえたら嬉しいんです。」

これまで長年にわたって京都の伝統行事に携わってきた長谷川さん。これまで京都の伝統行事は、その多くがその土地に昔からゆかりのある住民で組織される保存会によって受け継がれてきた。しかし、近年は担い手の半分以上が新しくこの地に暮らし始めた人によって行われているケースも少なくないと言う。

「どんな地域でも、その地に生まれて消えていく文化がある。そこに関わってみることで、例えば自分が育った地域のことがより深くわかるかもしれない。他の地域にいったときも、表面的な伝統や文化ではなく、そこに携わる人を見て、自分がその中でどう関わっていけるかを考えることができるといいんじゃないかなと思います。」
大文字送り火では、過去に参加したボランティア同士が、長年にわたり自主的にコミュニケーションをとっているそうだ。長谷川さんの元には、送り火前になると「今年は誰々が手伝いにいきますよ!」と毎年連絡が入る。

「僕が知らない間に、過去のボランティア同士で連絡を取り合っていてずっと関係が続いてるっていう何か不思議です(笑)ただ単に手伝いをするんじゃなくて、一緒に汗をかきながら大文字送り火をつくり上げることで、互いの関係性の中になにか生まれて、その繋がりが社会人になっても残り続けるんかな。」

笑顔で大文字送り火について話す3人は、保存会会長とボランティアという立場の違いを感じさせない家族のような雰囲気だった。無事、今回の送り火が終わったのも束の間、翌月からはまた次の送り火のための準備が始まる。伝統の重みだけではなく、そこに携わる人の思いに触れた学生たちの経験は、きっと卒業後も大きな支えになるに違いない。