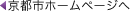サキョウ見聞録 その13 寺子屋KUMAN(川東学区)
ページ番号337699
2025年3月27日
1月某日。川東学区自治連合会集会所にて、「寺子屋KUMAN」の活動の様子を取材させていただきました。
「寺子屋KUMAN」とは、東竹屋町会長の里見さんと、東竹屋町内にある京都大学熊野寮の寮生が運営する、子どもたちに勉強をおしえたり、一緒に遊んだりする無料の塾です。
KUMANは約4年前に里見会長が、地域住民でもある熊野寮生らと関わる中で、「熊野寮と町内で何か面白いことを一緒にやろう。」と声をかけ、「地域の子どもに勉強を教えたい。」という寮生の思いを採用し、一緒に動いたことから始まりました。
「元々は子ども塾として勉強を教えることがメインでしたが、今は勉強しに来るだけでも良いし、遊びに来るだけでも良いです。とても自由でアットホームな場所です。」と里見会長。まさにその言葉通りで、この日も子どもたちが来ていましたが、宿題をする子、外で鬼ごっこをして遊ぶ子など、各々自由に過ごしていました。
ちなみに里見会長は、「おもろいことが好きやねん」が口癖なぐらい、普段から楽しい企画を考えておられ、KUMANで行われる夏祭りなどのイベントの際は、会長自ら子どもたちが楽しめる遊び道具を作られるそうです。しかも、電子工作が得意で、もぐらたたき形式のゲームなど、クオリティが非常に高いものを制作され、見る人全員びっくりされるのだとか。
また、町内で何が起こっているのかわかるように「東竹屋町だより」という町内広報誌の企画、発行もされています。こちらは地域の活動の情報はもちろん、熊野寮生が担当する記事や、会長と寮生による川東学区周辺のグルメを紹介するコーナーがあるなど内容も充実しています。

会長手作りゲーム。光るボタンを押して高得点を狙います!
KUMANの運営に携わる熊野寮生は、「子どもたちの楽しそうな姿を見ると、KUMANがみんなの居場所になっていると実感でき、とてもやりがいがあります。」とお話しくださいました。一方で、子どもだけでなく、多くの方に気軽に利用していただきたいとの思いで、KUMANの京大生たちで地域のふれあいサロンや地域行事の実行委員会にも参加されているそうです。「熊野寮は、怖そうといったイメージが先行しがちですが、地域の行事などに参加し、顔の見える関係性を築くことで、熊野寮がどういう意義を持って寮運営を行っているのかが伝わりやすくなると感じています。「実際に寮生と話してみたら印象が変わった。」という声もありました。」とのことで、寮生の皆さんは、地域とのつながりをとても大切に考えておられることも伺えました。
この日、寮生も数名おられましたが、外で遊ぶときは全速力で子どもを追いかけ回し、勉強を教えるときは複数人で問題を考えるなど、本気で子どもたちの相手をしていました。「子どもが近所のお兄ちゃんお姉ちゃんと過ごす」という感じでとても微笑ましい雰囲気でした。(筆者も皆さんに混じって小学生の宿題を本気で考えていました。)

取材がひと段落し、中の様子を伺っていると良い匂いがしてきました。KUMANでは月に2回食事会があり、この日はカレーでした。自分でごはんをよそってルーをかけてもらって、みんなで一緒に食べる姿を見て、筆者はほっこりした気分になりました。



みんなでご飯、の中で遊ぶチーム。本当に自由!
KUMANの活動に関する情報はすでに広まっており、地域の方が子どもたちのために大量のお菓子をくださったこともあるそうです。また、高齢の方も数名勉強しに来られているそうで、誰でも利用できる場になりつつあります。取材時も、料理を作りに来られた方や、お迎えついでに一緒に食事会の手伝いをされていた方もおられ、いろんな方によってKUMANは支えられ、作られていると感じられました。

熊野寮の食堂で働いておられる方がお手伝いに!とご飯が待ちきれない小学生。
左京区の魅力について、「自然があって都会過ぎない環境の中で、地域で自由に活動することを受け入れてくれる雰囲気を感じられるところが、左京区のもつ魅力だと思います。」と里見会長はお答えくださいました。寮生も、「熊野寮は学生自身で運営する自治寮であるからこそ、KUMANの運営も自分たちで自由に考え、地域の方と一緒に活動を続けられている。」と大きく頷いておられました。
「ここで育った子どもたちが、また戻ってきてくれたら嬉しい」
これは里見会長らがおっしゃった言葉です。KUMANがこれからも誰もが集える場所になるよう、熊野寮内でも活動が代々受け継がれているとのこと。取材日に遊びに来ていた子どもが今度は教える立場で戻って来る、なんて日が来ることを筆者も個人的に楽しみにしています。
取材を通して、子どもたちが楽しく過ごす様子を実際に見て、里見会長や寮生の思いを聞くことで、KUMANがあることも左京区の魅力の1つだと筆者は思いました。この記事が1人でも多くの方の目に触れられ、活動の輪が広がり、「寺子屋KUMAN」がみんなの居場所であり続けられることを願っております!