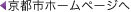区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(中京のすごい人!)三若神輿会 会長 近藤浩史さん、幹事長 吉川忠男さん part2
ページ番号344349
2025年8月15日
三若神輿会 会長 近藤浩史さん、幹事長 吉川忠男さん(令和7年8月14日更新)
京都の夏の風物詩、祇園祭。日本三大祭の一つということもあり、地元の方々だけでなく、国内外から観光客が集まり、大きな盛り上がりをみせました。今回は、先日取材させていただいた「三若神輿会(さんわかしんよかい)」の男衆のみで作る「弁当打ち」や、昼間の山鉾巡行で浄められた氏子地域を神輿が渡御する「神輿渡御」の様子を取材しました。
7月に入ると三若神輿会の活動は忙しくなります。鳴鐶(なりかん)という神輿の担ぎ棒につける金具を磨き、縄の傷みを確認して安全に渡御が行われるように準備・点検作業が行われます。さらに弁当の準備も始まります。
渡御の合間に輿丁らが食べる「みこし弁当」は、神輿を担ぐ輿丁自らが精進潔斎をして、神幸祭・還幸祭の当日に仕込む弁当で、江戸時代から続いています。
まず、7月上旬に会所に約50名が集まり、弁当を包む約6,000枚の「竹の皮」の裏表を絞った布巾で拭いて乾燥させておきます。
お弁当を包む竹の皮のお手入れの様子
神幸祭・還幸祭当日は、朝5時から会所に約70名が集まり、午前10時ごろまでに弁当を作ります。今年は17日に2,800個、24日に3,600個の弁当を作りました。四角い木型に入れて固めた白飯を竹の皮にたたきのせるその所作から「弁当打ち」とも呼ばれています。それにゴマをかけ、沢庵と梅干を添え、藁紐で締めます。木型は、白飯を詰めやすくするため、先に水で濡らしますが、その水に塩を少し入れます。
塩の量は当日の天候、気温、湿度などに合わせて調整して、作ってから食べるまで半日以上を常温で保つと、ひときわ味が引き立つという重要なポイントもあります。

しゃもじと一人前の木型

一人前のたくあんを測るものさし
弁当打ちの様子
弁当打ちの様子
神輿の屋根の上に飾る稲の穂は、京丹波町「神饌田(しんせんでん)」で収穫されたもので、神幸祭・還幸祭の前日に届けられます。「お稲さん」と呼ばれ、熱さましにも効果があるといわれ、輿丁や氏子などに1本ずつ配られます。
還幸祭の日に作られた「みこし弁当」は、神輿渡御に寄付された地元氏子約700軒に配られますが、この「お稲さん」も1本つけられます。

神饌田で収穫された稲の穂「お稲さん」
神幸祭は、7月17日に前祭りの山鉾巡行の後、八坂神社から素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの祭神を神輿に乗せて、四条御旅所にお連れし、そこで鎮座されます。神々は7日間、洛中におられ、24日に後祭りが行われます。
後祭りの山鉾巡行の後、夕方から還幸祭が行われ、神々は神輿に乗って、氏子地域をめぐり、八坂神社にお還りになります。中御座神輿、東御座神輿、西御座神輿と、それぞれ経路は異なりますが、中御座神輿は、御旅所を出たあと、大政所御旅所にも立ち寄ります。大政所御旅所は、烏丸通仏光寺下ル東側にあり、現在は、小祠があります。かつては八坂神社の御旅所で神輿の渡御が行われた場所ですが、天正19年(1591年)、豊臣秀吉によって御旅所は現在の四条寺町に移されました。
吉川幹事長(左)と近藤会長(右)
(大政所御旅所)
輿丁に指示を出す吉川幹事長
中御座神輿が京都三条会商店街の又旅社についたのは、19時半ごろでした。四条通から大宮通を通り、祇園祭発祥の地である神泉苑拝礼後、京都三条会商店街に神輿が到着すると、商店街の方々から大きな拍手がおこりました。店先で、椅子に座って待っておられる高齢者の方、お孫さんを抱いて神輿の到着を待つおばあちゃんなど地域とともにある三若神輿会の輿丁の方々への応援が温かく感じられました。
神輿渡御の様子
(四条大宮)
神輿渡御の様子
(京都三条会商店街)
神輿渡御は、約890人の輿丁の皆さんが白い法被と白い地下足袋をまとい、2トンの神輿を交代で担ぐ神事です。約50名の輿丁が「ホイット、ホイット」の掛け声とともに神輿を担ぎ、数十メートルほど進むと次の人に交代し、それを繰り返しながら進みます。要所では神輿を高く掲げる「差し上げ」を行いますが、商店街の道幅が狭く、窮屈に感じられるほどの迫力は圧巻です。重さも大変でしょうが、その状態をつなぎながら、それでもなお交代で担いで運んでいくことの大変さを目の前で見せていただきました。そしてこのように大変なご苦労をしていただきながら、神様が目の前に来てくださったのだと感じると、自然に感謝し、拝礼をしてしまいました。
三若神輿会が奉仕している中御座神輿(又旅社前)
京都の三大祭りのひとつ祇園祭は、特に山鉾巡行がメインのように思われていますが、神輿渡御を見ていると、八坂の神様は地域とともにあり、なじみの地域をめぐることがとても大事な神事であることをひしひしと感じました。
<詳細情報>
三若神輿会
場所:中京区今新在家西町11
電話番号:075-841-2344
Facebook:https://www.facebook.com/sanwakamikoshikai/![]()
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182