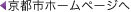区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(伝統産業)京都和傘屋 辻倉
ページ番号333530
2024年11月8日
京都和傘屋 辻倉(令和6年11月8日更新)

元禄3年(1690年)創業の京都和傘屋「辻倉」は、四条河原町上る東側のビルにあります。7階に店舗、5階には体験工房を備えており、落ち着いた趣で、和傘を手に取ることができます。今回は、代表取締役社長の木下基廣(きのした もとひろ)さんにお話を伺いしました。
初代の辻倉甚助(じんすけ)氏は、関ヶ原の戦いで敗れた浅井長政(あざい ながまさ)の家臣であり、戦いののちに、現在の建仁寺付近(東山区大和大路通四条下る)で「山城屋(やましろや)」の屋号で、傘の製造販売を始めたと言い伝えられています。明治時代になり、四条河原町の現在地に移転されました。
和傘の魅力について伺うと、「開く瞬間の精巧さと美しさです」と木下さん。「差している本人も楽しいのですが、すれ違う時にきれいだなと思ってもらえるような、日本ならではの細かい製法がたくさん詰まっています」と話されるように、和傘を広げてみるとその素晴らしい、緻密な製法がわかります。
まず傘を開くと、傘のはじき(傘を開閉した際にその状態を固定するための部位)が二段になっています。私たちが現在使っている通常の傘は、一つしかはじきはありませんが、和傘はその時の風の強さによって角度を変えられたり、また人とすれ違う際に当たらないようにすぼめるために二段になっているそうです。さらにすれ違う時に、錺(かざり)が見えるように装飾をつけています。通行する方への配慮も日本文化ならではといえます。

次に、一本の竹から作られているため、開いて傘になり、閉じたら一本の竹のように円筒になります。基本的には節間の長い真竹を使用するとのことで、一本の竹を44本に割き、竹の並び順が変わらないように骨組みを作ります。その骨組みを、細かい切込みと小さな穴がくり抜かれている「ろくろ」に、1本ずつ糸で通してつなぎあわせていくことによって、傘の土台(開閉できる構造)になります。


「ろくろ」に糸で骨組みをつなげる様子
そして、骨組みにはりつけられたしっかりとした和紙には素敵な絵が描かれていることはもちろん、内側にも「糸かざり」が施してあり、外側からも内側からも繊細な装飾を楽しむことができます。
ちなみに、和紙を骨組みにはりつけていく「張り」という作業は、雨や風にも負けない傘を作るためには非常に重要な工程です。タピオカの根茎から抽出したでん粉から作られたのりを用いることで強度が高められるそうです。

「糸かざり」を付けている様子
このような緻密な製法により作られている和傘は、安土桃山時代(約500年前)に誕生したと言われ、製法や材料などは300年来変わっていないそうです。「和傘」は元々、貴族や政治的に位の高い人たちに差し掛けるもので、日除けや雨除けのためではなく、災いを退ける「魔除け」の役割も果たしていました。江戸時代になり、雨除けとして一般的に使われるようになったことで、京都から全国に広まっていったそうです。
そして、今後の取組について、「ありとあらゆるものを京都産にしたい」という目標を教えていただきました。昔は「羽二重生地※」を用いた傘が主流でしたが、その生地を製作できる職人さんが減り、途絶えてしまったそうです。現在、辻倉さんの工房で「羽二重生地」を復活させようと5年前から取り組んでおられ、今年度中の完成を予定しています。このように、傘に使用される材料すべてを辻倉さんでまかなえるよう、完全自主製品を目指しておられます。「時代を後ろへ後ろへと戻っていくわけですが、素材や技術をもつ職人さんがいなくなることで文化の後継ができません。昔ながらの和傘から逸脱することなく、完全京都産にこだわって製作していきたいと考えています。」と意気込みを語っていただきました。
※たて糸とよこ糸を交互に織り合わせる、最も基本的な織り方「平織り」は、通常同じ太さのたて・よこ糸を用いるのに対して、羽二重生地は、細いたて糸2本とよこ糸1本を交互に交差して織られたものです。

有限会社 辻倉 代表取締役社長 木下 基廣(きのした もとひろ)さんからのメッセージ
私も妻も中京区で生まれ育ち、今もこの地で生活をしています。世界的に有名な都市の真ん中の区であり、京都の文化が集まる場所であると思っています。伝統工芸をはじめとした京都の文化を少しでも感じていただきたいですし、生活の中で使っていただけましたら、次世代につながり、さらに素晴らしい都市になると思っています。文化が集まるこのまちで、引き続き頑張っていきたいと思いますので、ぜひ店頭にいらしてください。お待ちしています!

<詳細情報>
有限会社 辻倉(つじくら)
場所:中京区河原町通四条上ル米屋町380 TSUJIKURAビル
電話番号:075-221-4396
ホームページ:https://www.kyoto-tsujikura.com/![]()

お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182