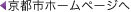区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(伝統産業)奇竹堂
ページ番号331096
2024年8月9日
奇竹堂 (令和6年8月9日更新)

奇竹堂は、江戸時代から続く千家十職の一つ「竹細工・柄杓師」である、黒田正玄(現在14代目)の分家として、竹細工の製造・販売を行っています。明治29年に分家、創業から約130年の歴史を刻み、現在は4代目の黒田宗傳さんが継いでおられます。
茶杓や柄杓、花生け、香合(こうごう)などの作品をオーダーメイドで制作されていますが、中でも、柄杓は使われる釜の大きさによって柄の角度や長さが変わるため、120もの種類があるそうです。また、接着剤を一切使わずに組み立てられる作品は、細工に高い技術が必要とされ、ひとつひとつ丁寧に手作業で制作されています。

材料となる竹には、一般的に知られている「真竹」のほか、「皺竹(しぼちく)」や「算盤竹(そろばんちく)」、「すす竹」、「亀甲竹(きっこうちく)」など、多くの種類があり、それぞれの特徴を活かして、作品に用いられています。竹は伐採された後、3箇月ほどの時間をかけて水分と油分が取り除かれ、さらに1箇月ほど天日干しを行ったうえで4~5年もの間、倉庫に寝かされて、はじめて使われるそうです。
奇竹堂では、炭火でいぶして油分を飛ばす製法にこだわり、薬品で油抜きをされるものと比べ、自然な色味が残る美しさと耐久性を高めることで、品質の高い作品を生み出しています。


黒田さんは制作のかたわらで、表千家の久田家と連携し、お茶の文化を広く知ってもらう活動にも力を入れておられます。「竹細工の加工には、カンナや小刀、ノコギリといった道具が必要で、良い道具があって始めて良い仕事ができます。使いながら“目立て”などの調整を行ってもらうことで、自分だけの道具になっていきますが、長年お世話になっている刃物屋さんが引退されてしまいます。伝統産業を継承していくには、少しでも需要を増やし、職を守りたいという思いで、道具に触れてもらう機会を作っています。」と話されました。この先は、オンライン販売など、一般の方にも手に取ってもらえるような仕組み作りも検討したいそうです。
作品が完成するまでには、さまざまな職人の技術が必要で、そのうち一つでも欠けると持続不可能であることを伺い、私たちも本当に良いものを選び、使っていくことで、伝統産業を守ることに繋がると感じました。
奇竹堂 竹器師 黒田 宗傳(くろだ そうでん)様からのメッセージ
お茶の文化をまず知っていただくことで、茶道具への興味やこだわりを持っていただけるのかなと思います。お稽古に通うことは、時間や費用の面でハードルを感じられるかもしれませんが、一生もののお作法と道具を自分のものにできる機会でもあります。ぜひ、お気軽にのぞいてみてください。

<詳細情報>
奇竹堂(きちくどう)
場所:中京区押小路富小路角
電話番号:075-231-2765


お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182