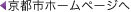区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(寺院神社)神泉苑
ページ番号326719
2024年5月20日
神泉苑(令和6年5月20日更新)

二条城と二条駅の間にある神泉苑。「龍神」がいるとされる大きな池やアヒルがいることで、ご存知の方も多いと思います。その歴史は古く、今年で建立1230年目を迎えます。今年は辰年ということにちなみ、「龍神」のお話や歴史について、副住職の鳥越 智翔(とりごえ ちしょう)さんにお話を伺いました。
平安京ができた延暦13年(794年)、大内裏の南側に隣接して造営された神泉苑は、「禁苑」(宮中附属の天皇のための庭園として造られたものであり、一般の方は入苑を許されない場所)として整備されました。
苑内は、大きな池や青々とした木々など、自然豊かな空間が広がっていて、当時の宮中の方々は舟遊びや魚釣り、春にはお花見、秋には菊の節句で菊の酒を飲んで長生きを祈願されるなど、季節ごとに趣のある時間を過ごされていたそうです。また、「弘法大師」の空海は、大内裏への参詣の後、その道すがら神泉苑で「豊かな自然が昔からあるところなので帰りたくない」などの漢詩を残しています。
大きな池

神泉苑でくらすアヒル
大きな池は平安京の前からあるとされ、「龍神のすまう池」としても知られています。天長元年(824年)、日照りが続いたことによる干ばつで、穀物等が育たなくなり、食糧が不足しました。そこで淳和天皇は飢餓に陥る人々を救うために、空海に「雨ごい(祈願等により降雨を求めること)」を命じられました。空海は、雨を降らすとされる「善女龍王」を、北天竺(てんじく)の大雪山付近(現在のチベットのエベレストの北にあるマナサロワール湖とされている)で見つけ、神泉苑に勧請(お招き)したところ、京都だけでなく日本中に恵みの雨が降り、干ばつは解消しました。

名鐘の拓本(うつし)
それ以降、善女龍王は今もここに居られると言い伝えられ、神泉苑には、北天竺から大蛇に乗ってやってきた金色の姿をした善女龍王の絵巻が残っています。そして、それまで天皇のための遊宴の場だった神泉苑は、空海の雨ごい以降、宗教的な霊場にもなり、863年に祇園祭の元となった「御霊会(ごりょうえ)」が行われました。
「非業の死をとげた魂が、世を恨み疫病を流行らせたり、怨霊となって現れたりする」と考えられ、その怨念を鎮めるために御霊会が行われるようになったとされ、当初は六柱の霊座を設け御霊を鎮めていましたが、6年後の869年には、長さ2丈(約6メートル)の鉾を66本建て、祇園社(八坂神社)から神泉苑に神輿を送り、厄払いを行うようになりました。これが祇園御霊会の始まりとされています。
平安時代末期から鎌倉時代にかけて、台風や火災、戦乱等によって荒廃した時期がありましたが「龍神がいる池」として代々守ってこられました。源頼朝や北条泰時なども神泉苑を修繕に力を注がれたと言われています。
また、神泉苑は今の15倍ほどの大きさがありましたが、江戸時代の初めに二条城が築城に伴い規模は縮小され、二条城の堀の水に神泉苑の水源が取り込まれました。今は規模の縮小に伴い、二条城の中から地下で送り出された水と、神泉苑で湧き出ている水の両方で池を満たしています。
今年は、空海の雨ごい(824年)から1200年を経た記念の年です。この機会にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

神泉苑 副住職 鳥越 智翔(とりごえ ちしょう)様からのメッセージ
神泉苑は、桓武天皇や嵯峨天皇、淳和天皇が遊宴されていたところで、憩いの場所です。今でも心の安らぐ場所だと思います。また境内のお堂には、観音様やお不動様、善女龍王様、弁才天様などご神仏をおまつりしています。自然やご神仏に触れていただき、心が安らかに過ごせるひと時をお過ごしいただけますと幸いです。

<詳細情報>
神泉苑(しんせんえん)
場所:中京区御池通神泉苑町東入門前町166
電話番号:075-821-1466
ホームページ:http://www.shinsenen.org/index.html![]()
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182