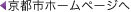区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(飲食店・ショップ)すはま屋
ページ番号324881
2024年4月19日
すはま屋(令和6年4月19日更新)

丸太町通烏丸西入にある「すはま屋」。「すはま」は浅煎りの大豆粉と砂糖、大麦や米からとった麦芽で作った蜜を練り合わせた和菓子で、宝暦の時代(1751~1764年頃)には「日本四大菓子」の一つとされ、葵祭では下鴨神社の御神饌(しんせん)として数百年にわたって「すはま」が献上されていました。今もなお、京都の銘菓として多くの方に親しまれ続けています。
「すはま屋」の前身は、2016年に閉店した「御洲濱司(おんすはまつかさ)植村義次」さん。1657年に創業し、約360年の歴史をもつ和菓子の老舗です。「すはま」の名前の由来となった「洲浜形」を考案したお店です(「浜辺の入り込み」が縁起がよいとされ、豆飴をそのような形にかたどったことから、「すはま」と呼ばれるようになったそう)。

第14代目の御当主が御高齢ということで閉店となりましたが、地元から惜しまれる声が多く、「すはま屋」店主の芳野さんもその一人でした。
芳野さんのお父様は、茶道の武者小路千家で修業をされた家元教授でおられ、初釜(年が明けて最初に行われる茶会)のときには、植村さんの「すはま」を御干菓子として出されており、芳野さんにとって「すはま」はなくてはならない存在でした。「閉店をきいたとき、『すはまがなくなってしまう』と悲しく思っていたところ、植村さんから『自分で作ってみたら』と誘われたことがきっかけで、父と一緒に作り方を植村さんから教えてもらうようになり、練習していたらどんどん楽しくなっていきました」と芳野さん。その後、2018年11月に、「御洲濱司 植村義次」直伝のすはま専門店として「すはま屋」を開店しました。

店内は販売だけではなく、カフェも併設しています。「私も植村さんも珈琲が好きで、すはまが珈琲と合うことも植村さんから教えていただきました。お抹茶だけではなく珈琲や紅茶と一緒に食べてもおいしいということを知っていただきたいのでカフェの併設を決めました」と話されました。
また、「すはま」だけでなく、「押物(おしもの)」という和菓子づくりにも挑戦しました。すはまの生地で椿や桜の絵柄を描き、押物にしたもので、能や茶会等の記念品としてオリジナルの絵柄を作られることもあるそう。「すはまと同様に、押物も植村さんから2年ほどかけて教わりました」と話され、さらに、大豆粉は季節によって風味が変わるため、今なお植村さんに味をみていただいているそうで、技術の継承に余念がありません。

「お客様も昔からの常連の方がほとんどです。『復活してくれてありがとう』とよく言っていただけるのでうれしいです」と芳野さん。地域の方々とは昔からつながりが深く、「地蔵盆」に来られた方に記念品として「すはま」を配っていただくこともあるそうです。
皆さんも一度、伝統和菓子の真の味わいを楽しまれてみてはいかがでしょうか。
すはま屋 店主 芳野 綾子(よしの りょうこ)様からのメッセージ
「細く長く」をモットーに、一人で励んでおります。自分のできる範囲でコツコツと精進していきますので、今後ともよろしくお願いいたします!
「洲濱セット」は、「すはま」と、飲み物は珈琲・紅茶・お抹茶の中から選んでいただけるように用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。


<詳細情報>
すはま屋
所在地:中京区丸太町通烏丸西入 常真横町193
電話番号:075-744-0593
公式SNS:https://twitter.com/suhamaya193![]()
*販売
営業時間:10時~17時半※第2・4水曜日、日曜日、祝日は休み
すはまは2日前、押物は4日前までに要予約
*喫茶
営業時間:12時~17時半(ラストオーダー17時)※水曜日、日曜日、祝日は休み
お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182