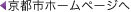区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(寺院神社)壬生寺
ページ番号293920
2020年10月29日
壬生寺(令和2年10月29日更新)

律宗・壬生寺は991年(正暦2年)創建。快賢(かいけん)というお坊さんが,亡くなった母の菩提を弔うために,お地蔵様を御本尊としてお堂を建てたというのが始まりです。壬生寺と言えば「壬生狂言」ですが,始まりは1300年(鎌倉時代,正安2年)で,火事で焼失した壬生寺を再興させた円覚上人(えんがく しょうにん)が仏教をわかりやすく伝えるために,お説法に身振り手振りを取り入れたことがきっかけと言われています。現在では,国の重要無形民俗文化財「壬生大念仏狂言」として広く知られています。
コロナ禍で今年は壬生狂言は中止となり,壬生寺を訪れる人も減りました。「人と会って実際にお話しすることで,人と人とのつながりが生まれます。」と副住職の松浦俊昭さん。壬生狂言には台本がなくすべて口伝であり,人が人に伝えてきたため途絶えずに今なお継承されています。「伝統や文化,風習というものは人が人に伝えるものであり,人と人とのつながりがあれば伝統文化は廃れない。」と語られました。
また,150年前からお地蔵様の居ない町内に地蔵盆の期間中,お地蔵様を貸し出す出開帖(でがいちょう)を行っています。新型コロナウイルス感染症の影響により今年は多くの地域で地蔵盆の開催ができませんでしたが,祇園祭ができなかった鉾町の方から,「子どもたちのために何かしたい」という要望があり,ホテルのフロアをお借りして鉾町主催で地蔵盆を行いました。大変好評であったため,地蔵盆が終わっても今なお,お地蔵様はその町内で過ごされています。「仏様を縁として人が集まり,新しく御縁ができたことは京都ならでは」と話されました。
松浦副住職さんは,京都市の「オンライン地蔵盆壬生寺 副住職 松浦 俊昭(まつうら しゅんしょう)様からのメッセージ
「共結来縁」という古くから伝わる言葉があります。「来るべき縁を結びましょう」という意味で,新しいスタートの言葉であると思っています。新しい御縁を結ぶためにも前に進みましょう。出会った御縁を大切に,これからも様々な取組をしていきたいです。

<詳細情報>
壬生寺(みぶでら)
所在地:中京区壬生梛ノ宮町31
電 話:075-841-3381
ホームページ: http://www.mibudera.com/![]()


お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182