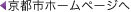区民ライターがゆく!頑張る中京人・魅力再発見(伝統産業)長谷川松寿堂
ページ番号290129
2020年12月25日
長谷川松寿堂(令和2年12月25日更新)

大正8年創業の長谷川松寿堂は,和紙工芸品約2000アイテムを取り扱っており,全国800店の小売店を対象に商品を卸しています。昭和11年に六角柳馬場から現在の三条高倉に移転され,祇園祭の後祭りが三条通を通っていた昭和41年まで,お店の場所がくじ改め※(くじあらため)の場所でした。
※巡行順がくじ通りであるかを確認する儀式。各山鉾の行司がくじ札の入った文箱(ふばこ)を差し出す所作は,毎年注目を集め,奉行役の京都市長がくじ札を見定めて通行の許しが得られると山鉾に扇子を広げて合図がおくられます。
詳しくはこちら:京都観光Navi 祇園祭「深く知る」
https://ja.kyoto.travel/event/major/gion/understand.php![]()
和紙工芸品の製造は京都が今でも中心となっています。京都には御所があり,昔から素晴らしい技術を持った職人さんが集まり,その技術を継承されてきました。「最近は,色紙を使って和歌を書いたり,写経をしたりするような文化が少なくなっているような気がします。」と営業部長の加納健三さん。色紙や短冊の需要が減り,最近は職人さんの数も減少傾向にありますが,今なお40~50人の職人さんが活躍されています。
コロナ禍では,マスクを外した時に収納できる「マスクフォルダー」や,疫病退散として知られる妖怪「アマビエ」を使った色紙や置物なども作製されました。さらに,「透明うちわ」も作られ,耳にマスクをかけることやお顔を隠すことが難しい舞妓さんたちに使用されました。「京都には職人の技があります。どうしたら良いのだろうと思ったとき,職人さんがたくさんおられるのですぐに相談することができます。」と話され,商品開発に日々取り組まれています。例えば,扇子の職人さんは華やかで細かなデザインが得意であるため,色紙に絵を描いてもらったり,最近人気となっている麻の細長いタペストリーを作製いただいたりと,扇子以外でも活躍の場が広がっています。「ものづくりには,普段からのコミュニケーションがとても大切」と話され,「コロナが終息したら,区民の皆様にはさまざまな人との関係づくりをしてほしい。」と語られました。
長谷川松寿堂 取締役営業部長 加納 健三(かのう けんぞう)様からのメッセージ

<詳細情報>
株式会社長谷川松寿堂(しょうじゅどう)
所在地:〒604-8111 京都市中京区三条高倉東入
電 話:075-255-1515
ホームページ: http://www.h-shojudo.co.jp/![]()



お問い合わせ先
京都市 中京区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画担当:075-812-2421、事業担当・広聴担当・振興担当:075-812-2426
ファックス:075-841-8182