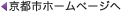市電保存館 on WWW (無軌条電車-I型~地下鉄東西線50系)
ページ番号6824
2024年4月30日
車両解説
無軌条電車-I型

昭和7年3月、我が国初の営業用(四条大宮~西大路四条間)としてのトロリーバス1~4号車の4両が竣工した。全て英国製であった。1、2号車と3、4号車は車体寸法、座席定員、車輪径、ホイールベース等でも若干の違いはあるが、1号車は出入口が前後一箇所あるのに対し、3、4号車は中央部一箇所となっており扉構造はいずれも手動両開き4枚折戸である。1、2号車の前部扉には運転手のレバーロッド操作による遠隔手動となっている。
昭和7年12月に国産車の5号車1両、9年4月に6号車、15年2月に7号車がそれぞれ増備され、昭和25年9月に7号車、28年8月までに1~6号車まで全て廃車された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1,2 | 二軸六輪単車型無軌条電車 | 2 | 50 | 28 | ガイモータース[英] | ---- | ガイモータース[英] | 65HP×1 | 間接非自動 | レバー式手用直通空気 | 昭和7.3 |
| 3,4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | イングリッシュ エレクトリック[英] | 〃 | イングリッシュ エレクトリック[英] | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 5 | 〃 | 1 | 〃 | 30 | 日本車両 | 〃 | 日本車両 | 35HP×2 | 間接自動 | 〃 | 昭和7.12 |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 川崎車両 | 〃 | 川崎車両 | 65HP×1 | 〃 | 〃 | 昭和9.4 |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 日本車両 | 35HP×2 | 〃 | 〃 | 昭和15.2 |
無軌条電車-100型

昭和27年から28年にかけてI型と入れ替わりに登場した形式である。全6両が製作された。 I型3号車以降と同様入口は中央一箇所、車長もほとんど同じであるが、各部装置に近代化が図られ、車体にはアルミ合金を多用し、扉は空気戸閉機による自動開閉装置を搭載した。電動機は100馬力1基を車体後部に取り付け制御装置は電動発電機による低圧制御回路を使用した間接自動制御方式を採用した。主制御器を車体後部としたため、前部にクロスシートを配置、座席定員31名、定員56名と広くなっている。制動装置は空気制動機を主とし手用制動機、電気制動(非常用)を備えている。またトロリーポールは先端集電部に摺動子を採用、I型のホイール式とは異なっている。全て昭和43年9月に廃車された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 101-104 | 二軸六輪単車型無軌条電車 | 4 | 56 | 31 | ナニワ工機 | TR-23 | 日野ディーゼル | 100HP×1 | 間接自動 | レバー式手用直通空気 | 昭和27.4 |
| 105,106 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和28.7 |
無軌条電車-300型

無軌条電車としては最後のタイプで昭和33年から40年の間に渡って増備された。車長は200型より0.5メートル長く主制御器などは市電と同じく車体床下につり下げられたため、後部機器室が無い。そのため乗客定員は75名と増加し、全席ロングシートとなっている。室内灯や方向幕灯は複流電動発電機による蛍光灯を使用していた。昭和40年から41年にかけて301~317号車までのワンマン化工事が完了したが、200型と同じくワンマン運転されることなく昭和44年9月末のトロリーバス全廃時に廃車された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 301-305 | 二軸六輪単車型無軌条電車 | 5 | 75 | 37 | ナニワ工機 | MC-31 | 日野ディーゼル | 133HP×1 | 間接自動 | レバー式手用直通空気 | 昭和33.12 |
| 306-309 | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | TB-13 | 三菱ふそう | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 310-314 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和34.6-36.4 |
| 315-317 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和37.3 |
| 318 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和40.3 |
狭軌散水車

京都電氣鐵道から譲り受けた1~136号車の内134~136号車が散水車であった、譲渡と同時に散水車1~3号と改番した。散水車とは軌道部分が舗装されていない当時は電車の走行後に起こる砂塵の飛散を防ぐ目的で使用されたが、昭和15年頃から軌道部分の舗装が進み使用頻度は減少。昭和27年までには全車廃車となった。構造は車体中央部に約6立方メートルの鋼板製水槽が備え付けられていた。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 積載荷重 (水槽容量) | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(トン) | ---- | 形式 | 製作所 | ||||||||
| N1-N3 | 電動タンク貨車 | 3 | N1-不明 N2-6.096 N3-4.369 | -- | 梅鉢鉄工所 (丹羽鉄工所) | 21-E | ブリル | 25HP×2 | 直接 | 水平片手々用 | 京都電氣鐵道株式会社 より譲り受けた ため詳細不明 |
広軌散水車

京都市営電車開業まもない明治45年ごろに竣工したのがこの散水車であった。狭軌散水車と同じく、車体中央部に約6.5立方メートルの鋼板製水槽が備え付けられていた。図の10号はI型電動客車49号を改造したものとなっている。
これらも狭軌散水車と同じく、昭和15年頃からの軌道部分の舗装の進展と、かえって軌道保守に悪影響があるとして昭和16年頃から昭和25年までに全車廃車された
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 積載荷重 (水槽容量) | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(トン) | ---- | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1-3 | 電動タンク貨車 | 3 | 6.503 | -- | 松原鉄工所 | 21-EM | マウンティンギブソン | 25HP×2 | 直接 | 水平片手々用 | 明治45.6 |
| 4,5 | 〃 | 2 | 〃 | -- | 梅鉢鉄工所 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大正2.10 |
| 6-8 | 〃 | 3 | 〃 | -- | 田中車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大正13.10 |
| 9 | 〃 | 1 | 〃 | -- | 大藪地金商店 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和10.3 |
| 10 | 〃 | 1 | 〃 | -- | 淀屋三吉商店 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和11.5 |
貨車

大正14年7月に業務用資材運搬車として購入したのが始まり。構造は無蓋四輪車で車体中央部にダブルポール1組及びこれを取り付ける鉄塔が組まれている。 2号車以降は廃車となったI型電動客車(2、3号車)や散水車(4-8号車)を改造して使用した。昭和31年までに2、4、5、6、7、8号車は廃車。残った1、3号車は時々花電車などに使用されたが、昭和48年2月に廃車された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 積載荷重 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(トン) | ---- | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1 | 電動無蓋貨車 | 1 | 3.064 | -- | 梅鉢鉄工所 | 21-E | ブリル | 25HP×1 | 直接 | 水平片手々用 | 大正14.7 |
| 2,3 | 〃 | 2 | 〃 | -- | 京都市電壬生工場 | 〃 | 〃 | 25HP×2 | 〃 | 〃 | 昭和19.8 |
| 4-8 | 〃 | 5 | 〃 | -- | 〃 | 21-EM | マウンティンギブソン | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和21.5 |
■参考
地下鉄東西線50系

平成9年に開通した地下鉄東西線醍醐~二条12.7Kmを走る車両として50系車両、6両14編成、計84両を製作しました。この車両は準小型車両ではありますが、21世紀の車両として新たな発想のもとに安全性、快適性を基本に今日の最新技術を駆使した車両となっています。
| 車種-形式 | 両数 | 乗車定員 | 車体 製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | |||||||
| Tc1,Tc2-5100・5600 M1,M1'-5200・5400 M2,M2'-5300・5500 | 84 | 92(T) 104(M) 600(1編成) | 34(T) 42(M) 236(1編成) | 近畿 車輛 | KH-182,183 モノリング式 ボルスタレス台車 | 日立製作所 | SEA-362 85kW-1,100V×4台/両 | GTO-VVVFインバータ方式 1C8M制御 | MBS-A 電気演算式ブレーキ 予備ブレーキ付き | 平成9.10 |
お問い合わせ先
京都市 交通局企画総務部企画総務課
電話:(企画担当)075-863-5031、(調査担当)075-863-5035、(契約・入札担当)075-863-5095
ファックス:075-863-5039