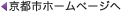市電保存館 on WWW (狭軌I型~2000型)
ページ番号6788
2024年4月30日
車両解説
狭軌I型

大正7年7月、京都電氣鐵道株式会社から特許権、軌道施設等と共に譲り受けた車両で1~136号の136両存在した。このうち1~133号車が普通客車で134~136号車が散水車である。普通客車には、当時在籍していた広軌木造単車1~167号車と重複するため車両番号の頭に「狭軌」の2字を付記するものとし、車体番号には「N」を付した。これが後に「N電」と呼ばれたゆえんである。
この狭軌車両は、路線の軌間拡張工事に伴い大正14年までに39両、昭和28年までに▼散水車3両を含む108両を廃車し、神戸市伊藤商事(大正8年33両)、熊本市菊池電鉄(昭和3年6両)、名古屋市(昭和19年15両)等へ売却譲渡された。
その後、広軌I型の全車を廃車したこともあって、昭和30年に当時の残存車両28両に対して1~28号の連番に改番を行った。その後昭和36年3月末に6両、同年7月の北野~京都駅前間の狭軌路線廃止時に残り22両が廃車となった。
(27号車は2001年現在▼梅小路公園内でチンチン電車として運行中)
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 自重 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | |||||||||
| N1-N133 | 高床四輪木造電動客車 | 133 | 38(43) | 20(12) | 6.604t | 梅鉢鉄工所 | 21-E | ブリル | 25HP×2 | 直 接 | 水平片手把手々用 | 京都電氣鐵道株式会社より譲り受けたため詳細不明 |
広軌I型

明治45年6月の京都市営電車開業とともに登場した車両がこのI型高床木造四輪単車である。当時製作中のものを含め1~167号車の167両あった。開放式運転台、2段式屋根、2段胴羽目、中央ダブルポールである。
大正10年10月に168、169号車の2両を増やし、大正12年5月には▼貴賓車2両を普通車に改造し170、171号車となった。
このI型は、昭和25年4月を最後に全部廃車になったが、昭和13年に大連都市交通へ10両、長崎電気軌道へ5両譲渡している。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 自重 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | |||||||||
| 1-30 | 高床四輪木造電動客車 | 30 | 48 | 20 | 約9t | 天野工場 | 21-EM | マウンティンギブソン | 25HP×2 | 直 接 | 水平片手把手々用 | 明治45.5 |
| 31-50 | 〃 | 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 梅鉢鉄工所 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 明治45.5-7 |
| 51-90 | 〃 | 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 天野工場 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 明治45.6-大正1.11 |
| 91-93 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | BL-21-E | 汽車会社 | 〃 | 〃 | 〃 | 大正1.11-2.9 |
| 94-95 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 21-E | ブリル | 〃 | 〃 | 〃 | 大正1.11 |
| 96-166 | 〃 | 71 | 〃 | 〃 | 〃 | 梅鉢鉄工所 | 21-E | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大正2.2-2.9 |
| 167 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 21-E | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大正2.9 |
| 168-169 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | MG21-EM | 汽車会社 | 30HP×2 | 〃 | 〃 | 大正10.10 |
| 170-171 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 天野工場 | 21-EM | マウンティンギブソン | 25HP×2 | 〃 | 〃 | 明治45.6 |
貴賓車

明治45年6月に貴賓車1、2号車として2両が竣工した。車体寸法などは、I型木造単車(広軌I型)と同じであるが、座席数を8にして使用。材料を厳選し、入口窓枠など内装はチーク材を使い、床板の下張りは日本松、上張はチークおよびケヤキ板の網代張であった。窓は片側5箇所で欄間は模様入りガラスをはめ込み窓掛、椅子などは高価なものを用いた。大正12年5月に普通客車に改造。出入口回廊、座席、吊革などを取り付け170、171号車となり、昭和25年1月まで活躍した。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1,2 | 高床四輪 木造電動客車 | 2 | ---- | 8 | 天野工場 | 21-EM | マウンティン ギブソン | 25HP×2 | 直 接 | 水平片手 把手々用 | 明治45.6 |
500型

京都市の発展と共に、市内交通機関として市電の役割が増大したため大型の半鋼製低床ボギー車が登場した。これが500型で京都市で初めて空気ブレーキを採用、集電装置は前後に各一組を備え車体前後及び中央の三ヵ所に出入口を設けていた。大正13年2月に501~510号車10両が竣工し、次いで14年3月に511~517号車の7両、昭和3年11月には518~540号車の23両が竣工した。
なお511型(511~517号車)のうち514~517号車の4両は昭和10、11年に中扉をなくし、小型に改造された。車両番号はそのままであったが京都市電としては514型と呼んでいた。 514型を除く他の500型車両は戦後新造された1000型とともに昭和33年9月中扉を閉鎖し座席を増やした。その他にも救助器の構造変更や客席シートの一部撤去ダブルポールのシングル化、さらにビューゲル化、車内放送設備の取付けを行った。昭和42、43年度末に5両づつ、昭和45年5月の伏見・稲荷線の廃止とともに残存する30両を廃車した。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 501-510 | 大型低床ボギー 半鋼電動客車 | 10 | 80 | 32 | 田中車両 | 77-E1 | ブリル | 40HP×2 | 直 接 | 直通空気垂直 ハンドホイール 手用 | 大正13.2 |
| 511-513 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | ボ製 | ボールド ウィン | 〃 | 〃 | 〃 | 大正14.3 |
| 514-517 | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 517-540 | 〃 | 23 | 〃 | 36 | 梅鉢鉄工所 | KS-45L | 住友製鋼所 | 50HP×2 | 〃 | 直通空気 | 昭和3.11 |
600型

昭和12年従来の車両とは異なる当時としては高性能な低床ボギー車が誕生した。これが600型で車体・台車構造は後の1000、▼800、▼700型の原型となった。昭和12年4~12月にかけて601~620号車が竣工。主な特長としては流線型の車体、前照灯の上部取り付け、空気式自動開閉扉の採用があるが、車体塗装が従来のあずき色から下部みどり色、上部クリーム色のツートンカラーに変わり、「青電」の愛称で親しまれ、活躍した。昭和39年にはワンマン化改造を受け18両が2600型に残りの車両は昭和41年12月から昭和43年3月にかけて、▼1600型に改造された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 601-620 | 小型低床ボギー 電動客車 | 20 | 64 | 32 | 日本車両 | KS-40L | 住友製鋼所 | 50HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和12.4-12.7 |
| 621-645 | 〃 | 25 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和13.4-12.7 |
| 646-675 | 〃 | 30 | 〃 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和13.4-13.10 |
| 676-685 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 住友製鋼所 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和16.7-16.8 |
| 686-695 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 田中車両 | 〃 | 田中車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和22.3-22.8 |
700型

昭和33年3月に竣工した中型ボギー車の700型(701~715号)の15両は、車体の容姿がそれまでの600型や800型とは少し異にしている。車両の軽量化に重点を置いたため、車体の高さが他の車両より約260mm低く、オーバーハングは短く側窓巾は広くなっている。
出入口扉は両開き4枚折戸で自動開閉となっており出入口有効巾は他の車両より広い。台車は900型と同様の構造であるが成形鋼板の溶接台車である。
昭和33年12月に716~728号車の13両、34年12月に734~737号車の4両、36年12月に738、739号車の2両、37年2月に740~743号車の4両、同9月に744~748号車の5両と順次増備し、総数48両となった。
この車両はワンマン改造されることなく昭和46年7月に3両、47年1月に22両、48年2月に7両と順次廃車、49年5月には16両の残存車両全車を廃車した。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 701-715 | 中型低床ボギー 電動客車 | 15 | 86 | 32 | ナニワ工機 | KL-11 | 日立製作所 | 60HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和33.3 |
| 716-721 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | NS-13 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和33.12 |
| 722-723 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 東洋工機 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 724-737 | 〃 | 14 | 〃 | 〃 | ナニワ工機 | 〃 | 〃 | 〃 | 間接自動 | 〃 | 昭和33.12-35.1 |
| 738-743 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 〃 | NK-24 | ナニワ工機 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和33.10-37.2 |
| 744-748 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | NS-13 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和37.9-37.10 |
800型

昭和31年4月に竣工したこの車両は、他の800型と同じ長さ、窓数であるが、車体と使用は直前に竣工している900型(901~915号車)とよく似ている。制御方式は801~865号車と同じ直接式であり電動機もSS-50である。
妻中央窓を大きくし、方向幕も一段と大きくしているところや室内灯、方向幕灯を蛍光灯にしたところはまったく900型と同じである。
照明用として電動発電機を積載している他、当初よりビューゲルを装備している。台車は従来のものと異なり、軸受箱(コロ軸受)がリンクにより台車と結合されたアクスレンカー式を採用、揺れマクラバネに2重コイルばね、上部に防振ゴム、中央にスナッパを使用、車体の上下振動、特にローリングに対処している。
801-870号車はワンマン化改造を受け▼1800型として活躍したが、881-890号車は昭和48年4月に廃車されるまで、全く部分改造はなく、またワンマン化することもなかった。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 801-805 | 中型低床ボギー 電動客車 | 5 | 76 | 36 | 川崎車両 | KS-40J | 扶桑金属 | 50HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和25.4-25.9 |
| 806-815 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 816-820 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 821-825 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 826-845 | 〃 | 20 | 〃 | 〃 | 近畿車両 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 846-850 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 帝国車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 851-855 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 856-860 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | ナニワ工機 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和26.5 |
| 861-865 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和27.12 |
| 866-870 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 愛知富士 | 〃 | 住友金属 | 60HP×2 | 間接自動 | 〃 | 昭和28.4 |
| 871-875 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | ナニワ工機 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和29.5 |
| 876-878 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | MD-6 | 新三菱重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 879-888 | 〃 | 2 | 〃 | 〃 | 飯野重工 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 881-890 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | ナニワ工機 | MD-201 | 〃 | 50HP×2 | 直 接 | 〃 | 昭和31.4 |
900型

昭和30年3月に竣工した900型(901~915号車)の15両は800型より一窓分長い車両であるが、各部に新しい装備を施している。制御方式は866~880号車に引き続き間接自動制御である。車体妻部の中央窓を大きく広げ、それに伴い方向幕も大きくなっている。室内灯、方向幕灯には蛍光灯を採用している。
800型後期の車両と同じく車体側板下部の覆い「スカート」は無い。台車の揺れマクラばねにコイルばねを使いコロ軸受を採用している。車輪は始め弾性車輪(ゴムサンドイッチ型)であったが昭和40年10月から同41年にかけて普通車輪とした。電動機はSS-60である。
昭和32年9月に916~935号車の20両を増備したが、この車両は直接式制御であった。昭和45年5月に901、902、同46年7月に932~935の計19両を廃車したが、916~931の各車はワンマン車に改造、▼1900型として引き続き使用された。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 901-915 | 中型低床ボギー 電動客車 | 15 | 86 | 42 | ナニワ工機 | FS-65 | 住友金属 | 60HP×2 | 間接自動 | 直通空気 | 昭和30.3 |
| 916-927 | 〃 | 12 | 〃 | 〃 | 〃 | FS-65A | 〃 | 〃 | 直 接 | 〃 | 〃 |
| 928-930 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 東洋工機 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 931-935 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
1000型

戦後はじめて増備された車両がこの大型ボギー車1000型である。昭和24年12月に1001~1022号車、翌年は1023~1032号車が竣工し合計32両となった。
車体は600型の形状を引き継ぎ外側板上部から前面各面部へのカッターラインが入っている。車体長は京都市電中もっとも長く、片面3出入口で各扉とも片引戸自動開閉扉を採用していた。台車は600型と同じで、電動機には当初SS-50を用いていたが、昭和30年8月から順次SS-60に取り替え輸送力の増強を図った。同年10月にはシングルポールをビューゲルに変更し昭和33年9月には500型とともに中央出入口を閉鎖してその部分に座席を設置、昭和37年10月には車内放送設備を設けた。昭和46年7月に7両、47年1月に25両を廃車した。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1001-1005 | 大型低床ボギー 電動客車 | 5 | 90 | 36 | 日本車両 | KS-40J | 扶桑金属 | 50HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和24.10-11 |
| 1006-1010 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 日立製作所 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1011-1016 | 〃 | 6 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和24.12 |
| 1017-1027 | 〃 | 11 | 〃 | 〃 | 日立製作所 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和24.12-25.4 |
| 1028-1032 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 広瀬車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和25.4 |
1600型

▼600型をワンマン・ツーマン兼用車に改造したもので、昭和41年12月に6両が竣工したのを手始めに、43年3月までに1605~1667号車の63両が竣工、同時に車両番号の変更を行った。この変更は「ワンマン」を意味するように車両番号を1000番台とし2000型改造による欠番整理も同時に行って1600代の番号とした。
車体は外板中程に赤帯を配し、前照灯の2灯化、妻及び外板ワンマン表示、出入口表示などのワンマンカー識別を施した。この他にもいろいろなワンマン装備を設け、完成後にもテープガイド装置や降車合図表示装置、警笛の電気化を追加装備した。
改造設計など工事の一部は当時の壬生電車車両工場で行った。この1600型は昭和47年1月に1635号車を1両、48年2月に5両、49年4月に2両、50年1月に4両と順次廃車され、昭和51年3月末の今出川・丸太町・白川線廃止と同時に残る51両全車を廃車した。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1605-1620 | 小型低床ボギー 電動客車 | 16 | 84 | 34 | 日本車両 | KS-40L | 住友製鋼所 | 50HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和41.12-43.3 |
| 1621-1637 | 〃 | 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1638-1657 | 〃 | 20 | 〃 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1658-1667 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 住友製鋼所 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
1800型

▼800型をワンマン化改造したもので、昭和43年10月から昭和45年3月までに70両が投入された。改造時に後部出入口を廃して中央寄りに出口を新設、ワンマン識別塗装の赤帯、前照灯の2灯化、ワンマン表示など1600型と同様の装備を追加した。旧867~870号車は間接自動制御器を直接式制御器に置き換え。旧801~865号車には床下にワンマン機器用の電動発電機を取り付けた。この形式はワンマンカーの代表車種として活躍。昭和52年の河原町・七条線廃止時に24両をまた昭和53年2月に2両を残り43両は昭和53年9月末の全廃時まで走り続けた。
(*下表の車両番号下3桁は旧車両番号)
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1801-1805 | 中型低床ボギー 電動客車 | 5 | 94 | 34 | 川崎車両 | KS-40J | 扶桑金属 | 50HP×2 | 直 接 | 直通空気 | 昭和43.10-45.3 |
| 1806-1815 | 〃 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1816-1820 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1821-1825 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1826-1845 | 〃 | 20 | 〃 | 〃 | 近畿車両 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1846-1850 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 帝国車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1851-1855 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 汽車会社 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1856-1860 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | ナニワ工機 | MD-6 | 中日本重工業 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1861-1865 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | KS-40J | 扶桑金属 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1866-1870 | 〃 | 5 | 〃 | 〃 | 愛知富士 | 〃 | 住友金属 | 60HP×2 | 〃 | 〃 | 〃 |
1900型

800型ワンマン改造に引き続き▼900型をワンマン化改造したものがこの1900型である。
改造は全く▼1800型と同じであるが集電装置はZパンタであったのを、自動引き下げ装置付きビューゲルに取り替えた。昭和48年2月に1922号車が廃車され、続いて、昭和52年10月の河原町・七条線廃止時に1921,1923号車を広島電鉄へ売却譲渡した。残存車両も市電全廃時まで1800型とともに活躍し、全廃後、全車(1916-1920,1924-1931)が▼広島電鉄に引き取られ2014年現在運行中。
(*下表の車両番号下3桁は旧車両番号)
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 1916-1927 | 中型低床ボギー 電動客車 | 12 | 100 | 38 | ナニワ工機 | FS-65A | 住友金属 | 60HP×2 | 直接 | 直通空気 | 昭和45.2-45.3 |
| 1928-1930 | 〃 | 3 | 〃 | 〃 | 東洋工機 | FS-65A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 1931 | 〃 | 1 | 〃 | 〃 | 日本車両 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和45.3 |
2000型

昭和38年5月に認可を受けたこの2000型は通常のツーマン運転の他にワンマン運転および連結運転が出来るように設計されたもので、特にワンマン運転方式、各設備などはこの後の各型式のワンマン装備の基本となった京都市電初のワンマンカーである。
昭和39年2月に2001、2002号車の2両、40年2月に2003~2006号車の4両が相次いで竣工。2600型18両とともに早朝ラッシュ時には2両連結運転により通勤・通学の足として活躍した。また昼間の閑散時にはワンマンカーとして運行された。当初は他の車種との識別の意味で外部塗装色を下部はコバルトブルー、上部をアイボリーとしたが他車種のワンマン化などにより従来の色に塗り替えられた。この2000型はその設計思想から複雑な機能、設備を持った車両であったため整備の面で手数がかかったことから、昭和52年9月の河原町・七条線廃止時に全車廃車された。 2002~2006号車は▼伊予鉄道へ引き取られ2014年現在運行中。
| 車 号 | 車 種 | 両数 | 乗車定員 | 車体製作所 | 台 車 | 主電動機 | 制御装置 | 制動装置 | 竣工 年月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計(名) | 座席(名) | 形式 | 製作所 | ||||||||
| 2001-2002 | 中型低床ボギー 電動客車 | 2 | 90 | 32 | ナニワ工機 | KL-11 | 日立製作所 | 60HP×2 | 間接非自動 | 非常弁付 直通空気 | 昭和39.1 |
| 2003-2006 | 〃 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昭和40.1 |
お問い合わせ先
京都市 交通局企画総務部企画総務課
電話:(企画担当)075-863-5031、(調査担当)075-863-5035、(契約・入札担当)075-863-5095
ファックス:075-863-5039