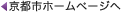【PRチーム】汚泥消化タンク
ページ番号241781
2023年4月21日
汚泥消化タンク


京都市では,汚泥の減量化を図るために汚泥消化を行っており,2018年から「卵形汚泥消化タンク」という施設を導入しています。
汚泥消化タンク築造の流れは,こちらの動画から。

下水をきれいにする過程で,微生物が有機物(汚れ)を食べる処理があります。汚泥とは,有機物(汚れ)を食べ終えた微生物のかたまりのことです。京都市では,毎日約85万㎥の下水をきれいにする過程で,日々360トンもの汚泥が発生しています(平成29年度実績)。

汚泥消化タンクは,酸素が少ない条件において,微生物の働きによって汚泥を消化(発酵)し,メタンガスを発生することができます。
メタンガスは,エネルギーとして使用できるため,汚泥を燃やす処理を行う焼却炉の燃料として有効に利用しています。また,消化させることで有機分を減らし,汚泥量を減少する役割もあります。
下水汚泥の有効利用について詳しく知りたい方はこちら。

汚泥消化タンクには,色々な種類(円筒形,亀甲形,卵形)がありますが,卵形汚泥消化タンクには次のような特長があります。
1.工事コスト縮減効果
消化効率が高く,狭い用地面積で済むため,築造コストが低減でき,全体事業費を縮減できます。
2.メンテナンスコスト縮減効果
内部が滑らかな曲線構造のため,砂等の堆積を防ぐことができます。そのため,攪拌効率が高く,維持管理が容易となり,ランニングコストが大幅に縮減できます。