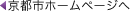岡崎の歴史
ページ番号332983
2024年9月30日
1200年の歴史からひも解く岡崎
平安時代の岡崎
平安京の東に位置するこの一帯は、白河と呼ばれ、平安時代末期には、院政が執り行われた白河殿のほか、法勝寺をはじめとする6つの寺院(六勝寺)の大伽藍が造営され、栄華をきわめました。これらの建物は鎌倉時代にかけて焼失し、その後、13世紀末に編纂されたとみられる歴史書の中に「岡崎」の地名が見られます。

(図 :六勝寺復原図 作画 - 梶川敏夫氏)
近代化を牽引してきた岡崎
幕末の騒乱や東京遷都により京都が衰微するなか、殖産興業策の一つとして、琵琶湖疏水が計画されました。明治23年に第1疏水が竣工し、水運や灌漑用水のほか、水力発電による電力を提供するなど、京都の近代化の礎を築きました。明治28年には、工業都市としての発展や京都の圧倒的な文化度を内外にアピールする一大事業として、政府主催の内国勧業博覧会と、平安遷都1100年紀念祭が同時開催されました。博覧会会場には、紀念祭の象徴として平安神宮が創建され、各種のパビリオンが設けられたほか、奉祝の行事として時代祭が実施されました。
博覧会跡地には、岡崎公園が開設し(明治37年)、その後も様々な博覧会の会場となりました。さらに、図書館や勧業館、公会堂、美術館などの様々な文化施設が建てられ、徐々に文化ゾーンを形成していきました。また、周辺一帯では、疏水を契機に新市街開発が進められ、東山山麓では、風致保全とあわせた別荘地の開発が進み、疏水の水を活用した庭園群(小川治兵衛の作庭による庭も多い)が形成されました。

(写真:平安神宮地鎮祭の余興 明治26[1893]年)

(写真:大礼記念京都大博覧会 応天門ヨリ見タル東会場 昭和3[1928]年 『大礼記念京都大博覧会写真帖』より 京都岡崎魅力づくり推進協議会所蔵)

(写真:明治40年頃の蹴上インクライン)

(写真:昭和8年頃の京都市美術館)
戦後の岡崎
戦後、一部施設が米軍に接収されていましたが、国際文化観光都市を標榜して、昭和35年に京都会館が建てられ、昭和末期から平成にかけて、京都国立近代美術館(昭和61年)、京都市国際交流会館(平成元年)、京都市勧業館みやこめっせ(平成8年)など、新たな施設の建設や機能更新が進められました。これにより、岡崎地域の文化交流ゾーンとしての地位は確固たるものとなりました。

(写真:昭和40年頃の京都会館)

(写真:同時期の京都会館 中庭)
お問い合わせ先
京都市 左京区役所地域力推進室
電話:庶務075-702-1001 防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1021 まちづくり075-702-1029
ファックス:庶務・防災・統計・選挙・企画・広報075-702-1301 まちづくり075-702-1303