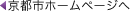松ヶ崎題目踊・さし踊
ページ番号24265
2007年12月17日
月日:8月15日,16日 場所:涌泉寺
13世紀末,天台宗派の強かった松ヶ崎に,法華宗が伝えられ,僧実眼(じつげん)は,自ら住職を務める寺を法華宗に改宗し,松ヶ崎の住人たちに法華経のありがたさを説きました。そして,1306年,村人たちが一人残らず改宗したのを見た実眼は,歓喜のあまり飛びはねて自ら太鼓を打ち鳴らし,南無妙法蓮華経と音頭を取り始めたと伝わっています。居合わせた村人たちもお題目を唱え,日本最古の盆踊りといわれる「松ヶ崎題目踊」が始まりました。
男女とも背中に妙法と染め抜かれた浴衣,男性は角帯,腰に手拭い,女性は三幅(みはば)前垂れに赤襷(あかたすき)の衣装で,右手に扇子を持ち,題目音頭に合わせて踊ります。
さし踊は,楽器を用いず,男性の音頭取り衆の音頭に合わせ,櫓(やぐら)の周りを輪になって踊ります。