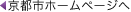観光冊子「裏を往く~あなたの知らない北区~」番外編: 左大文字保存会の岡本会長にインタビューしました!
ページ番号248521
2019年3月22日
観光冊子「裏を往く~あなたの知らない北区~」番外編: 左大文字保存会の岡本会長にインタビュー!
本ページでは,観光冊子「裏を往く~あなたの知らない北区~」を深堀するインタビュー内容を掲載します。
伝統の灯を継承し続ける「左大文字保存会」会長の岡本芳雄様に御協力いただきました。
昨年に引き続き,左大文字保存会様のご好意で五山の送り火を体験した,若手職員ならではの質問で「裏」北区を紹介します。
左大文字保存会について
【質問】
左大文字保存会はどのよう方々で構成されているのでしょうか。一般の方は参加できないのでしょうか。
【岡本会長】
地元(衣笠街道町を中心に金閣寺周辺の町内)に住んでいる方のみで構成する団体で,中学1年生から加入でき,現在70名ほどの会員がいます。
従前は,保存会に入るのは地元の直系の男系家族で生まれた男性のみでした。しかし,少子化の流れなどもあり,2年前より女系家族で生まれた男性も入会できるようになりました。
【質問】
当保存会は,年間を通してどのような活動されているのでしょうか。やはり準備が大変なのでしょうか。
【岡本会長】
8月の本番に至るまでの準備が大事です。
具体的には,年間を通しての山道整備,火床修理,遮蔽木や松枯れ,楢枯れの木々の伐採,下刈などの準備を行い,8月の本番を迎えます。
伝統を紡ぐ人々について
【質問】
左大文字保存会の方々の中には,数珠を掛けておられる方がたくさんいました。何か意味があるのでしょうか。
また,親火松明を山頂まで運ぶ方は一人と聞いていますが,どのような方がされるのでしょうか。
【岡本会長】
数珠を掛けている人は15年以上従事者で,主に京都市市長表彰を受賞した人です。お盆の前に表彰式があり,その記念に保存会から数珠を渡しています。
親火松明は,原則として,その年に市長表彰を受賞した保存会員の若者が,一人で山頂まで担いで上がります。

蓮華台から親火松明に火を移す様子
火が灯るまで
【質問】
8月16日午後7時ごろ,菩提寺である法音寺から,山上へ向かう松明行列は圧巻でした。松明行列はいつ頃から始まったのでしょうか。
【岡本会長】
松明行列は昭和35年頃から始まりました(岡本会長が16歳くらいの時だそうです)。それまでは他の4山と同様,松明を運ばずに山上で待機し,点火時刻になると火床に直接,点火していました。
また,松明行列は先祖の霊をお送りする宗教行事を忠実に再現しており,これを始めたのが私の4代前の会長である椙村隆輝(すぎむらたかてる)さんです。彼は菩提寺である法音寺の先代の住職と兄弟で,松明行列を始めたほか,街道筋に門火台,法音寺に蓮華台を設置しました。

法音寺に設置されている蓮華台
今昔で変わった物事
【質問】
伝統行事である「左大文字送り火」ですが,昔と比べて変わったことはありますか。逆に変わらないことは何ですか。
【岡本会長】
昔の「大」の字は短く,昭和36年に火床の数を43基から53基に増やしました。
燃やす物も変わりました。元々,松割木ではなく,農作物を作るのに使っていた蔓を誘引する支柱(松,杉やクヌギで作った杭)を点火資材として燃やしていました。
また,燃えるにつれて,積み上げた松割木が崩れやすく,一気に炎が小さくなる火床が多くありました。それを防ぐ為に,昭和50年から鉄の支柱を使って設置しました。そうすることで,美しい「大」の文字を作り出すことができるようになりました。
逆に,今でも変わらないものは,精神的なもの。ご先祖さんをお送りするという気持ちです。
左大文字保存会 岡本会長
活動内容についてはコチラから!~北区の文化を伝える本~
昨年,北区の幅広い文化を一同にまとめた「北区の文化を伝える本」を作成しました。
若手職員が,実際に「左大文字送り火」に参加し,記録した「京都五山送り火(左大文字)体験レポート」を掲載していますので,ご覧ください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/digitalbook/page/0000000298.html
問合せ
北区役所地域力推進室庶務担当 TEL:075-432-1197
お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室総務・防災担当
電話:庶務担当:075-432-1197、地域防災担当:075-432-1197、統計調査担当:075-432-1199
ファックス:075-432-0388