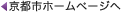琵琶湖疏水施設 国宝・重要文化財への指定について
ページ番号341284
2025年5月16日
24か所が重要文化財に、うち5か所が国宝に指定
本日、国の文化審議会において、琵琶湖疏水の諸施設を国宝・重要文化財に新たに指定することについて、答申が出されました。
琵琶湖疏水は、明治23年の竣工以来、豊かな水の恵みで、京都市民の皆様のくらしを守り、まちの産業や文化を支えており、水道、水力発電、舟運、かんがい、庭園、防火用水等、総合的な役割を通じて、明治維新において衰退の危機に瀕した京都のまちの再生と発展を支えた都市基盤施設です。
今般の答申では、「西洋技術の習得過程にあった明治中期において、当時の土木技術の粋を集めて築かれ、世界的に高い評価を得た、類い希なる構造物であり、明治日本における都市基盤施設の金字塔である」と高い評価を受けました。
「重要文化財」として指定される施設は、大津市から京都市にかけて、24か所の施設で、そのうち、5か所が「国宝」として指定されることとなりました。今後、官報告示を経て、国宝・重要文化財(建造物)となる予定です。
今もなお、現役で活躍している琵琶湖疏水の役割や価値を将来にわたって継承するとともに、魅力創造・情報発信を更に進め、文化を基軸としたまちの魅力・豊かさの向上につなげてまいります。
国宝・重要文化財として指定されるもの:琵琶湖疏水施設24か所
国宝 5か所(4所、1基)
近代京都を象徴する、明治日本における都市基盤施設の金字塔
| 施設名 | 所在地 | 施設管理者 | 建設年 |
|---|---|---|---|
| 第一隧道 | 京都市 滋賀県大津市 | 京都市 | 明治23年 |
| 第二隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治21年 |
| 第三隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治22年 |
| インクライン | 京都市 | 京都市 | 明治22年 |
| 南禅寺水路閣 | 京都市 | 京都市 | 明治21年 |
文化審議会の答申内容
琵琶湖の湖水を京都へ疏通し、舟運、灌漑(かんがい)、防火、発電、水道といった多岐の機能を果たす長大な運河の構成施設。西洋技術の習得過程にあった明治中期において、当時の土木技術の粋を集めて築かれ、世界的に高い評価を得た類い希なる構造物であり、明治日本における都市基盤施設の金字塔。自然と人工、伝統と近代の景観が織りなす京都の比類ない風致を育んだ琵琶湖疏水の代表的遺構であり、文化史的意義も極めて深い。また、近代の土木構造物としては、初めての国宝となる。
重要文化財 24か所(16所、4基、4棟)
近代京都の形成に大きく寄与した長大な運河とその関連施設
国宝の5か所に加え、以下の19か所が指定される
| 施設名 | 所在地 | 施設管理者 | 建設年 |
|---|---|---|---|
| 大津閘門及び堰門 | 滋賀県大津市 | 京都市 | 明治22年 |
| 大津運河 | 滋賀県大津市 | 京都市 | 明治20年 |
| 安朱川水路橋 | 京都市 | 京都市 | 明治23年 |
| 第一〇号橋 | 京都市 | 京都市 | 明治37年 |
| 第一一号橋 | 京都市 | 京都市 | 明治36年 |
| 夷川閘門 | 京都市 | 京都市 | 明治23年 |
| 第五隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治23年 |
| 第六隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治21年 |
| 日岡隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 新旧両水連絡洗堰 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 合流隧道 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 蹴上放水所 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 七瀬川放水所 | 京都市 | 京都市 | 明治44年 |
| 蹴上浄水場第一高区 配水池 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 旧御所水道大日山水源地喞筒所 | 京都市 | 京都市 | 明治45年 |
| 蹴上発電所旧本館 | 京都市 | 関西電力株式会社 | 明治45年 |
| 夷川発電所本館 | 京都市 | 関西電力株式会社 | 大正3年 |
| 伏見発電所本館 | 京都市 | 関西電力株式会社 | 大正3年 |
| 本願寺水道水源池 | 京都市 | 宗教法人真宗大谷派 | 明治27年 |
名称は、竣工当時の記録による(現在の名称と異なるものがある)。
文化審議会の答申内容
琵琶湖の湖水を京都へと疏通する長大な運河とその関連施設。舟運、灌漑(かんがい)、防火、発電、水道等の都市近代化に係る多岐にわたる機能を集約した大規模な施設。特に新技術を積極的に導入し、建設当時我が国最長規模を誇った第一隧道は、近代トンネルの規範的存在。明治維新後に衰頽した京都の再興を支えた、京都の近代化を象徴する都市基盤施設。
附(つけたり)指定 337点
上記施設に関連する備品や文書などであり、附属的に指定されるもの。以下、所有者は、京都市と個人。
- 水車1台、発電機1台(水力発電用の機器)
- ヴェンチュリーメーター 5台(水の流量を計測する機械)
- カンテラ 1個
- 導火線 1本(個人所有)
- 関係文書 328点(一部、個人所有)
参考1 琵琶湖疏水について
琵琶湖疏水は、明治期における事実上の東京遷都によって衰退の危機に瀕した京都の復興のため建設されました。
琵琶湖疏水の完成によって、琵琶湖から京都へ運ばれてくる豊かな水は、水道、水力発電、舟運、かんがい、防火用水、庭園用水など多目的に利用され、京都の経済や産業、文化を発展させました。
これまで、琵琶湖疏水は、平成8年に第1疏水関連施設の12か所が国の史跡に指定され、平成19年には、経済産業省により近代化産業遺産として認定されました。
また、陸上交通の発達などの影響によって昭和26年に途絶えた舟運は、平成30年に、約70年ぶりに観光船「びわ湖疏水船」として復活しました。
そして、令和2年6月には、琵琶湖疏水のストーリー「京都と大津を繋ぐ希望の水路 琵琶湖疏水 ~舟に乗り、歩いて触れる明治のひととき」が、日本遺産に認定されました。
京都を再生と飛躍に導き、現在のまちの姿を形づくった琵琶湖疏水は、今も現役の施設として、豊かな水の恵みで、市民の皆様のくらしを守り、まちの産業や文化を支えています。
参考2 国宝・重要文化財について
制度の概要
建造物、工芸品、彫刻、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料などの有形の文化
的所産で、我が国にとって歴史上、芸術上、学術上価値の高いものを総称して「有形文
化財」と呼んでいます。このうち、重要なものを「重要文化財」に指定し、さらに世界
文化の見地から特に価値の高いものを「国宝」に指定して保護を図っています。
指定基準
重要文化財(建造物)の指定基準
建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号の一に該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの
ア 意匠的に優秀なもの
イ 技術的に優秀なもの
ウ 歴史的価値の高いもの
エ 学術的価値の高いもの
オ 流派的又は地方的特色において顕著なもの
国宝の指定基準
重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的意義の特に深いもの
現在の指定件数
重要文化財に指定されている建造物は、令和7年5月1日現在で、2,589件(5,532棟)で、そのうち国宝は、232件(298棟)です。232件の国宝のうち、ほとんどは、近世以前のものであり、近代における建造物の国宝は3件(5棟)です。今回、琵琶湖疏水の施設が国宝に指定されると、4件目になります。また、近代の土木構造物としては、初めての国宝となります。
報道発表資料
発表日
令和7年5月16日
担当課
- 文化財に関すること
京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課(075-222-3130) - 琵琶湖疏水に関すること
京都市上下水道局総務部総務課(075-672-7810)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
上下水道局総務部総務課
電話:075-672-7810
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝及び年末年始を除く。)