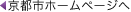10月7日(火曜日)「北区『WAのこころ』創生講座‐文化のWA‐」第4回を開講しました。
ページ番号346737
2025年10月7日
令和7年度の4回目は、都山流尺八奏者の三好芫山(げんざん) 様、生田流箏曲 三好晃子 様にご登壇いただきました。
会場には、様々な素材や大きさの尺八とお箏(こと)をご持参いただき、実際に楽器を鳴らしたり演奏したりしながら、その歴史と特徴をお話しいただきました。
河村晴久先生との対談では、「虚無僧が吹いているイメージ」の尺八は、どこから来るのか?という分かりやすいところからお話が始まりました。三好先生によると、飛鳥時代に持ち込まれた尺八は、修行のための「法器」として「吹禅(すいぜん)」に使用されていたので、元々は、西洋音楽のように分かりやすいメロディを奏でるものではなかったと。まさに「虚無僧」のイメージですね。
それが、明治以降、ピアノをはじめとする西洋音楽の普及と共に、「楽器」(音楽を奏でるためのもの)と認識され、それに伴って、楽曲も変わっていったそうです。
江戸時代までは、和楽器の5音の音階で吹かれていた尺八ですが、西洋音楽や西洋楽器との合奏も行われる現在では、穴のふさぎ方、息の吹き方などを加減することによって、ドレミファソラシドの音階が出るように工夫されているのだとか。長い歴史のある楽器ですが、時代ごとに、位置付けや演奏方法に変遷が見られるのですね。
「西洋の音楽は美しい音を追求しているが、尺八は汚い音(かすれた音や複数の音が交ざり合った音)も追求する」といったお話や、また、どんな管でも、名人の手に掛かれば楽器になる、ということで、水道管の管で作った尺八を実際に吹いてみせていただきました。大変興味深かったです。さらに、こういったことを、遊びでやっている訳ではなく、高価になりがちな和楽器に、どうやって気軽に触れてもらえるか、興味を持ってもらえるかを考え、楽器でないものも楽器となり、音を楽しむ取組をしておられることに感服しました。
何より、今日は、目の前で尺八と箏の演奏をしていただき、その豊かな音を全身に浴びられたことが、実に貴重で豊かな体験でした。やはり「ほんまもん」は素晴らしいですね。こんなに素晴らしい体験が出来る機会を頂けるのは、本当にありがたいことです。
また、三好晃子様から、箏の歴史や特徴についてもお話があり、こちらも大変勉強になりました。お二人の合奏による「春の海」は、お正月などに聞き馴染みのあるものですが、名人のお二人による生演奏は、また格別で、会場の皆様も、しんと聴き入っておられました。
しかし、ほかの分野と同じく、邦楽の世界においても、次世代への継承が大きな課題になっているそうです。そこで、三好様は、流派を超えた一大コンサートを企画されているとのこと。多くの人が行き交う京都駅ビル室町広場で、どなた様もお気軽に聞いていただける観覧無料の大コンサート「全日本尺八大会Ⅱ」を予定されているそうです。ご興味を持たれた方には、是非、足を運んでいただきたいです。(詳細は、下をご覧ください。)
次回の講座は、12月2日(火曜日)、京都市考古資料館 館長 山本 雅和 様をお招きし、「北区にのこる御土居」をテーマにお話しいただきます。本講座はどなたでも無料で受講いただけますので、気軽にお申込みください。オンライン受講も可能ですよ!
北区長 川妻 聖枝
■北区「WAのこころ」創生講座について
http://https://www.city.kyoto.lg.jp/kita/page/0000337877.html![]()
■ 全日本尺八大会Ⅱについて
・日時 2025年10月13日 12時~
・場所 京都駅ビル室町小路広場(大階段)
・出演 中尾都風, 三好芫山, 坂田誠山, 石川利光, 小湊昭尚, 川瀬順輔, 谷保範, 雲井雅人, ジョン・海山・ネプチューン
・曲目 12時~ 各流派による演奏、15時~ プロによる演奏、16時~ 全員による演奏
・料金 観覧無料
詳しくは、こちら![]()
※ただいま、寄付も募られています。詳しくは、こちら![]()




お問い合わせ先
京都市 北区役所地域力推進室まちづくり担当
電話:企画連携担当、事業担当、広聴・地域コミュニティ活性化担当、振興担当:075-432-1208
ファックス:075-441-3282