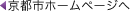令和6年度 上京民生児童委員会 第2回 障害者福祉専門部会研修会について
ページ番号334889
2025年2月17日
障害者福祉専門部会研修会の実施
上京区役所と上京民生児童委員会とが連携して、上京民生児童委員会 第2回障害者福祉専門部会の研修会を実施しました。今回は、「聴覚障害の基礎知識と聴覚障害のある方とのコミュニケーション」と題して、京都府聴覚言語障害センターから、今西和弘センター長、森さやか様、尾上友菜様をお招きし、聴覚障害の基礎知識や聴覚障害のある方とのコミュニケーションの方法について教わりました。
前半のお話では、聴覚障害の方はどのような聞こえ方をするのか、聴覚障害の方との具体的なコミュニケーションの手段などについて、当事者の方のお話も交えて学びました。後半では、手話入門として、簡単な挨拶やよく使用する表現を教わり実際に受講者同士で使ってみたり、聞こえない体験を実際にして対応を考える体験実習など、聴覚障害のある方とのコミュニケーション方法について、実践的に学ぶことができました。
最後に、研修の受講者には「聞こえのサポーター認定証」が配られました。聴覚障害の方がより暮らしやすい社会になるように、地域で「聞こえ」のサポーターがもっと増えたらいいなと思います。
京都市手話言語条例について
京都市では、平成28年3月25日、「京都市手話言語がつなぐ心豊かな共生社会を目指す条例」(手話言語条例)が、市会議員全員により提案され、全会一致で可決のうえ制定、同年4月1日に施行されました。
この条例では、手話への理解促進・普及をすすめ、全ての人が相互に人格と個性を尊重することを基本理念に、豊かな共生社会を実現することを目指しています。
「手話は言語」を合言葉に、手話による自由なコミュニケーションが保障される社会を構築していきましょう。
(補足)専門部会は、生活支援・防災、高齢者福祉、障害者福祉及び児童母子福祉の4部会で構成されています
対象
障害者福祉専門部会所属の民生委員・児童委員及び主任児童委員 49人
研修会の様子




研修会
(1)日時
令和6年11月19日 火曜日 14時00分から
(2)場所
上京区役所 4階 大会議室
(3) 概要
京都府聴覚言語障害センター 今西和弘センター長、森さやか様、尾上友菜様による講座、体験実習
- 聴覚障害への理解を深める
- 手話言語条例と合理的配慮について
- 聴覚障害のある方とのコミュニケーション手段(筆談・ジェスチャー・字幕・メール等)
- 手話入門(簡単な挨拶・よく使用する表現)
- 体験実習(聞こえない体験・聞こえない人への対応を考える)
参考
民生委員・児童委員について
厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員であり、学区内の各々の担当エリアにおいて、援助を必要とする住民の生活に関する相談に応じたり、助言等の援助を行うことを主な職務とし、福祉行政の協力者として重要な役割を担うとともに、地域の諸団体とも連携して様々な福祉活動を展開しています。また、民生委員に委嘱された方は、児童福祉法の規定により、児童委員を兼ねることとされています。
主任児童委員について
主任児童委員は、学区全体において児童福祉に関する問題を専門的に担当する児童委員で、児童福祉関係機関や児童委員との連絡調整を密にし、民生委員・児童委員の活動に対する援助、協力を行っています。
人数等
- 民生委員・児童委員 159人(上京区)
- 主任児童委員 36人(上京区)
問合せ
上京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課地域支援担当(2階26番窓口)
電話:075-441-2871 FAX:075-441-0180
お問い合わせ先
上京区役所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課地域支援担当(2階26番窓口)
電話:075-441-2871 FAX:075-441-0180